2004-03-31
●死に花 (Shinihana/2004/Inudo Isshin)(犬童一心)
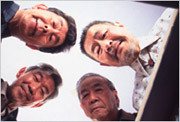
◆事務所のなかを抜けて試写室に行くなんて風情は、テロだなんだと騒いでたださえ過剰警戒になりがちないまどき、大映ぐらいにしかないだろう。昔の新聞社や雑誌社のなかはそうだった。いつまでもこうでありたい。試写室の環境は大分老朽化してはいるのだが。
◆老人ホームといっても、個室にバーがあったり、死に慣れるために棺桶を買って持っているといったことが可能な相当豪華な老人ホームのちょっとはずれた老人たちの話。人間なんてみな個々にはユニークなのに、習慣上自分を偽ったり、演じたりしているにすぎない。が、そのまま描いては映画にならないという通念があるので、映画の登場人物たちは、「普通」ではなくなる。この映画も、その路線。それは、途中までは成功している。楽しめる。しかし、後半でドタバタになってしまう。どうせ「夢」を描くなら、最後まで夢を見させてほしい。
◆源田金蔵(藤岡琢也)は、同じホームの鈴子(加藤治子)を愛し、風呂で抱き合っているような、まあ「自由」な老人生活を送っている。死んだら入れてもらう棺桶も買い、自室に置いて、そこに入ったりして、死の準備をしている。だから、彼が80歳で死んだときは、葬式のやり方もすべて計画済だった。司会の映像を作り、「メモリアル・アーティスト」(ミッキー・カーチス)率いるスタッフのもと、ジャズ演奏(白髪の鈴木章治が出演している)から飲み物まで完璧にセットアップされたパーティが仕組まれる。しかし、彼の計画はこれだけではなかった。
◆このシーンは、いまどきありがちな金持ち老人の未練のようなものを感じさせて、面白くもないのだが、彼の棺が運ばれた火葬場で起こる事件のシーンは、はっとさせる。焼き終った遺体を引き出したとき、そこに2体の骨があったのだ。なるほど、こういうやり方もあるのかという思い。意外性があって、このシーンはすばらしい。
◆元映画監督の菊地真(山崎努)は、源田から託されたフロッピーをプリントアウトして驚く。そこには、隅田川沿いの土手から銀行ビルの地下まで掘り抜き、金庫から金を奪う計画が詳細に記されていた。そこから、にわかに、菊島の恋人で大学教授未亡人明日香(松原智恵子――けっこういい感じに歳をとった)からその情報がながれ、同じホームの仲間たちの庄司(谷啓)、穴池(青島幸男)、そしてとりわけ、元銀行支店長で銀行界には恨みのある伊能(宇津井健)が乗り気になる。穴を掘るのに最適な場所にブルーテント・ハウスを作って住んでいる「ホームレス」の先山(長門勇)も加わって、たちまち計画が実行に移される。
◆資金は、菊地が映画を撮るために貯めたが使われなかったという数千万円。しかし、これでレンタルしたジェット噴射のカッターとか、作業場として借りた大きな倉庫、その作業、そして、「たまたま」掘り当てた戦時下の防空壕・・・このへんになると、とたんに話が非現実化する。みな70すぎの老人だから、穴を掘りながらすぐにへたる。すると山崎などは、よく水を飲む。肉体労働をしながらあんなに水を飲んだら、とても息が続かなくなるもの。穴がほとんど空いて、いざというとき、台風が来て、穴に水が侵入し、ビルが倒壊する。しかし、そのとき、街で騒ぎにならず、パトカーも来ない。変ではないか! いまの時代、隅田川沿いのビルが倒壊したら、自衛隊までやって来るだろう。
◆いま、老人たちにかぎらず、人々は、仲間を作れないことで孤立している。老人ホームで彼らのようにすでにくったくのない仲間でいられる連中は、それ以上何もやる必要はないのではないか? ふだんはたがいに不信と嫉妬をいだきあっている個々人が、一つのきっかけで連帯するというのなら、面白い。しかし、最初から(いつも菊島の部屋のバーの集まったりして)仲良くやっている連中がこういう「共同事業」をやると、「夢」にもならなくなる。
◆どのみち他愛のないエンターテイメントなら、「たまたま」掘り当てた防空壕が、実は、このホームで最長老の青木(森繁久弥)が戦中に家族を失った防空壕で、源田の「死に花」計画の本当のねらいはここになったなどというひねりなどやめたほうがよかっただろう。もし、見るのなら、この映画は、あちこちで姿をあらわすカメオ出演(?)の「有名人」たちの姿とか、この老人ホームに職員としてやって来る若い女性井上(星野真理)と老人たちのやりとりとか、褒美に桃の缶詰をたらふく食う(『三匹の侍』以来変わらぬ)飄々とした風情の長門のような「記念物」に会えることか?
◆犬童一心は、『金髪の草原』で老化へのユニークなアプローチを見せた。主演した伊勢谷友介もいいスター俳優になった。『ジョゼと虎と魚たち』も、生き方への一つの切り込みを見せた。この映画では、「人生は楽しむためにあるもの」というのがこの映画のテーマのようだが、どうも、こういう考えは、犬童にはしっくりしないのかもしれない。それよりも、彼は、若者の描きかたがうまい。この映画でも、星野真理のは今後、映画でもいい仕事をするだろう。
(東映第1試写室)
2004-03-29
●ホーンテッドマンション (The Haunted Mansion/2003/Rob Minkoff)(ロブ・ミンコフ)

◆映画としての評価は高くないのだが、イギリスでかなりのヒットを記録したので、是非見てみたいと思っていた。ついつい他を優先し、見るのが今日になった。が、なぜ当たったかはよくわからなかった。テレンス・スタンプはいい演技をしていたし、マーシャ・トマソンが不思議な魅力を発散していたが、これだけでイギリスの観客を動員できるだろうか?
◆おやじのジム(エディー・マーフィ)がやり手の不動産屋。どんどん仕事を入れてしまうので妻のサラ(マーシャ・トマソン)はあきれている。ファミリーが問題にはなっているが、喜劇仕立てということもあり、アメリカの家庭としては「平和」なほう。家庭なんて、なんかのきしみや悩みがないほうがおかしいのであるから、この家庭はごく普通と言ってよい。約束をたびたびホゴにしてきたおやじが、すまんすまん、内心しょうがねぇというわけで、ある日、車で2人の子供と妻を旅行に連れ出すことにする。ところが、出がけに「仕事」がとびこんでくる。ま、なんとかなるさと、ジムは、ちょっと寄り道してその物件を見て、それから目的地へ行こうと、家族連れで出かける。
◆エディー・マーフィの盛りはすぎた。それは、彼は、ちょっとした街のワルガキ的な「悪」は演じられても、本格的な「悪」には向かないからだ。いまのアメリカでは、「お人好し」やこの手のキャラクターはお呼びでない。おそらく、このへんが、アメリカでよりもイギリスでこの映画がウケた理由の一つかもしれない。ファミリーが危険にさらされるがみんなでがんばって、危険をのがれる話だから、結局家族第一の話ではあるのだが、ひどく深刻なまでにあぶなくなっている家族が、危機のすえにその結束をとりもどすといったきまじめさはない。そこがいい。
◆原題は、「幽霊屋敷」であり、単純明解だ。
◆『スリーピー・ホロウ』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』でもそうだったが、「過去」が適性な「未来」に向かって投企(プロジェクト)されなくて、そのため「現在」という時間性のなかで(普通ならすでにその機能をやりとげたり、吸収されつくされたりしているはずなのに)往生できないでさまよっている――というテーマは、くりかえし使われる。日本でも、「因果応報」とか「祖霊信仰」などの考えでは、「過去」が適性に治まることが望ましいとされる。『陰陽師』や『陰陽師 II』は、恨みをのんで死んだ者たちの治まらない「霊」があらぶり、それをしずめる話である。
◆冒頭、52室もある鬱蒼とした「幽霊屋敷」の主人エドワード(ナサニエル・パーカー)が愛の手紙を書き、封をする。封を赤いパラフィンでするところをみると、時代は19世紀以前。次の場面では、彼はぐったりした女性をかかえている。そして首を吊っての自死。ジムのところに屋敷を処分したいという電話をしてきたのは、エドワードの執事ラムズリー(テレンス・スタンプ)。むろん、彼も「幽霊」。
◆ラムズレーのような「お家大事」で自分を犠牲にする「執事」のような存在ほど、困ったものはない。ブッシュ政権だって、会社だって、必ずこういうのがいて、悪の根源になっている。国家的なもの、家庭的なものが終焉するポストモダンの時代、この映画は、「執事」がいなくてもやっていける集団と、そうでない旧来の集団との違いを見せてくれもする。
◆屋敷は迷路のようになっていて、廊下にずらりと「泰西の名画」がならんでいる。最近のパロディ画で有名になったジャック・ルイ・ダヴィッドの「騎乗のナポレオン」なんかもある。そして、その一枚には、エドワードが愛した女性の肖像。その顔は、サラにそっくり。同じにするために、端正で不思議な魅力のある表情のマーシャ・トマソンが選ばれた。
◆ヴァーチャルな映像技術は駆使されている。その秀逸は、庭園のある4人の胸像が陽気に歌うシーン。クレジットには、「ザ・シンギング・バスツ」となづけられている。ジムたちにアドバイズして危機を救うクリスタル・ボールのなかに首人間マダム・リオッタ(ジェニファー・ティリー)がいるホログラム的な仕掛けは安すぎる。鏡のなかの自分の顔が腐っているのにジムが驚くシーンは、仕掛けは簡単でも面白い。
◆エドワードが手紙に封印するとき、封筒のフラップの三角の頂点に溶けたパラフィンを丸く押しつける。これは、19世紀以前には普通に行われた手紙の習慣だが、封がフラップの角の部分だけしかなされていない点に興味を持った。受け取った者は、その部分をはずしてなかから便箋を出すわけだが、いま(といっても電子メールに移行しているが)の時代、手紙の封は、普通べったり糊付けしてしまう。わたしのような無精者は、この10年ぐらい電子メール優先で、封書は、指で封を開けられないものは見ない。でも、昔のパラフィンの封なら、指でも開けてわけだ。封だパスワードだと隠蔽主義は近代にエスカレートする。
(ブエナビスタ試写室)
2004-03-25
●アップルシード (Appleseed/2004/Masamune Shirow)(士郎正宗)

◆またまた世界を2分するスケールの大きいSF的ドラマ。なんで日本の「未来」ものは、グローバル・サイズが好きなんだろう? 時代は2131年。やはり世界戦争があり、どの国も勝利せず、世界は疲弊している。この映画の舞台は、そうした戦後に生まれた「地球全土を統合する」オリュンポス。ここで平和路線を守るのは、人間ではなく、女性バイオロイドのアテナ行政総監らだ。逆に人間は、ウラノス将軍に率いられ、オリュンポス正規軍を組織し、バイオロイドを皆殺しにしようとチャンスをねらっている。
◆映画は、女性兵士として大戦を生き抜いたデュナンが、廃墟と化した街のなかを彷徨しているところからはじまる。彼女は、西欧ではポルノアニメにまで使われるようになった典型的な少女コミックの目をしたキャラ。彼女の登場とともに、ズンズンドンドンとドラムンベース的な音楽がはじまり、思わず笑ってしまう。10年ぐらい時代がバックした感じがしたからだ。が、次の瞬間、彼女はヘリに襲われ、勇ましく抵抗するが、麻酔銃のようなものを打たれ、逮捕される。
◆平和主義のバイオロイドによる支配という逆説は、好戦的な人間の暴走を防ぐために考案されたプログラムで、そのプロジェクトに関わっていたのが、デュナンの母親だった。彼女は、バイオロイドに戦闘意志を持たせることを拒否したために殺された。この映画の大詰めは、バイオロイドに戦闘プログラムを与えようとする一派とそれを阻止しようとする者たちとの闘いであり、最初から予測できるように、デュナンがその阻止のために英雄的な活躍をする。しかし、その大詰めが、コンピュータのキーボードに暗証番号を入れ、あと一文字入れるかどうかといった単純極まりないアクションに終始するのはなさけない。これでは、007の時代を一歩も出ないし、いまのコンピュータ・システムでも通用しないではないか。
◆しかし、ブッシュ政権のアメリカの現状を見ていると、バイオロイドやアンドロイドに「良心」をプログラムしてしまい、それを人間に守らせるというのはまんざらでもないと思う人も少なくないかもしれない。しかし、『ホーンテッド・マンション』でも示唆されていたように、「執事」的な原理主義ほど困ったものはない。そもそも、このように考えられる「善」もまた、極めて原理主義的な観念なのだ。そのような「善」は容易にとてつもない「悪」に転化しうる。問題なのは、スウィッチを切り替えるような二者択一的な考え方であり、世界が一つであるべきだと考えがちな単純主義である。
◆「宇宙」とか「地球」という全体概念は欺瞞である。そのような考えをしているかぎり、「平和」は決して訪れない。この映画の世界は、長期にわたって世界大戦(これは、そもそも、世界は一つであるべきだという観念から発する)をやったというのに、ふたたび、「オリュンポス」という一つの統合的単位であり、しかも、この世界は、「七賢老」という人間と「ガイア」というウロトラ・コンピュータとの対話によってコントロールされている。7人の七福神にも似たポンコツ寸前の老人たちが、空中を浮遊しているシーンはなかなかいいし、7人とコンピュータだから、複雑な組み合わせがありえるわけだが、場所的に一つの中心から世界がコントロールされていることには変わりがなく、ここには未来的なものは何もない。
◆世界は、もう、単一なコントロールはできないのであり、大きなものが小さなものをコントロールするというわけでもない。逆に、原子的なもの、分子的なものが世界を崩壊に陥れたり、革命的な変化に持ち込んだりするナノ的可能性はますます高まっている。今日起きている不幸な混乱は、こういう事態を無視し、現状維持のためにその動向に逆らうことから生じている。その意味では、「平和」や「テロ撲滅」などといった「英雄的」な努力をするよりも、一旦全部を放棄――いや、むしろ禅の言葉にある「放下」(ほうげ)――し、細胞から地域にいたる各単位が自発的・自律的に動くようにする必要がある。そういう稀なるチャンスが訪れることを願いながら、わたしは、歳をとっていきたいと思う。
(東宝試写室)
2004-03-24
●キャシャーン (CASSHERN/2004/Kiriya Kazuaki)(紀里谷和明)

◆紀里谷監督がうやうやしい態度で挨拶し、「いま出来上がったばかり」であることを強調。編集しおわったデジタルをそのまま見せるには、イマジカは便利。その意気ごみがたしかに最初には感じられた。いいぞ、という感じ。1920年代のロシアアヴァンギャルドや表現主義のポスターのデザインや、映画『メトロポリス』風の絵柄もうまく使われているように見える映像。しかし、次第に、どこか、ハリウッドのメイジャーな作品で使われた特殊映像のソフトを購入して自分のパソコンにインストールし、一人でオタク的に作ったような感じがしてくる。むろん、たくさん(そうそうたる)役者が出ているし、一人では出来ない映画だが、そう見えるのはなぜか?
◆21世紀になってますます世界戦争的な雰囲気が出てきたこと、ロボット・テクノロジーや遺伝子操作技術、ナノテクノロジーの発達によって、「人間」概念が終るのではないかという予感、これらがこの映画にも御多分に洩れず色濃く反映している。戦争があったら、死んでも戦地におもむかなければならないのではないかといういま進行しつつある観念も、確実にこの映画のもの。世界が、「大亜細亜連邦共和国」と「ヨーロッパ連合」(EUはそのまま?)とに分裂したまま50年戦争をしているという設定。
◆伊勢谷友介演じるキャシャーンは、遺伝子工学の父(寺尾聰)と植物学者の母(樋口可南子)との子。「友達が命をかけて闘っているのに黙って見ていられない」と言い、軍を志願し、戦死する。東(寺尾)は、死なない兵士を作るために「新造細胞」の研究に没頭している。しかし、皮肉なことに、その研究が完成するまえに息子が戦死し、その命を復活させるために、未完成の「新造細胞」を使おうとして、パニックが起きる。そこにはからくりがあり、それが最後にわかるが、形の上では、「新造人間対人間の泥沼の滅亡的な闘いがはじまる。人間への憎悪を集約し、新造人間を統括するのが、ブライ(唐沢寿明)。
◆善玉・悪玉(その最高峰に大滝秀治演じる将軍がいる――彼が会議のとき酸素を吸っているのはありがちな発想だが、自己中的でいい)の区別がはっきりし、そのあいだを揺れ動く東博士、キャシャーン。よくわからない存在は、母ミドリと特別出演の三橋達也が演じる『赤ひげ』的な医者。キャシャーンの恋人のルナ(麻生久美子――あいかわらずの髪型)が多少の未来的希望を託された存在。しかし、問題は、こういうキャラクターの奥行きのなさではなくて、映画の基調が『ロード・オブ・ザ・リング』的な戦争シーンだということ。これは、ゲーム指向から来るのだろうか? ばーんばーんばーん。耳を弄する爆発の音といかにもの音楽。このへん、もう少しなんとかならんか? これじゃ、いつまでたっても、戦争は終らない。まず映画で戦争をやめること。こういう言い方をするのは、単に平和主義の観点からではなく、いまや闘いも、通常は見ることも聞くことも難しい「ナノ」や「ミクロ」のレベルで起こる時代になっているという現状認識からだ。
(イマジカ第1試写室)
2004-03-18
●ウォルター少年と、夏の休日 (Secondhand Lions/2003/Tim McCanlies)(ティム・マッキャンリーズ)

◆100ぐらいある席が満席。知った顔のなかに今野雄二さんの姿もあった。出版関係か、急がしそうに電話している女性が何人もいる。ピッポッパの音があちこちで。いまどき音漏れのするヘッドフォンでウォークマンを聴くのと同様に、ケータイやPDAのボタン確認音をONにしているヒトはアホだと思うのですが。
◆家庭が不幸な孤独な子供と老人との友愛や連帯というテーマは、世界共通だが、アメリカでは1980年代に、家庭・家族の多様化(マイナス面ばかりではないのでそう呼びたい)で親の愛情や庇護を受けられない子供の数が増えた。そういう時代に育ったいまの中年のとって、このテーマは受ける。ハーレイ・ジョエル・オスメントという子役(もうそろそろ限界)は、まさにそういう役柄にうってつけの俳優であり、実際にそういう役でキャリアを築いてきた。この映画では、離婚した母親メイ(キーラ・セジウィック)は、男の定まらない女。息子ウォルター(ハーレイ・ジョエル・オスメント)がじゃまなので、2人の叔父ハブ(ロバート・デュバル)とガース(マイケル・ケイン)が住むテキサスのへんぴな田舎にあずけられる。2人が遠くからメイの姿を見て、ハブが「フッカー(売春婦)を呼んだのか?」と言うところが、メイの感じを形容していて可笑しい。
◆冒頭、ハブとガスが狂喜しながら複葉機に乗って空をとびまわっている。次のシーンでは、ハブはライフルを川のなかに乱射して魚を捕ろうとしている。相当な変人という設定。説明がなければ、2人はホモかと思うだろう。彼らは、電話もテレビも置かず、セールスマンが来ると、銃で追い返す。そういう2人のところにあずけられたのだから、ウォルターはどうしていいかわからないし、2人も子供をもったことがないので、とまどってしまう。しかし、ウォルターは、ソウルからやはりへんぴな田舎の祖母のところへあずけられた『おばあちゃんの家』の都会っ子のサンウようにはぶすくれない。2人が手加減しないのがかえって功を奏して次第にいい連帯関係が出来て行く。
◆ウォルターがあたえらた屋根裏部屋には、海外の色々なホテルのラベルがべたべた貼った大きなトランクがあり、躊躇のすえ、開いてみると、厚いほこりの堆積に下に「美しい」女性の写真が出で来る。子供時代というものは、天井のシミにも色々な想像をたくましくするものだから、このトランクは写真は、ウォルターの好奇心をふくらませる。ある日、おそるおそる(ハブよりとっつきのいい)ガースにそのことを尋ねる。ガスの話は、ウォルターにとって、想像を越えるものだった。2人はその昔、フランスの外人部隊に属しており、居留先の北アフリカで王族の姫ジャズミンに恋をし、波瀾万丈の生活を送ったというのだ。
◆このへんは、『ビッグ・フィッシュ』にちょっと似ている。しかし、重要なのは、物語るという行為によって人と人とが結びつくことだ。ネット時代は、口頭で物語るということが乏しくなるし、また、年長者が年下の者に(「老いの繰り言」や自慢話も含めて)物語を聞かせるという習慣や場がほとんどない。この映画も、『ビッグ・フィッシュ』も、その物語の部分をフラッシュバックで描写するので、物語はそのディスクールとトーンにしか残らないが、いまの時代は、こういうやり方でわずかに物語に接するわけである。ワルター・ベンヤミンが「物語作者」で示唆したように、別に口頭で物語ることだけが物語形式のすべてではない。
◆原題は、「ポンコツのライオン(複数)」であるから、主役はウォルターではなく、ハブとガースである。映画は、成人し、デザイナーをやっているらしいウォルター(ジョシュ・ルーカス)が、1本の電話を受けるところから始まった。それは、2人の訃報を伝える保安管の電話だった。彼は、テキサスに向かうことになるわけだが、そのあいだにそこで暮らした日々が回想されるというスタイルだ。だから、映画としては、老人の生き方を描いたものとしても見ることができる。結婚し、あるいは結婚したかもしれないが、子供のいない老人が、兄弟でもいいし、そうでなくてもいいが、誰かと暮らしている。ウォルターとの出会いは、彼らにとっては、別に親戚の子供でも、子供代わりでもなく、同じ仲間なのだ。ハブとガースは、年令にとらわれない生き方をしているから、幼児であろうと、少年であろうと、仲間であるかそうでないかにすぎない。そして、パーっと散る。
◆「ポンコツのライオン(複数)」の「ライオン」の直接の由来は、金(どこから手に入れたのか――北アフリカで王族の財宝を手に入れたことになっているが、銀行強盗をやったといううわさもある――そのへんのあいまいさは、幼いウォルターの回想というフィルターのせいであり、この映画の物語性でもある)をもてあました2人が、きまぐれに購入した1頭のライオンである。買ってみて、そのライオンは、サーカスではもう使い物にならなくなった「ポンコツ」だったが、最後に1度だけ「野生」をとりもどす。ハブとガスは、「ポンコツのライオン」かもしれないが、しっかり生きているよという感じが哀れっぽくではなく伝わる。
◆この映画も、ポピュリズム、回顧趣味、地域主義(ウォルターにとっては、テキサスの田舎が「故郷」)といった志向が強い。都会主義では決してない。映画としては面白いとしても、そういうテイストに魅惑されているうちに、世の中が変な方向に行きそうな気もする。最近のアメリカ映画の傾向に感じるところ。
(ヘラルド試写室)
2004-03-16
●アメリカン・スプレンダー (American Splendor/2003/Shari Springer Berman & Robert Pulchini)(シャリ・スプリンガー・バーマン&ロバート・プルチーニ)

◆実在のコミック脚本家にしてマルチタレントのハービー・ピーカー本人がナレーションを担当し、その彼と、彼を演じるポール・ジャマッティとが交互に登場し、さらにハービーとロバート・クラムが作ったコミック、「再現」コミックの画面、ハービーが出演したワイドショーのてれびk映像などがたくみに合成される1時間41分。脇役ばかりだったポール・ジャマッティのはまり役。開始まえ、ロビードで中央公論社の白戸直人氏に会う。彼とはときどきメールをやりとりするが、顔をあわすのは、『中央公論』で仕事場の取材をされて以来。
◆ポール・ジアマッティが主役を演るのを見るのははじめて。『トゥルーマン・ショウ』の最後の方で、コントロール・ルームのディレクター役の彼が、エド・ハリスの無慈悲な命令に異議を感じつつも、卑屈な表情でそれに従う屈折した演技が印象に残った。こういう役がうまい。
◆「暗いことばかりだからsplendid(輝く→すばらしい)なことがほしい」というような台詞があったが、それはいまのアメリカにぴったりだ。
◆実在のハービー・ピーカーは、1939年生まれで、1959年にはジャズの評論を書きはじめたという。ジャズにとってこの時代はいい時代だった。植草甚一も、ちょうど同じ時期にジャズに開眼し、ソニー・ロリンズやマイルス・デイヴィスなどのハードバップ・ジャズについて書き始めた。そして1960年代には、氏はニュージャズの最も重要な最新の紹介者になった。ジャズに染まる人間の生き方というのは、どこか偶然まかせというところがある。さもなければジャズには惹かれないだろう。ハービー・ピーカーも植草甚一も、偶然まかせの人生を愛したように思う。そういう人生を生きていると、不満や不遇なことに接することが多いから、多くの日常は、「こんちくしょう」「ファック」「ばかにしやがって」といった呪詛の言葉を吐く毎日である。映画の冒頭、ポール・ジャマッティは、ハービーのそんな人生態度をうまく表現している。
◆ハービーの人生は、出会いによって新しくなるが、その最初の重要な出会いは、ロバート・クラム(ジェームズ・アーバニアク)との出会いである。それは、1960年代の初めに、クリーブランドのガレージ・セールでSPレコードをあさっているときだった。クラムは、クリーブランドの「ボヘミアン・クラウド」(要するにアーティストや自由人)の世界に精通しており、ハービーを案内する。ロバート・クラムにとっても、クラムとの出会いはインスパイアリングなものであったはずであり、ハービーとの出会いなしには、1966年にサンフランシスコに移住し、1968年に『ZAP』でアンダーグラウンド・コミックの寵児になるクラムは存在しなかったかもしれない。なお、クラムについてはすばらしいドキュメンタリー『クラム』(Crumb/1994/Terry Zwigoff) を見てほしい。
◆ハービーが、コミックの脚本を書くきっかけとなったのは、直接にはクラムとの出会いだが、それにくわえて、書類整理のフリーターとして働いていた病院でたまたま目にしたカルテとの出会いもあった。それは、自分がこのまま行くとこんな人生になるのかと思わせる孤独な人生が読み取れる男のカルテだった。家に帰り、彼は、白紙を線で4つに分け、そこに稚拙な省略図形を描き、そのかたわらにせりふを書いて行く。このシーンは、映画やビデオの絵コンテの描き方にも役立つだろう。絵コンテは、かならずしもうまい絵で描かなくてもいいのだ。紙に鉛筆でパパーと線を引いて描く大ざっぱさがなかなかよかった。
◆スーパーに行くと明らかにユダヤ人ぽい老女がレジでねばっている。まず、ババーと割引クーポンを置く。そして、1ダースで4ドルのグラスを6個並べて、これを2ドルで売れと言う。本来12個で4ドルなのだが、あとでもう6個買うからそうしてくれと言う。その保証はないから、レジの店員は躊躇し、レジに列が出来る。このシーンからハービーは、「ユダヤ人の女性はレジでねばる」というギャクを思いつく。また、家の外で労働者が、「普通はバカと同じだよ」というのを耳にし、早速使う。このあたりも「ジャズ的」である。
◆デラウエア州で友人とコミック雑誌専門店を経営ハービーの妻となるジョイス・ブラナー(ホープ・デイヴィス)が、ハービーに電話したのも全くの偶然だった。彼女は、ハービーが脚本を書き、ローバート・クラムが絵を描いたコミックが載っている『アメリカン・スプレンダー』のバックナンバーのストックを補充するために、雑誌社に頼むと時間がかかると思い、直接ハービーから手に入れようと思ったのだった。これが縁で2人は会い(店を放棄してクリーブランドまでのこのこと出てきてしまうジョイスも変わっている)、それほど意気投合したというわけでもないのに、結婚してしまう。これもジャズのノリだ。ジャズ的人生には、向けられたフレーズには(それがどんなものであっても)応えなければならないという「モラル」がある。
◆コミックの仕事が上向き、テレビの「デイヴィッド・レターマン・ショー」に出演して名が売れてきたとき、ハービーの身にハプニングが起きる。下腹部に悪性の腫瘍が出来たのだ。このとき、ハービーは、その「アドリブ」にうまく応えられず、絶望の淵に追いつめられる。再出演した「デイヴィッド・レターマン・ショー」(有名人でもそう何度もこのショウーに出演できない)でも、ハービーは、情緒不安定になり、基本的にオバカ番組であるはずのこのショウーで、GEは家電を売ってるが本当は軍需産業じゃないか(それは本当)といったスポンサー批判をしてしまう。が、こうしたハービーの危機を救ったのはジョイスだった。ハービーよりも社会意識の強い彼女は、彼が「デイヴィッド・レターマン・ショー」な番組に出演するのを快く思っていなかったが、このとき、彼女は、ハービーの癌との闘いのプロセスをコミックにすることを思いつく。癌という「アドリブ」に巧みに応えた彼女は、ハービーのよきパートナー/共演者だったわけだ。
◆ハービーが売れ子になった時期(1980年代後半)、ジョイスは、アメリカの支配とその傀儡政権から独立したエル・サルバドルなどに旅行する。1979年のニカラグア革命以後、ラテン・アメリカはなかなかホットな場所になっており、そういうところへ旅行するジョイスは、ラディカルなことが好きな人間であることを示している。
◆やがて養子にする女の子ダニエル(マディリン・スィーテン)との出会いも、普通なら、それだけで終ってしまいそうな出会いだった。彼女は、化学療法でつらい毎日を送るハービーの絵を担当するようになったフレッド(ジェイムズ・マキャフェリー)の先妻の子供だ。むろん、彼女がかわいい子だったのだろうし、相性もよかったのだろう。ハービーが病気を克服し、検査でOKが出た日、病院から帰った彼をダニエルが(決して劇的にではなく)シャイにぎごちなくハグするシーンがあるが、だしかし、それだけでなく、どんな出会いも新鮮なものとして受け止めてしまうハービーの特質がここにも見出せるような気がする。
◆わたしも、ジャズ的に生きてきたし、いまもそうだが、人生というものは、何とかなってしまうものだ。ハービーには特別の才能が備わっていたのだろうが、その才能の大半は、知識や技能ではなく、ある種のセンス――出会ったものに対し真正につきあい応える繊細さと敏感さ――ではないかと思う。それは、誰でもがまねることができるものではないか? 少なくとも、環境と生活文化のなかで身につけることができるものだろう。先日、「NHKスペッシャル」でフリータについての取材を報道していた。それは、フリーターを「困った存在」として論じていたが、ハービーのような生き方を見ると、そうも思えなくなる。ハービーだって、コミックの脚本を描くことために病院の書類整理という仕事をしていたわけではない。2度目の妻は、彼の生き方のサエないところに愛想をつかしたらしい。ハービーは自分でも自分の嫌気がさしていた。それが、変わって来るのは、彼が、未知なる人とに出会いに真摯だったためだ。フリーターの仕事は、単なる金のため、生活のためと割り切ったら味気ないが、さまざまな出会いのチャンスをあたえる機会とみなすならば、フルタイムの仕事より多彩であるかもしれない。
◆結婚してまもないころ、ハービーとジョイスを映画『オタクの復讐』(Revenge of the Nerd/1983/Ken Kwapis) にさそう「変人」トビー(ジェダ・フリードランダー)が登場する。「純粋オタク」を自認するトビーだが、文章を棒読みにしているような出来すぎた人物像にうんざりしていると、やがて本物のトビー・ラドロフが姿をあらわす。それが、演じられたキャラクターよりももっと「出来上がって」いるのに、大笑い。この男は、ハービーの周辺にいるうちにテレビの目にとまり、MTVの「Week in Rock」に出るようになり、3本のB級映画にも出演しているという。
(ヴァージンシネマズ六本木ヒルズ・スクリーン5)
2004-03-12
●Re:プレイ (The I Inside/2003/Roland Suso Richiter)(ローランド・ゾズ・リヒター)

◆非常にスタイリッシュな作品。またヘラルドの試写室に来た。以前と変わったと思うのは、昔は、かなり混んでいるときでも、最前列に座る人が少なかったが、最近は、後ろががらがらでも、最前列が半分以上埋まっている。わたしは、2、3列で見ることにしている。最前列だと、松竹試写室のように、首をふらないと全部見えないのだ。ひょっとして、最近は広角の水晶体の人が増えたのだろうか?
◆男が病院で目覚めると、記憶がない。2000年だと思ったら、2002年だと医者に言われる。が、検査の最中に突然2000年の世界にもどる。そして、その世界でさんざん翻弄されたのち、また2002年の世界に帰ってくる。映画は、この2つの世界をひんぱんに行ったり来たりし、次第に、この男にとってどちらがリアルな世界なのか、どちらが「現実」でどちらが「妄想」なのかわからなくなってくる。
◆何度も過去の同じ世界に戻り、それが自分には理不尽な世界なので、今度は、自分の過去を別の筋書きにしてやろうと決心して、主人公が過去を操作しようとするくだりがある。これは、『バック・トゥー・ザ・フューチャー』的なパターンだが、この映画は、ちょっとおもむきがちがう。それよりも、夢の自己解釈の試みようようなおもむき。
◆ドアーを開けると別の世界、別の時間に入り込むというのは、映画ではよく使われる技法。この映画でもこの手法が頻繁に使われる。が、その使い方は洗練されており、飽きさせない。
◆2年間の時間がどうして急に飛ぶのかはわからないが、その2年間に変わったことは見ていてわかる。凡庸なスタイルの映画なら、時系列で描くことを、2000年と2002年とのあいだを頻繁にスウィッチングすることによって観客の意識のなかで自然に構築されるようにしている。このやりかたはなかなか新鮮だ。
◆出演は、『ゴスフォード・パーク』でクールな青年を演じていたライアン・フィリップ、『死ぬまでにしたい10のこと』で印象的な演技をしたサラ・ポーリー、『コヨーテ・アグリー』で田舎からニューヨークに出て来る田舎娘を演じてブレイクしたバイパー・ペラーボなど。この作品では、ペラーボが一番サエた演技をしていたように思う。2000年のときは看護婦、2002年の時点では主人公サイモン(ライアン・フィリップ)の妻を演じ、それぞれ違った印象をあたえる。いきなり彼女がサイモンの頬にビンタを張るシーンにはハッとした。
◆2000年の世界には、サイモン、その兄(ロバート・ショーン・レナード)、そのフィアンセ、クレア、看護婦アンナ(バイパー・ペラーボ)がいる。2002年の世界では、病院に収容されているサイモンをアンナが妻として(そう医者から言われる)登場する。ここで、観客は、この2年間にアンナがある理由でサイモンの妻になったと考えてもよいし、両者が別々の世界であると考えることも出来る。2年間の「両端」だけを見せて、その間を観客に想像させる手法は実にユニークだ。
◆「現実」か「妄想」かは別にして、描かれる事実だけを列記してみると――サイモンと兄は父から譲り受けた豪邸に住んでいる/兄のフィアンセのクレアとサイモンとは不倫関係にある/兄とサイモンがもめ、兄を豪邸のエントランスに墜落させてしまう/兄を車に乗せて運ぶ/病院に運ぶ/断崖に運ぶ/交通事故/病院に運び込まれる/一度心臓が止まるが蘇生する。
◆いろいろ疑問が残る。なぜ、サイモンが蘇生したとき、皮膚も目もいままで眠っていた感じではなく、実にさっぱりした顔をしていたのか? 入院した病院は、なぜ「聖ユダヤ人(St. Jew)病院」なのか?
(ヘラルド試写室)
2004-03-11
●アタック・ナンバーハーフ2 全員集合 (Sa tree lex 2/Iron Ladies 2/2003/Youngyooth Thongkonthun)(ヨニュット・トンコートン)

◆ゲイのこともさることながら、タイのハッピーな生活文化のようなものがびんびん伝わってくる映画。ゲイ・カルチャーが抵抗なく受け入れられるという環境がタイにはあるらしいが、この映画は、先の『キャンプ』より、はるかに「キャンプ」的だ。いや、これこそ「キャンプ」映画だ。
◆エンディングで流れる「栄光も、一番になることよりも、毎日が楽しければいい。わたしという人間は世界でただ一人なんだから」といった意味の歌は、日常生活の肯定であると同時に、おおげさな言い方をすれば、「マルチチュード」のすすめである。パオロ・ヴィルノは、『マルチチュードの文法』(廣瀬純訳、月曜社)のなかで、「マルチチュードは複数の個体のネットワークに存するものであり、多数的なものとは複数の特異性のことなのです」と言っている。これまでの「公共性」や「普遍性」や「一般」や「普通」は、すべて、個々人を平均化してきた。だから、社会的に生きるには、タテマエとホンネが分裂する。しかし、マルチチュードという概念は、個が「特異」な個であるまま集団でもありえる新しい――国家や規範に支配されない――社会性を表現しようとしている。
◆わたしは、スポーツは大嫌いで、テレビで「松井」だ「新庄」だ「長島」(訂正→長「嶋」←早速まちがえた)だといった名が出ただけでチャンネルを切り替える。だから、スポーツがテーマの映画は警戒して見る。この映画は、前作の『アタック・ナンバーハーフ』(Sa tree lex/Iron Ladies/2000/Youngyooth Thongkonthun)で明らかなようにバレーの話でもある。バレーは、映画『キャンプ』の学芸会的「ミュージカル」のような役割を演じているにすぎない。だから、試合に勝つかどうかということは、あまり重要ではない。それよりも、ゲイとバイセクシャルとストレイトの「キャンプ」的「マルチチュード」が、ときおり反発を買いながらも、あるがままに肯定され、さらにその「マルチチュード」的「特異性」を加速させていく。
◆バレーボールチーム「サトリーレック」(これが原題)が、タイから列車で中国の雲南省に行くというのも、「脱属領的」行為だ。彼や彼女らが集まる居酒屋のカーニバル的というか、ミハイール・バフチン的な「ポリフォーニー」的な雰囲気が愉快。
◆両手を合わせるあいさつは、タイではあたりまえの「仏教徒」的身ぶりだが、ゲイ(マール・ゲイ)がやるととてもエロティックである。なぜだろう?
◆この映画に出てくる町や村の人々の雰囲気がゆったりしていていい。中国に入ると、道端でスイカを売っている老婆がいる。スイカは、おでんの具のように切って、長い串を差して売っているが、金を払わなくてもくれる雰囲気。
◆民主化デモに対して軍が発砲して多くの死者を出した1992年5月の「5月事件」のニュース映像がぱっと入るシーンがる。アン(ハタイラット・チャルーンチャイチャナ)は、最初ノンポリだったが、次第に政治に目覚め、このデモに参加したらしいことがちらっと描かれる。彼女はレズだったが、最後はアメリカに行き、男性と結婚する。ただし、これは、最後の方で、伝聞的に告げられるのであって、主要な話ではない。
◆ノンは、過去(フラッシュバックの仕方が定型的でなく、シュールである)には「ストレイト」を気取っていたが、実は隠れゲイで、彼の部屋の洋服タンスを開くと、ばーとマチョ的男性のアイドルポスターが貼ってあるのが見えてしまう。
◆チャイ(ジェッダーポーン・ポンディ)は、「サトリーレック」のなかでただ一人のストレートだが、妻とうまくいかず、心が揺れている。
(映画美学校第1試写室)
2004-03-10
●ミッシング (The Missing/2003/Ron Howard)(ロン・ハワード)

◆遅ればせながら『ビューティフル・マインド』以来作品を見ることができなかったロン・ハワードの新作を見た。試写は大分まえからやっていたが、機会を逸した。またケイト・ブランシェットが主役で、これまた顔に似合わず強いという設定の女を演じている。まあ、芯の強い役にうってつけの顔なのかもしれない。ケイト・ブランシェットに関してわたしが好きな部分はそういうところではない。
◆家庭を捨ててアパッチインディアンのところに行ってしまった父サミュエル(トミー・リー・ジョーンズ)が、妹リリー(エヴァン・レイチェル・ウッド)と娘ドット(ジェナ・ボイド)と暮らすマギー(ケイト・ブランシェット)のもとに帰って来るというところからはじまるので、また「父帰る」路線かと思ったら、かなりちがっていた。むろん、そうした流れも押さえている。が、それよりも監督ロン・ハワードの関心は、インディアンは(40~50年代とは)一転して「すべて善」とみなす傾向にさからい、インディアンにも「いいインディアン」と「悪いインディアン」とがいるということであったように見える。ここで登場する「悪党」としてのインディアンは、アパッチの呪術師(エリック・シュウェイグ)で、彼に率いられた白人混合の一団は、ニューメキシコの一帯を跋扈しながらインディアンから白人にいたる娘を誘拐して、メキシコの淫売宿に売りつけている。時代は、1885年だが、このアナロジーを「アラブ」に応用すると、けっこうヤバイ。
◆自分たちを捨てた父に対して冷たいマギー。ありがちなパーターで孫にあたるドットがやさしい。サミュエルと彼女とのあいだに交流が芽生える。行き先のない父を1晩だけ泊めた翌日、牧童で恋人のブレイク(アーロン・エッカート)とリリーが町に祭りの見物にとドット出かけるが、家の表手でリラックスしていたマギーは、ブレイクの馬が人を乗せずに帰って来るのを発見し、驚く。彼らが行った道へ急行すると、ブレイクは惨殺され、ドットはものかげにひそんで助かったが、リリーは行方がわからなくなっていた。
◆ここで、(タイミングよく)もどってきたサミュエルがマギーを助けるということになるわけだが、よくしたもので、犯人はインディアンであることがわかる。そうなれば、インディアンの戦術や性向を熟知しているサミュエルに出番である。以後、残忍でしたたかな呪術師とサミュエルとの闘いがはじまる。そこに、旧知のチリカファ・アパッチの親子がからんだりして、以後、活劇が展開される。呪術師の呪いが出てきたり、飽きさせない。ただし、闘いのなかでマギーのヒーラー(万能治療師)としての技能が活かされたり、すべてがストーリ作成上の予定調和になっているところが、月並み。
◆いったいなぜロン・ハワードはこのような映画を作ったのだろうか? マクロな見方をすると、この映画の核は、一旦は解体されたファミリーが、外敵(「テロリスト」のアナロジー)との闘いのなかでもう一度(つかのまではあれ)復活するということであり、ファミリーのために命をかける父親の自己犠牲の話である。
(UIP試写室)
2004-03-09
●永遠のモータウン (Standing in the Shadows of Motown/2002/Paul Justman)(ポール・ジャストマン)

◆いろいろなところで話題になった映画をようやく見れた。期待はまあ70%満たされた。何度か出て来るジョーン・オズボーンがなかなかいい感じなので、映画の帰り、タワーレコードに寄って彼女の最近のCD「How Seet it is」を買ってしまった。が、映画のなかの迫力あるオズボーンはこのCDのなかにはなく、がっかり。
◆冒頭、モノクロで一人の黒人の子供がさびれた風景の地面に弓のようなものをたてて、弦をはじいているシーンが映る。これは、長じて「ザ・ファンク・ブラザーズ」の中心となったベーシスト、ジェームズ・ジェマーソンの幼少時代を示唆しているようにも見える。この映画は、最初、モータウンつまり自動車(モーター)産業の町、デトロイトに田舎から出稼ぎにやってきた面々が、やがて1959年に実業家のベリー・ゴーディが設立した「モータウン・レコード」のもとで、「ザ・ファンク・ブラザーズ」として、次々にヒット作とスターを生み出していった歴史をたどる。
◆作り方としては、生き残りの元メンバー(リチャード・"ピストル"・アレン/ドラム、ジョニー・グリフィス/ピアノ、ジョー・ハンター/キーボード、エディ・ウィリス/ギター、ジョー・メッシーナ/ギター、ロバート・ホワイト/ギター、ユリエル・ジョーンズ/ドラム、ボブ・バビット/ベース、エディ・"ボンゴ"・ブラウン/パーカッションなど)の証言、過去の映像、「ザ・ファンク・ブラザーズ」と共演したことのあるミュージッシャンの映像、「モータウン」サウンドのシンパ的ないしはファン的アーチスト(トム・スコット、ジョーン・オズボーン、ミシェル・ンデゲオチェロ、チャカ・カーンなどなど)との「共演」と対話、そして、何度か挿入される「再現映像」等によって構成されている。
◆映画のもとになったアラン・スラッキー『伝説のモータウン・ベース ジェームズ・ジェマーソン』(リットーミュージック)も刊行されていることだし、「モータウン」の専門家、マニアが無数にいるはずだから、ここでわたしが言うべきことはあまりない。たぶん、モータウンに入れ込んでいる者からすると、かなりものたりない部分もあるだろう。「再現映像」の部分はなかったほうがよかった。しかし、わたしが一番惹かれたのは、モータウンのサウンドが生み出されたスタジオ「ヒッツヴィルUSA」という稀有なる場でメンバーたちがすごした時間の流れを想像できたことであった。決して豪華とはいえないスタジオで(レーベルに名前は出なくても)みな癖の強いやつらが、「職人」的な踏ん切りとノリで「一発決める」――その感じが伝わってきたことだった。
◆ジャズから来たジョー・メッシーナは、「30年近くギターを弾いていない」とのことだが、しゃべりも久しぶりに弾いたというギターも、いい感じだった。ジャズに入れ込んでいたわたしからすると、「モータウン」というのは、ブルース的な側面もジャズ的な側面も「口味がよすぎる」感じがするが、それを言ったら、身も蓋もあるまい。
(シネカノン試写室)
2004-03-08
●恋愛適齢期 (Something Gotta Give/Nancy Meyers)(ナンシー・メイヤーズ)

◆老年の恋とはいかなるものかをねちっこいジャック・ニコルソンとどこかに不安を隠した演技のうまいダイアン・キートンが渡り合う半分コメディ半分本気のドラマ。ワーナーの試写室の入口にはいつも警官のような制服のガードマンが立って目を光らせている。受付に行くには何かを提示しなければならない。ニューヨークのギャラリーなどには、相手の顔を見ていちいち電気錠を開くところがまえからあったが、それでも9・11が起こった。日本も、段々監視社会化がエスカレートする。
◆監督・脚本・制作のナンシー・メイヤーは、脚本が出来上がるまえからダイアン・キートンとジャック・ニコルソンを想定していたという。それだけに、2人の個性が、登場人物(キャラクター)をこえてにじみ出てくるようなところがあり、それがいい人といやな人とに分かれるだろう。ちなみに、わたしはうんざりだったが、キアヌ・リーブスが、「職業的」な演技を通して「ガス」を抜いてくれたので、最後まで見ることができた。
◆「ロマンティック・コメディ」と見なされているようだが、「コメディ」にしては笑えない。笑わせようとしているセリフはたくさんあるが、けっこう毒が強い。キートンの妹役のアマンダ・ピート(【追記/2004-04-10】これは、フランシス・マクドーマンドのまちがい。アマンダは、キートンの娘役。柏木明生さん、ご指摘ありがと!)がちょっと出てきて、フェミニスト風のキツイ批判をニコルソンに加えるが、彼女のタッチがこの映画の基底にある。おそらくアマンダ(→フランシス)が監督の分身役なのだろう。
◆何でも言葉で確認するといのがアメリカ流だということをこの映画はよくみせてくれる。キートンに気のあるリーブスが、彼女を食事に誘う。その席で、彼女が言う――「わたしとどうなりたいの? ただの友達、それとも恋人?」別に彼女は喧嘩ごしで言っているわけではない。商売の取り引きをしているわけでもない。だから、リーブスは、「ノー、友達じゃない」と言い、一歩近づく。日本語でこういうやり方をしたら、一歩後退するのではないかな? ニコルソンとのあいだが熟して、ベッド・インしたとき、上のなった彼が、キートンに、憮然とした態度で「バースコントロールは?」と言う。すると、彼女は、「もういらないわ」と言い、ニコルソンが、「ぼくはラッキー・ボーイだ」と笑顔になる。日本では、恋人同士が、「今日イタリアン食べない?」と言うのと同じ語調と語感で「今日セックスしない?」とは言わないと思う。むろん言う人もいるが、「エッチしない?」などと、どこかで婉曲表現を使う。これでも、30年もまえにくらべたらどぎつくなっている。しかし、アメリカはそうではない。思っていることを明確に言うことが基本なのだ。これは、わかりやすくていいところもあるが、単純だなぁと思うことが最近は多い。
◆ここまで書いてきて、この映画についてちょっと別の印象がうかんだ。アメリカが嫌いになっているので、ついつい「アメリカ」の名のもとに悪口を言ってしまうが、ナンシー・メイヤーは、キートンとニコルソンを選ぶに際して、こういう「アメリカ」的個性が平均より強い設定にしたかったのではないか? 設定からすると、ダイアン・キートンは、「リリアン・ヘルマン以来の大女流作家」と評する人もいる人物であり、また、ジャック・ニコルソンは、「ヒップホップのレコード会社として政界第2位」という会社の社長という設定だ。まさに「アメリカ」を代表する男女なのだから、「アメリカ」的デイスクールがむんむんするのは当然だろう。
◆並の階級には属さない人間を描くのは、「ロマンティック」の条件だが、この映画は、そういう設定でありながら、彼らが特権的な階級に属しているという感じがしない。たしかに、ニコルソンがキートンを追ってパリに行ったりする。彼女は、毎年パリの高級ホテルに泊まり、高級レストランで誕生日を祝う。これは、特権階級のやることだろう。しかし、それが、映画で描かれるとそう思えない。これは、わたしがそう思うだけか? それとも、ニコルソンとキートンのドン臭い演技のためか?
◆ニコルソンもキートンも、役柄としてセレブリティで、それぞれに自尊心が強いから、他人にあまり関心を持たない。娘が連れて来て初めて会ったときも、キートンは、ニコルソンが何者か知らなかったし、知りたいとも思わなかった。が、それが変わって来て、互いに相手のことを知ろうとしたときに使うのがインターネットの検索サイトである。これは、いまでは一つの習慣になっているとも言える。実際、最近は、ちょっと何かをしただけでもネットのどこかに載ってしまう。ましてウェブページを立ち上げていれば、ばっちりである。
◆この映画で一番面白かったのは、個物へのこだわりだった。食べるシーンでどんな料理が供されているかをちらりとであるが、ちゃんと見せる(ということは、数秒様のショットで出ている料理も手を抜いていないということ)とか、部屋の調度品や道具などへのこだわりである。キートンの家にニコルソンが居候しているとき、気まずい雰囲気が流れたあと、執筆中の彼女のノートパソコン(マッキントッシュ)にいきなりメールが入る。別の部屋のベットの上でニコルソンがノートパソコン(こちらはVAIO――使い分けているところがニクい)を開いている。やがて2人のあいだにチャットのようなメールのやりとりがはじまる。どちらのパソコンにもLANケーブルはつながっていなかったから、おそらく2人は無線LAN/ブルトゥース機能でメールのやりとりをしたのだろう。「じゃあ、5分後にキッチンで」。映画のドラマのなかでパソコンやケータイは重要な小道具だが、この例は成功している。
(ワーナー試写室)
2004-03-04_2
●キャンプ (Camp/2003/Todd Graff)(トッド・グラフ)

◆どちらかというと「通」好みの作品。ある種の「隠し玉」が次々に出て来る楽しみがある。「普通」の感じで登場して、猛烈芸達者なやつがあちこちにいるのもその一つ。学芸会風にではあるが、昔ブロードウェイで見たヒット・ミュージカルのシーンがいくつも演じられ、なつかしかった。会場には女性の姿が多く、あちこちからポップコーンとバターのにおいがする。
◆このタイトルを見て、日本では「野営」や「サマー・キャンプ」という意味の「キャンプ」を思い浮かべる人が多いかもしれないが、英語的文脈では、同時に「キャンプ趣味」という意味での「キャンプ」が浮かぶのではないだろうか? この語は、しばしば「同性愛的」という意味でも使われたし、もっと発展的にいまの「クール」(cool)のように、カッコイイとかイケテルとか言った意味でも使われた。『アメリカ俗語辞典』(研究社)によると、「20世紀初頭から〈見せつけるような、はでな、大げさな、気取った、ホモらしい〉という意味であったが、近年になって〈鼻についたり、これ見よがしであるためにかえっていきでしゃれて見える〉という逆説的な意味に変わった」とある。
◆わたし自身がこの映画のタイトルを見て、まず思い浮かべたのは、こうした意味と、スーザン・ソンタグ (Susan Sontag )が1964年に『パーティザン・レヴュー』(Partisan Review)に書いた「《キャンプ》についてのノート」のことだった。アンディ・ウォーホルは、1965年に、明らかにソンタグを意識しながら、『Camp』というタイトルの映画を作っている。怪マルチアーティストのジャック・スミスがめちゃめちゃやっていたりして、面白いし、いまでは「ファクトリー」時代の貴重なドキュメントである。トッド・グラフは、当然、ソンタグやウォーホルを意識していないはずはない。
◆形式的には、この映画は、一方で学校が休みのあいだに開かれる特別合宿教育という意味での「キャンプ」(レジデント・キャンプ)をおさえながら、同時に、「変な」連中、感覚的にトンでる男女が集まる場所(ウォーホルの「ファクトリー」もそういう場所の一つだった)、スーザン・ソンタグが考察したような「趣向」の生まれるプロセスを描いている。後者のほうの意識がどの程度のものであったのかは、若干、疑問に思える部分もないわけではないが、そういうふうに見たほうが面白いと思う。以下で、冒頭にソンタグの「《キャンプ》についてのノート」(高橋康也他訳『反解釈』所収)からの引用を挙げ、そのあとで映画についてノートしてみる。
◆「キャンプとは、誇張されたもの、《外れた》もの、ありのままでないものを好むこと」――これに関しては、この映画の登場人物はすべて「普通」ではない。その誰としてスポーツに興味がないのがそのことをあらわしている。一番「まとも」に見えるヴラッド(ダニエル・リタール)も、数字を思い浮かべ、それを端から足して行かないと気がすまないという強迫神経症に悩んでいることがわかる。
◆「同性愛者はキャンプの最前衛を、そして最もはっきりした受容者をなしている」――ゲイで、高校の「プロム」(卒業パーティ)に女装をして行き、受付でなぐられ、追い返されるマイケル(ロビン・デ・ジーザス)は、この映画の重要な登場人物である。
◆「両性具有者というのは、キャンプ的感覚にとって重要なイメージの一つである」――ただし、マイケルは、気が変わって黒人の女性ディー(サシャ・アレン)と寝る。ヴラッドは、あるとき、マイケルに性愛を感じる。
◆「キャンプするというのは誘惑の一つの方法である」――誘惑しあうことがこのドラマの主要なプロットであることは明らかだ。
◆「キャンプとは、300万枚の羽根でできたドレスを着て歩きまわっている女である」――このタイプを一番代表しているのは、「大女優」気取りのジル(アラナ・アレン)だろう。よくしたもので、この子に、まるで付き人かメイドのようにつき従う子がででくる。フリッツィ(アナ・ケンドリック)だ。彼女は、ジルの下着まで洗い、かえってジルに気持ち悪がられる。
◆「キャンプとは、真面目に提示されはするが、〈ひどすぎる〉ために、完全には受け取れない芸術のことである」――マジに受け取れば、この映画は、アーチストになりたいと思っているが、並の学校では「微妙」すぎてイジメの対象になりかねない子供たちが、1夏の「キャンプ」で、特訓を受けて(ただし、彼や彼女らがどういう訓練を受けたのかは描かれない)自分の才能を発見して行く話にすぎないが、彼や彼女らの芸それ自体は、「学芸会」で子供が頑張ったというような意味では「感動」的なシーンもあるが、とても「完全には受け取れない」。が、しかし、全体としては、そういう切り捨てを越えている面白さがある。
◆「キャンプ趣味は、よいか悪いかを軸とした通常の審美的判断に背を向ける」。キャンプとは、「〈失敗した真面目さ〉の感覚であり、経験を演劇化する感覚である」――これは、この映画のことを言っているようではないか。
◆いや、ここまで書いて来て、こういう対照は、トッド・グラフとこの映画を買いかぶりすぎるのではないかという気がしてきた。とはいえ、わたしが70年代のニューヨークで見たスタンダードなミュージカルや芝居のシーンを少年少女たちが猛烈へたくそに、そしてときにはハッとするような新鮮さで演じているのを見て、こんな書き方になった。
(ヴァージンシネマズ六本木ヒルズNo.1スクリーン)
2004-03-04_1
●ヴェロニカ・ゲリン )Veronica Guerin/2003/Joel Schumacher)(ジョエル・シュマッカー)

◆アイルランドのダブリンで麻薬の密売の黒幕摘発に体をはった女性ジャーナリストの「実話」。リンとした感じが合うヴェロニカ・ゲリンがいい。雨がそぼ降るなか、かなりの盛況。補助椅子も出た。全身赤ずくめの「赤ちゃん」も来ている。あちこちにご常連の顔。
◆映画としての見ごたえかあると思う。しかし、「Based on the real story」と表示されている映画を見ていつも思う「それがどうした?」という感じはどこかに残る。それは、おそらく、映画に「社会告発」の含みを持たせるところから来るのではないか? この人は、こんなに闘った、彼女の相手はこんなに悪かった・・・。むろん、事実にもとづいたドラマや記録は、「ああ、こういうことがあったのか」とか「こういう人物がいたのか」という感慨を残し、そこから各自が何かを始めるきっかけをあたえる可能性はある。
◆圧力や恐怖に屈しないヴェロニカをケイト・ブランシェットが演じることによって、半分ウソっぽくなったとはいえるが、同時に闘うことやがんばることが何かの義務感からというよりも、ヴェロニカの本性から自然にわき出てきた感じが出て、好感を感じた。これは、ブランシェットの「人徳」かもしれない。『シャーロット・グレイ』に通じる演技。
◆「実話」であるという点でひっかかるのは、おそらく、ここで描かれるヴェロニカの闘いの具体的な振幅が弱く、その描かれ方が一直線で、観客にはそれを受け入れるしかなく、観客がそれぞれに彼女の闘い方を応用できないという点にある。黒幕のジョン・ギリガン(ジェラルド・マクソーレイ)もその妻(マリア・マックダーモットロウ)も、根っから「悪」であり、ヴェロニカの夫(グレアム・ターレイ)はいつも献身的で控え目であり、息子(サイモン・オドリスコール)は「愛らし」く、ヴェロニカの母(ブレンダ・フリッカー)は「やさしい」「いいひと」だ。悪人や悪事というものは、悪い奴がいて悪いことをやるというインプット/アウトプットの関係ではなく、相当量の偶然や無意識の部分が含まれた結果である。悪いことをする奴がからならずしも「悪人」の顔をしているとはかぎらないのはそのためだ。しかし、この映画では、「典型」が描かれ、麻薬取り引きの社会的政治的背景や経済に関するディテールが弱い。
◆ディテールといえば、この映画では、最初からケータイが重要な小道具として活躍する。しかし、わたしの記憶では、1996年(彼女が殺された年)以前はロンドンでもまだそれほどケータイは普及してはいなかった。ダブリンがロンドンより普及していたということはないだろう。まして彼女が映画のなかで見せるようなサイズのケータイをどこでも使えるという環境はなかった。「実話にもとづいている」のなら、こういうディテールもしっかり描かないとダメだ。
◆登場人物のなかでは、ギリガンとつるみながらヴェロニカに情報を流すヤクザのジョン・トレイナー(シアラン・ハインズ)が、一番屈折していて「現実」にやや接近している。
◆映画の最後に実のヴェロニカの顔写真が出る。それは、ケイト・ブランシェットよりももっと「したたか」な感じだった。修羅場をくぐってきた、言うなれば、「人を殺せる」目をしている。映画での彼女とジョン・トレイナーとの関係は、ジョンが一方的に彼女に惚れているだけのような描き方だったが、実顔からは、目的のためには、汚れ役を演じるのも辞さないという気迫としたたかさが感じられる。
(ブエナビスタ試写室)
2004-03-03
●キッチン・ストーリー (Salmer fra kjokkenet/Kitchen Stories/2003/Bent Hamer) (ベント・ハーメル)

◆タイトルからはわかりにくいが、最初敵対心と不信感をいだいていた者同士がうちとけあって行く「ほのぼの」ストーリ。ファニーな味がいい。開場前、狭い試写室内に「クロちゃん」の大声が部屋中にひびくので、待っているあいだ本を読んでいても落ち着かない。が、やがてお客がどんどん入って来て、あちこちで声がするようになったので、相乗効果で誰が何をしゃべっているのかがわからなくなり、落ち着いた。最後は、通路に座布団が敷かれるほどの盛況。
◆最初、1940年代のノルウェーでは、スウェーデンの「家庭研究所」による「立ち入り調査」があり、各家庭の台所で主婦が人間工学的にどういう動き方をするかを調べたということが、記録フィルムで紹介される。そして、今度は、独身の男性についても同じ調査をしようということになり、その調査員が派遣されるというところから、「本編」が始まる。キャンピングハウスのような小型のトレーラーをひっぱった車が列をなし、ノルウェー国境を越える。そして、一人暮らしをする老人イザック(ヨアキム・カルメイイヤー)の家を調査員のフォルケ(トーマス・ノールストローム)が訪れる。どういう契約があったのかわからないが、その日から、フォルケは、イザックの家の台所に「見張り台」のようなものを設置し、イザックの行動を監視しはじめる。
◆プレスには、こういうことが実際に行われたかのような記述があるが、見ていてすぐわかるように、この映画はそういう「事実」を再現しているわけではない。そもそも、1944年のフィルムを上映するシーンで、映写機を操作している老人が、映写をもたもたしているのをとがめられると、「スウェーデン製はすぐ壊れる」とつぶやき、スウェーデンへ批判を暗示する。この映画は、そのカフカ的な嘲笑とユーモアの雰囲気からすぐわかるように、1950年代のノルウェー/スウェーデン関係、組織による個人の権威主義的な管理をコミカルに描いているのであり、そういう権威主義のあいだから漏れ出てしまう人間の本音のようなものが見る者を感動させる。
◆今日の管理は多元的でしたたかだが、たとえば監視カメラのように、依然として「上から覗く」というのは監視と管理の原型である。先日、小倉利丸氏から氏が編纂した『路上に自由を 監視カメラ徹底批判』(インパクト出版会)を贈られた。この本は、監視カメラの増殖の猛烈な現実を教えてくれる。しかし、ここには、そうした現実への抵抗の方法についてはあまり記されてはいなかった。おそらく、『キッチン・ストーリー』の面白さは、監視のすごさを強調するよりも、それへの抵抗のおかしさとしたたかさを見せてくれるところだろう。監視は、今後もますます進み、その技術も高度化する。その実態と動向を小倉氏のように警鐘を鳴らしつづけることが重要であることは言うまでもないが、もっと重要なのは、そうした管理への抵抗の歴史を具体的に知ることであり、それを実践することだろう。
◆イザックの抵抗は、まず、正規の台所で食事の支度をしないということから始まった。監視する方は、それならば、彼がこっそり調理をしている屋根裏の寝室を監視すればいいはずだが、硬直した管理体制とその番人(フォルケ)は、そういう融通がきかない。というよりも、融通をきかせれば反則になってしまうのが権威主義的な管理体制なのである。そのことを知っているイザックは、フォルケをじらす。階上からうまそうな匂いがただよってくるし、目の前には温かい飲み物もあるが、フォルケは、トレーラーのなかでゆで卵とパンの冷たい弁当を食べ、あとはチョコレートをやけ食いするしかない。(注文したおいたソーセージなどの小包がとどき、それを無茶食いして吐いてしまうシーンもある)。
◆しかし、人間が行う管理には、どこかに必ずエアポケットがある。毎日顔を合わしているうちに、フォルケとイザックとのあいだに交流が出来てゆく。発端は、パイプタバコが切れたイザックに自分の(スウェーデンの)タバコを投げてやったことだった。魚心に水心。今度はイザックがフォルケにコーヒーをするめる。フォルケは、被観察者と話をしてはいけないのだが、そういう決まりもだんだんはずれて行く。
◆後半は、2人の会話とつきあいのなかで2人の生い立ちや相互にかかえている問題があらわになってくる。イザックは、その名からも想像できるようにユダヤ系である。彼の馬は病気にかかっている。彼も、医者から精密検査をすすめられている。フォルケは、恋人も妻もいない。
◆面白いシーンがあった。イザックは、口を空けて水道管を握るとラジオが聞こえるという。歯に銅を詰めてから、口が受信機になったというわけだ。実際に口を空けるとフォルケの耳にも音楽が聞こえる。これは、シュールな話のようにみえるが、ありえることだ。送信所のアンテナが近くでは特にこういうことは起こりえる。
◆監視カメラとロボティクスとの融合である今後の監視システムは、前述のような「エアポケット」を見出しにくい。フィジカルな意味での人間が極限まで隠されてしまうからだ。しかし、イザックが、「電話代が高いから」と言って、ダイヤルを回してベルを鳴らして切るという方法で友人との連絡をとりあっているシーンに示されるように、「人間性」をどんなに排除したオートマティックなシステムでも、逆手に取れる側面があり、テクノロジーが高度化すれば、その側面はそれだけ増えるのだと思う。たとえば、監視の強化に対しては、《露出》の戦略で! (「デジタル・ヌーディズム」参照)。
◆最後にある事件が起き、フォルケは決心をする。彼は、官僚的な会社をやめ、ノルウェー人になる。別にこの映画は、スウェーデンがダメだとは言っていない。そういう時代もあったということは示唆するが、それよりも、この映画の魅力は、管理的なものには抵抗し、個々のコミュニケーション、個々の「特異的」な関係に執着がなければ、生きている実感は持てないのだということを実感させるところだろう。
(映画美学校第2試写室)
2004-03-02
●ゴッド・ディーバ (Immortel (ad vitam)/2004/Enki Bilal)(エンキ・ビラル)

◆コミックとCGと生撮りを合成した独特のエンキ・ビラル映像。面白い。このヘラルドの試写室は、映写環境としてはベスト3に入る。しかし、会場に入ったら、冷たい風が舞っており、底冷えしそう。お客の数も少ない。2年ほどまえこの試写室に毎週のように来たことがあったが、近年はここでの試写が少ない。映画の世界は水もの。しかし、とにかく、この作品はおすすめ。
◆エジプト神話風の「神」が登場したり、『ブレードランナー』風の都市が出てきたり、話のスケールは大きいのだが、ちょっと個人映画のような、というか、手作りのCGのような感じがある。そう、少し『ムーラン・ルージュ』に似た感じと言えないこともない。アニメの登場人物のようにデフォルメされたキャラクターも、フィギャー人形的。この作品では「手作り」的なところがかえっていいのだが、同じフランスのCG映画でも、『ケイナ』は、チープな感じになっていて、かわいそうだった。フランスでは3月24日公開予定ということなので、この時期に日本語字幕付きで見れるのはうれしい。
◆『ブレードランナー』から『未来世紀ブラジル』をへて『マイノリティ・リポート』にいたるまで、映画で描かれる「未来」に明るいものは少ない。実際、遅くともレーガン政権が誕生した1980年代初頭以来、そして最終的には9・11に続くブッシュ政権のなりふりを見ても、人間は決して歴史から学ばないものだということ、歴史的時間の算術級数的進展は「文明」の後退であるらしいことが明らかになったのでから、ハッピーな未来など描こうにも描けないかもしれない。時代を2095年のニューヨークに設定したこの映画の「未来」も明るくはない。
◆わたしが住んでいた1970年代のニューヨークは、文化と社会の軸が「多元主義」(pluralism)から「多文化主義」(multi-culturism)にシフトした時期で、ある種アナーキーで多様な要素が容認された。レーガン政権の登場は、そうした状況への反撃だったが、以後、それは反撃・反動を通り越し、その反動のまま先へ進んでいる。この映画の世界でも、「神々」、エイリアン(異星人)、有機的・無機的なさまざまなアンドロイド/ミュータント/ロボット、そして人間等々、「多様」な「生き物」が存在する。しかし、そうした異なる存在者が異質なものとしてそれぞれにありのまま存在することへの恐怖と抑止は、いま以上に強くなり、大胆で強引な管理が遂行されている。刑を受けると、冷凍冬眠させられて、空中に浮く刑務所に収容される。逮捕されたときにはめられるのも、「手錠」ではなくてヘッドマイクのような「口錠」である。
◆2095年のニューヨークで、それぞれの存在者が、それぞれに悩みを持っている。古代エジプトの壁画にその姿が見える、頭が鷹で体が人間の神「ホルス」(トーマス・M・ポラード)は、反逆罪で永遠の眠りの刑を宣告されている。エイリアンのジル(リンダ・アルディ)は、地球のマンハッタンにいることの意味を見出せない。彼女が師のようにあおぐエイリアン・ジョン(フレデリック・ピエロ)には、地球にいられる時間は残りすくない。この都市を支配している企業・ユージニックス社の陰謀を告発して空中刑務所のコンテナーに冷凍冬眠させられていた「英雄」ニコポル(トーマス・クレッチマン)は、コンテナーの落下事故で脱出のチャンスをつかむが、毎日逃げ回らなければならない。ユージニックス社の社長の息子にして市上院議員のカイル(ジョー・シェリダン)にしたところで、東洋系の顔をした女性コンサルタントのリリー・ヤン(コリーヌ・ジャベール)にふりまわさてている。
◆2095年の人類は、神々から見放された存在なのだろう。神々は他者たる人間もエイリアンも助けない。が、神々のなかにそうした神々の冷酷さに反抗し、人間を救おうとする神がいる。ホルスは7日間の猶予を受けて、マンハッタンに姿をあらわす。マンハッタンの空中に浮くピラミッドは、古代、未来、異星とをリンクする超時空スペース。彼がやったことは、一人のエイリアンの女性ジルを見つけ、彼女に人間の子供を生ませること。が、神は、人間ではないから、受精させるために人間の男を必要とする。偶然か、あるいは、ホルスの操作か、空中に浮かぶ刑務所でを受けていたのコンテナーが地上に落ち、ニコポルが転げ出る。ホルストは、意識を取り戻した彼の体に一体化するのだが、ニコポルの側からすれば、自分が愛していもしない女性を「犯す」ことになる。このあたりの屈折が面白い。
◆マンハッタンは、「レベル1」から「レベル3」までの3つの区域にわかれ、それぞれに、「エリート」、「適応者」、「不合格者」が住んでいる。管理と支配(刑務所も)は、すべてユージニックス社が行う。経済もこの企業の独占状態なのだろう。80年代にはじまった「管理化」はさらにさらに強化されているが、「反体制」的な活動も依然続いている。ユージニックス社の技術で肉体を改造された者のセラピーを担当する医師エルマ(シャーロット・ランプリング)は、洗脳としてのセrピーではなく、解放としてのセラピーを密かに行っている。不法な「レベル」に入り込んで「保護」されたジルを、同じ会社の研究室で働く夫の便宜で自分の方にまわしてもらい、彼女の「自己発見」の手助けをする。
◆今後、弾圧/反抗という図式が成り立つ状況が続くのか、それとも、誰が支配しているのかわからない「多形的」な管理と支配がもっと浸透するのかは、わからない。この映画の「2095年」は、むしろいまの時代の継続と昂進を示唆している。だから、最後のシーンで、ジルが赤ん坊を連れてパリにいるのは、なかなか意味深長だった。もうニューヨークはダメだからだ。彼女は、シャルル・ボードレールの詩集『FLEURS DU MAL』(悪の華)のページを開いている。
◆原題は、「不滅」に括弧が付され、(ad vitam)とあるが、これは、「上位の者から授けられた生涯」のこと。
(ヘラルド試写室)