2018年アカデミー賞雑感
(「雑日記」より転載)

しばらく書かなかったので、書きたいことがたまった。新たな流行の兆しを見せるヴィーガニズムのこと、中途半端な書き方をしたロボットアームの実験のこと、最近入れ込んでいる井原西鶴のこと、それからオスカー/アカデミーのことなどである。
それらは、わたしのなかではみんなつながりがあるので、ひと続きに書きたいところだが、今日は、あと何日かで受賞が決まるアカデミー賞についてまず書こうと思う。
この1年半ほど「トランプ劇場」に日参していたために、リアリティ感覚が変わってしまった。それは、文字通り「リアリティTV」そのもので、そんじょそこらのハリウッド映画を見てもリアリティを感じないほど下品で鈍感になってしまった。
おかげで、この間にノミネートされた作品を見たり、見直したりしても、非常にかぎられたものしかピンと来ないのは、困ったものである。少なくとも、トランプ・リアリティTVには登場しないタイプのものでないと興味をそそられないのである。
おそらく、この賞の審査員たちも、評価の基準に大なり小なりそんな係数がかかった状態で作品や俳優を評価するということになるだろう。
そこで、ここでは、もし、いまのアメリカの「空気」のなかで、ハリウッドの業界経済とは無縁に賞を選ぶとすれば、どうなるかといった観点から、いくつかの作品をコメントしてみようと思う。
まず、あたかもアメリカの社会・歴史的な「実相」を映そうとしているかのような作品はオミットしたい。「現実」が映画にかぎりなく近づく時代には、映画らしい映画、つまり映画というメディアを意識し、映画でなければやれないことを試みる作品こそが評価されると思うからである。
そうすると、【作品賞】のなかでは、『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』は真っ先にはずしたい。『ダンケルク』と『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』も、もういいだろう。
『スリー・ビルボード』は、トランプを倒すには、『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』みたいな「理性的」なやり方ではなく、「次は火だ」式にいっちゃえというような挑発があって楽しいが、これも、社会的なメッセージ性が感じられるかぎりにおいて、【作品賞】からは、はずす。最有力候補だそうだが。
『ゲット・アウト』は、最初、なんだまた人種差別反対の映画かと思って見ていたら、ホラー/サスペンスと「持つべきものは友人だ」という話であることがわかり、かえって感心した。最初、なんの変哲もないリベラルな意識の女の子にを演じていたアリソン・ウィリアムズの変貌ぶりが見事。しかし、【作品賞】としては弱い。
『レディー・バード』は、シアーシャ・ローナンの(ひと昔まえの)広末涼子的な演技が鼻について、見通せなかった。『ハンナ』のローナンには瞠目し、『つぐない』もよかったが、『グランド・ブダペスト・ホテル』あたりから演技が安くなった。
『君の名前で僕を呼んで』は、あちこちで非常に高い評価を受けており、実際に、主演のティモシー・シャラメはすばらしいのだが、これも、屈折した意味で「社会派」なので、除外する。ドラマに同化した批判で不公平かもしれないが、わたしは、彼が演じるエリオが、なんでまたオリヴァー(アーミー・ハマー)みたいなツマラナイ奴を好きになったのかと終始イラついた。
ただし、この映画は、実はそこが狙いなのかもしれない。一見、田舎の「純真」な少年と都会男とのひと夏の切ない同性愛の物語のような成り行きは見せかけか? エリオの父親のパールマン教授から招かれて夏の休暇をすごしにイタリアに来るアメリカ人の大学院生オリバーが、イタリア人の目で、しかもユダヤ人同士の目で批判されているのかもしれない。
このオリバーという男は、最初から嫌な奴として描かれている。まず、朝食のゆで卵の食い方がなってない。アプリコット・ジュースを出されて、その飲み方も下品だが、おまけに、"apricot" という言葉についてエリオの父親がヨーロッパのインテリ特有の雑談的ユーモアのつもりで口にしたその語源を、ひとまず聞き流したうえで、そんなことはあなたより知っているよと言わんばかりに滔々と語源的蘊蓄を聞かせる。何というユーモアのなさだろう。そのときの父親の若干の当惑と困惑の混じった笑いは、演じるマイケル・スタールバーグの妙技だが、同時に、ヨーロッパ人が困った「野蛮人」に見せる典型的な表情でもある。
それから、庭の古い小プールのところでオリバーに、ハイデッガーの言葉を引用した自分のメモを読んで聞かせるくだりにもオリバーの俗物インテリ根性が露出していて胸糞が悪い。ここでオリバーが読む駄文は、ハイデッガーがヘラクレイトスのアーレテイヤ等について言っている「非隠蔽性/隠れなさ」に関する文章を参照していると思えるが、そんなものをなんでいきなり読むんだよ、という感じ。
ある意味で、アーミー・ハマーの演技は、ドライで身勝手なアメリカ人をよく出しているとも言える。そういえば、彼は、『コードネーム U.N.C.L.E.』 (2015) のイリヤ・クリヤキンを演じていた。もとのテレビシリーズでデイヴィッド・マカルムた演じたクリヤキンは違うが、ハマーが再演したクリヤキンは、白人至上主義を隠し持つ「アメリカ人」に見えてしかたがなかった。
それに、この『君の名前で僕を呼んで』は、一見同性愛を支持しているように見えながら、ユダヤ系のファミリーではあたかも同性愛に対して(まあ時代設定はあるとしても)強い偏見があるかのような設定になっている。結局、エリオは同性愛に生きて、傷つくのだ。どうして、どんどんブッ飛んでしまう描き方ができないのか? これは、トランプのアメリカで目下増殖しつつあるネオピューリタニズムの差別意識を暗黙に肯定するものだ。いずれにせよ、『君の名前で僕を呼んで』に【作品賞】はやりたくない。
とすると、残るは、『シェイプ・オブ・ウォーター』と『ファントム・スレッド』のどちらかということになる。わたしは、『シェイプ・オブ・ウォーター』のなさそうでありそうな話、シュールな飛躍、「怪物」を見せてしまっても違和感がない作り(メイクがうまいということではない)、サリー・ホーキンスが演じるイライザの切なさ、最後の熱い高揚に感動した。
しかし、この作品は、アカデミー賞の選考委員の平均値には「高級」すぎるかもしれない。彼や彼女らは、もうちょっと「普通」の「完成度」のようなものを評価し、『ファントム・スレッド』を取るのではないか?
主演のダニエル・デイ=ルイスは、本作をもって俳優をやめるというし、相手役のビッキー・クリープスは、さすがポール・トーマス・アンダーソンの演技指導のかいあってちょっと現実離れした、ある種「宇宙人」的な(つまり『レディー・バード』のシアーシャ・ローナンみたいなカマトトにならない)演技を見せる。
この映画は、ある意味でレイノルズ・ウッドコックというロンドンの由緒あるドレスメーカーと若いウエイトレスとの〝変態愛〟の話である。それが通常の意味の「変態」とは見えないように描かれているところがアンダーソンの上手いところ。
 エレクロトニカの鋭角的な音で始まるこの映画で音楽と音の力は大きい。音楽がエモーショナル・ナレーターを演じているとも言える。好き嫌いはあるだろうが、ジョニー・グリーンウッドはいい仕事をした。【作曲賞】の候補になっているが、その資格は十分だ。
エレクロトニカの鋭角的な音で始まるこの映画で音楽と音の力は大きい。音楽がエモーショナル・ナレーターを演じているとも言える。好き嫌いはあるだろうが、ジョニー・グリーンウッドはいい仕事をした。【作曲賞】の候補になっているが、その資格は十分だ。
 ここでテーマ音楽を含めてピアノを弾いているカスリーン・ティンカー(Katherine Tinker) は、ロンドンの若いアーティストで、これがフィーチャー映画では初仕事のようだが、これからどんどん出てくるひとに思える。グリーンウッドの引きで参加したらしい。
ここでテーマ音楽を含めてピアノを弾いているカスリーン・ティンカー(Katherine Tinker) は、ロンドンの若いアーティストで、これがフィーチャー映画では初仕事のようだが、これからどんどん出てくるひとに思える。グリーンウッドの引きで参加したらしい。
ここまで一気に書いて来て、ふと、『シェイプ・オブ・ウォーター』の方が『ファントム・スレッド』よりも、アカデミー賞の選考委員の平均値には「高級」すぎるかもしれないと書いたが、それは逆で、彼や彼女らには、『ファントム・スレッド』の奥深さは決してわからないのではないかという思いが強まった。
だから、【作品賞】がもし『シェイプ・オブ・ウォーター』か『ファントム・スレッド』かということになれば、『シェイプ・オブ・ウォーター』となるだろうが、わたしの希望はあくまでも『ファントム・スレッド』だということである。まわりくどくて失礼。
(2018/02/28)

アカデミー賞の行方は、「リベラル」を装おう俳優や製作陣の路線で決まることはあまりない。また、時代が「リベラル」な方に傾いているような時代だからといって、そういう傾向の作品が選ばれるとはかぎらない。
いまのように、もはや「リベラル」とか「保守」という枠組みが通用しなくなってきている時代には、俳優やスタッフの言動や雰囲気(たとえば、トランプ批判が多いとかの)からは、ますますその行方はつかみがたい。
事実、トランプによって「フェイク・メディア」と腐されたマスメディアで連日トランプ批判が続けられているにもかかわらず、かつての赤狩りのときのような、ハリウッドの内部から結束したトランプ批判が出るわけではない。そもそも、「結束」とか「連帯」という概念自体が有効性を失ってしまった。
しかし、アカデミー賞を審査する者は、既存メディアの空気のなかで生きているわけだから、それが「フェイク」であろうとなかろうと、影響を受けないはずはない。そこで今日は、一貫してトランプを支持しているFox Newsが今回のアカデミー賞に関して、どの作品や俳優・監督を支持しているかを見ながら、戦略的に「偏見」にみちた見立てをしてみようと思う。
Fox Newsのタリク・カーン (Tariq Khan) は、以下のような「予見」をする(→Oscars predictions)。
【作品賞】:『スリー・ビルボード』
【監督賞】:ギレルモ・デル・トロ(『シェイプ・オブ・ウォーター』)
【主演男優賞】:ゲイリー・オールドマン(『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』)
【主演女優賞】:フランシス・マクドーマンド(『スリー・ビルボード』)
【助演男優賞】:サム・ロックウェル(『スリー・ビルボード』)
【助演女優賞】:アリソン・ジャネイ(『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』)
なるほど、さすがFox Newsだ、わたしなどとは全く考えがちがう。が、なんてつまらない選択だろう。これでは、当たりはずれは別とする「予見」の楽しみがまったくないじゃないか。
Fox Newsが【作品賞】に『スリー・ビルボード』を選ぶのは、きわめてトランプ路線に忠実な選択だ。 フランシス・マクドーマンドが見事に演じたミルドレッド の「過激さ」が、実は、アメリカの「右翼」の根底にあるものであり、かつてのトランプの「手配師」スティーヴ・バノンのお好みのスタイルだからである。
カーンが【監督賞】にギレルモ・デル・トロを挙げたのは、他の選択を封じるための無難な選択にすぎない。
クリストファー・ノーラン(『ダンケルク』)
グレタ・ガーウィグ(『レディ・バード』)
ジョーダン・ピール(『ゲット・アウト』)
ポール・トーマス・アンダーソン(『ファントム・スレッド』)
上記の残りの4作品のうち、Fox Newsがどうしても避けたい作品がある。それは、『レディ・バード』である。ただし、それは、わたしがこの映画を評価しないのとは別の、もっと単純な理由による。要するに、この映画の舞台となるカリフォルニア州サクラメントと、カソリック校という要素がそもそもFox News 好みではないからに過ぎない。
映画の冒頭に、ジョーン・ディディオンの言葉が引用される。「カリフォルニア州の快楽主義について語る者は誰も、サクラメントでクリスマスを過ごすことなかった。」(→参考)まあ、そのくらい、禁欲主義が強いということだが、ちなみに、いまは違う。サクラメントは、いまでは、アメリカの都市のなかでLGBTQの人口が最も高い街の一つであり、カソリック系の学校に愛想をつかし、ニューヨークのコロンビア大学へ入ろうとする〝レディ・バード〟ことクリスティン(シアーシャ・ローナン)が、結果的にここにとどまるのは、この都市のその後の変化からするとまちがいではなかった。
監督グレタ・ガーウィグの自伝的要素の強い『レディ・バード』は、その意味で、17歳の高校生が変わって行く過程と都市の変化の予兆とを重ね合わせて見る示唆をあたえていて面白い。が、それならば、シアーシャ・ローナンは、もっと奥行のある演技をしなければならなかったし、監督はそういう演技指導をしなければならなかった。自殺願望的な要素を持ちながら、あっけらかんとしてもいるという、ある種「バイポラール」(「双極性障害」という訳語は使いたくない)的なキャラクターが、全然出ていないのだ。低予算で頑張っても、これでは、【監督賞】はあげられない。
『ゲット・アウト』のジョーダン・ピールは、アフリカン・アメリカンであり、ひねりを利かせているとはいえ、白人至上主義を批判しているかぎりで、潜在的にはFox Newsが避ける作品である。
あまり偏見にみちたFox News 批判も退屈だから、結論を急ぐ。
『ダンケルク』のクリストファー・ノーラン監督としては、いろいろと思い入れがあるだろうが、この作品は、彼のこれまでの映画的「冒険」からすると新味(少なくとも「素人」目から見たかぎりでの)がない。彼の演出の可能性が出きっているとは思えない。
 【監督賞】では、わたしは、『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロは非常に有力だと思う。【作品賞】を避けた者は、この作品に【監督賞】をあたえてバランスを取ろうとするパターンが考えられる。
【監督賞】では、わたしは、『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロは非常に有力だと思う。【作品賞】を避けた者は、この作品に【監督賞】をあたえてバランスを取ろうとするパターンが考えられる。
 しかし、この作品の基本と情感は、すでに『ヘルボーイ』シリーズにあったと思う。だから、わたしが、この作品よりも、最後に残る『ファントム・スレッド』のポール・トーマス・アンダーソンを選ぶのは、Fox Newsが推す作品には抵抗したいという子供じみた理由だけからではない。彼は、彼のこれまでの作品のなかでも異質なものを取り入れており、「冒険」をしているからである。
しかし、この作品の基本と情感は、すでに『ヘルボーイ』シリーズにあったと思う。だから、わたしが、この作品よりも、最後に残る『ファントム・スレッド』のポール・トーマス・アンダーソンを選ぶのは、Fox Newsが推す作品には抵抗したいという子供じみた理由だけからではない。彼は、彼のこれまでの作品のなかでも異質なものを取り入れており、「冒険」をしているからである。
俳優に関する賞については、次回を待たれたい。
(2018/03/01)

Fox Newsのアカデミー賞予想をとりあげたので、公平を期して、「敵対関係」にあるNew York Timesの予想を見てみよう。「わが社のエキスパートがオスカー・ウィナーを予言する」と大仰に出たカーラ・バックリー (Cara Buckley) の予想は以下の通りである。
【作品賞】:『シェイプ・オブ・ウォーター』
【主演女優賞】:フランシス・マクドーマンド(『スリー・ビルボード』)
【主演男優賞】:ゲイリー・オールドマン(『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』)
【助演女優賞】:アリソン・ジャネイ(『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』)
【助演男優賞】:サム・ロックウェル(『スリー・ビルボード』)
【監督賞】:ギレルモ・デル・トロ(『シェイプ・オブ・ウォーター』)
挙げる順番が、男優を先にするFox Newsに対して、女優を優先するのは New York Times の流儀なのだろう。筆者も女性であり、【主演女優賞】と【助演女優賞】に関しては、女性目線を重視している。
【作品賞】に『シェイプ・オブ・ウォーター』を選んだのは、New York Timesらしい選択だ。その「エレガントでドリーミーな」ところ、「寛容、残酷さ、人魚の性に関するデル・トロらしいお伽噺と寓話」、と同時に「映画へのオマージュ」を評価したいという。きわめてまっとうな意見である。
まあ、Fox にしてもTimes にしても、わかるひとにはわかるであろう「病的」な側面を隠した『ファントム・スレッド』のような作品は、避けるのである。
さて、【主演女優賞】に『スリー・ビルボード』のフランシス・マクドーマンドを選んだのは、彼女が「〝ミー・トゥ〟時代には誰でもが期待するであろう強い女」を「恐ろしいまでに容赦なく」表現しているからだと言う。
カーラ・バックリーのもの言いには、どこか奥歯にもののはさまった感じがあり、自分の本意はちょっとちがうというニュアンスが込められている。つまり、「〝ミー・トゥ〟時代」を全面的に肯定するわけではないが、時代の流れではこういうタイプが受けるでしょうねといった含みである。
ただし、わたしの印象では、〝ミー・トゥ〟で脚光をあびる女性は、 フランシス・マクドーマンドが演じるミルドレッド のようなストレートさはないような気がする。彼女は、後出しなんかはしない。むしろ、〝ミー・トゥ〟系の女性というのは、ミルドレッド的女性にあこがれながら、それができなかったが、みんなやり始めたからあたしも的な「みんな主義」のひとであって、ミルドレッドのような DIM (Do It Myself) ではない。
とはいえ、ここで論じなけらばならないのは、ミルドレッドではなく、それを演じるフランシス・マクドーマンドの演技である。それは、【主演女優賞】に値するのか? う~ん、迫真の演技ではあるが、古いのではないか? あいかわらずアクターズ・スタジオ系の「入れ込む」「役になりきる」演技の亡霊につきまとわれていないか?
コーエン兄弟のもとではそうはならないのだが、ガス・ヴァン・サントの『プロミスト・ランド』(2012) のスー・トマソン役がそうであったように、彼女の基本は舞台俳優的な演技なのだ。それは、助演ではいきるが、主役になると、その面が前面に出て来て、単調な感じがする。「うまい」けれど、新しくはない。
演技の多様性や奥行、繊細さやチャレンジ性という点では、『シェイプ・オブ・ウォーター』のサリー・ホーキンスは、はるかに上の演技を見せる。ハリウッドの政治経済がからまなければ、【主演女優賞】はこのひとで決まりではないか?
『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』のトニヤを演じるマーゴット・ロビーは、トニヤというキャラクターが「ぶっ飛び面白い」としても、マーゴット・ロビーでなければ演じられないわけではない。もっと適役がいたかもしれない。その点で、トニヤの母親は、アリソン・ジャネイならではの演技で、New York Times が【助演女優賞】に選んでいるのは納得できる。
【助演女優賞】の他の候補のうち、『シェイプ・オブ・ウォーター』のオクタビア・スペンサー、『ファントム・スレッド』のレスリー・マンビルは、いずれもベテラン中のベテランで、このぐらいの演技が出来ても何の驚きはない。『レディ・バード』のローリー・メトカーフ、『マッドバウンド 哀しき友情』のメアリー・J・ブライジは、何で候補になったのかわからない。『マッドバウンド 哀しき友情』は、「映画」というより、「テレビ映画」のつくりでわたしは買わない。
【主演男優賞】のTimes の選択は、『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』でチャーチルを演じるゲイリー・オールドマンで、Fox の選択と重なる。無難な選択である。こういうところが大メディアのつまらないところ。あたかも「視聴者」や「読者」や「大衆」という概念に実体があるかのような動きしかできない。ブロックチェーン的なピア・ツウ・ピア・メディアが台頭する時代にマスメディアに出来る意味あることは、挑発と偏執だ。
カーラ・バックリーによると、オールドマンは、『君の名前で僕を呼んで』のティモシー・シャラメや『ゲット・アウト』のダニエル・カルーヤのような「生意気な若造」 (whippersnapper) たちと互角にわたりあっており、キャリアのうえでも二人より上におり、また、『ファントム・スレッド』のダニエル・デイ=ルイスとデンゼル・ワシントンのようなベテランは、すでに何度も賞を獲っているからと、つまらない理由を挙げてオールドマンを【主演男優賞】に選ぶ。こういう言い方なら、演技をじっくり検証しなくても書けるだろう。
なぜもっとはっきり書かないのか? そもそも、『Roman J. Israel, Esq.』のワシントンは全然ダメである。『フライト』(2012) で見せたような屈折や矛盾やニヒルさやユーモアが混在した演技はどこかに行っている。つまりこの作品ではデンゼル・ワシントンは活かされていない。
アカデミー賞が年期や功労をねぎらう賞でないのなら、ティモシー・シャラメはいい仕事をした。ダニエル・カルーヤも悪くないが、作品の幅や奥行を考えると、シャラメの方が、面白い。早い話、『レディ・バード』にも出ていやいややっているかのような倦怠さとレイジーさをたたえた若者カイルの役を演じてもいるシャラメと、『君の名前で僕を呼んで』のエリオ役とを比較してみればいい。幅ある演技力がわかるだろう。
ゲイリー・オールドマンのチャーチル役は、メイクに負っている面がかなり強い。彼自身の俳優としての年輪に加えて潤沢な条件が整っている。その評価は、同時に候補に挙がっている【メイクアップ&ヘアスタイリング賞】の方で充たせばいいのではないか?
こういう特権的な条件のもとでの演技を評価するのなら、『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』で【主演女優賞】候補になっているメリル・ストリープおばさんなんかも真剣に考慮の対象にしなければならない。が、それはもういいと思うのなら、ゲイリー・オールドマンも除外すべきである。
どうも、あれこれ屁理屈を言って『ファントム・スレッド』のダニエル・デイ=ルイスに持っていこうとしているかのように思うかもしれなが、デイ=ルイスは、オールドマンに比べれば、「ノー・メイク」で演技している。オートクチュールの英国有数のドレスメイカーのステイタスを確立している初老の男が、無名の若いウェイトレスを愛するラブストーリーと思ったら、大間違い。単にマザコンで偏屈な老人ならいくらでもいる。老人好きの女もめずらしくはない。が、この映画の「主役」は、音楽であり、ある種の「ドラッグ」である。
観る方も、一度観ると抜けられなくなるかもしれない。というよりも、こういう映画で俳優として演技をするのは、並大抵のことではないと思うのだ。一見、初心(うぶ)な娘を「平凡」に演じているかに見えるヴィッキイー・クリープスも、【助演女優賞】にノミネートされてもいいくらいだ。
ダニエル・デイ=ルイスは、この映画を最後に、今後は、すでに本職裸足の靴作りに専念するとのことだが、そもそも針で縫うということ、しかも靴の底ではなく、女をまとう布を糸で縫っていくということは、きわめて「変態」的な行為でもある。それしか頭にない男を演技するのは、単に「仕立て」や「裁縫」の職人技を真似るのでは足りない。というより、そういうレベルを表現するには、別に針使いなど見せなくてもいい。デイ=ルイスは、それをただ歩き回ったり、手を些末に動かすだけで、表現しつくした。
というわけで、わたしは、断固としてダニエル・デイ=ルイスの【主演男優賞】を推したい。たとえ、それが、胡蝶の夢であるとしても。
『スリー・ビルボード』のサム・ロックウェルを【助演男優賞】に推すひとは多い。
『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』のウィレム・デフォーは、『スリー・ビルボード』のウッディ・ハレルソンに劣らぬベテランだが、この作品で彼の演技がいかされているとは思えない。「ベテラン」は、もういいんじゃないか?
『ゲティ家の身代金』のクリストファー・プラマーは、ご老体の身でそんなに頑張って大丈夫かねといった演技だったが、『シェイプ・オブ・ウォーター』のリチャード・ジェンキンスの演技の味わいは忘れがたい。
しかし、ジェンキンスの演技を取るならば、デフォーもハレルソンも同じ台に乗せなければならなくなる。
そういうわけで、【助演男優賞】に関しては、候補のなかにわたしがこれだと思うひとはおらず、受賞は、サム・ロックウェルに行くのを傍観することになる。
カーラ・バックリーは、選考理由として、サム・ロックウェルは、ディクソンという人物の意識の大きな変化過程を表現しなければならないという要求に応えており、それは、アカデミーの選考委員たちには受けるのだと、書いているが、またしても、言い方が直截ではない。
【監督賞】は、Fox Newsと同じく、『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロを選んでいるが、その場合にも、バックリーの言い方には棘がある。曰く、「もし彼が金をかっさらえば、この5年間に4度ひとりのメキシコ系の監督が賞を持ち去ることになる」と。
たぶん無理と思うが、作品の質から正しく選ばれるならば、【監督賞】は、『ファントム・スレッド』のポール・トーマス・アンダーソンに獲ってもらいたい。
(2018/03/02)

トランプとともに変わったものは何か? 〝ミィー・トゥー〟主義の台頭である。ファシズムでも赤狩りでも大恐慌でもなかった。それは、トランプの「プッシーわしづかみ」スキャンダルとともに波及した。
2010年代の終わりは、だから、ミートゥーイズムの時代である。すべてが、このパースペクティヴで見られ、語られる。映画の評価も、例外ではない。
この主義が蔓延する発端を作ったトランプ自身は、したたかにも、この主義を逆手に取ろうとしている。代わりに彼の〝複製細胞〟が次々に破滅した。
が、当初、「変革」や「批判」の装いをみせていたミートゥーイズムは、いまやある種の制度や慣習となり、その影響を考慮せずに表現することも、ひとと交流することも出来なくなってきた。
その意味で、「古い」と「新しい」という単純だが便利な価値基準でものを語る際には、ハラスメントの度合いが尺度になる。が、ハラスメントとは何か?
それは、他人の「心」というよりも身体に浸食することである。だから、もう、ハグはおろか握手も気をつけなければならない。キスは、頬にする場合でも数センチ以上の距離を置こう。身体性の内部と外部につねにヴァリアブルな距離を持つことが「常識」となる。
これは、別枠で詳述したいが、いまにわかに高まりつつあるヴィーガニズム (veganism) への「新たな」関心とも関係がある。アニマルフレンドリーであること、動物を虐待しない、殺さない、食べない・・・とは、動物の身体を浸食しないことである。というよりも、浸食しないことへの極度の恐れと配慮だ。それは、単なる「菜食主義」の徹底ではない。
主義には、便乗と反動がともなう。「わたしも、わたしも」と後出しの告発に邁進する者が登場する一方で、身体性そのものを消去するために、銃を乱射したり、自傷したり、生命そのものを否定する者が増える。
そのため、人々はおのずから、それぞれの「避難所」に閉じこもったり、自らの身体に「避難所」を作ろうとする。最初は、反逆や防衛を試みるが、閉じこもり、引きこもるしかないことを悟る。
この傾向は、ミートゥーイズム以前からあったし、メディアテクノロジーがスマホのような形式に自閉・収斂するときには必然的な帰結であったとも言える。
御託は聞き飽きただろう。問題は2018年のアカデミー賞のことだった。では、いま書いたような観点から今年のアカデミー賞候補を見てみたら、どうなるだろうか? 見るべきは、内容よりも身体のあつかい方であり、その自己意識である。
こいういうことを考えながら、【外国語映画賞】の候補作品を取り上げると、真っ先に上がってくるのは、ハンガリーのイルディコー・エニェディ監督の『心と体と』(国際的な英語タイトル:On Body And Soul)である。

この作品は、牛の食肉処理工場で働く男アンドレ(ケーザ・モルチャーニ)とマリア(アレクサンドラ・ボルベーイ)のある種の「ラブストーリー」であるが、その116分のあいだに、いまの時代の、他者および自己の身体感覚、コミュニケーション、そしてさらには、肉食問題までが問われている。
それらは、決して「メッセージ」として表現されるのではない。おそらくこの工場の事故で左手を損傷したらしい中年後期のアンドレには、すでに人生を投げている雰囲気がある。食肉の検査担当のマリアは、かなり自閉症っぽい。
 その二人が、わずかにコミュニケーションを交わすようになるのは、勤務者の精神衛生担当医(二人の雰囲気とは裏腹にやけに艶めかしい女性)による面接で二人が同じ日に一つながりの夢を見たことがわかったからだった。偶然にすぎないかもしれないし、テレパシーかもしれない。
その二人が、わずかにコミュニケーションを交わすようになるのは、勤務者の精神衛生担当医(二人の雰囲気とは裏腹にやけに艶めかしい女性)による面接で二人が同じ日に一つながりの夢を見たことがわかったからだった。偶然にすぎないかもしれないし、テレパシーかもしれない。
この面接は、「個人情報」に立ち入る質問をあけすけに行うが、一方で「個人情報」を閉ざしながら、他方では、それを守るためと称してすべてが記録されざるをえないといういまの時代の皮肉を示唆してもいる。
こういう社会では、もはやこれまで通用した、おしゃべりを交わすとか、食事を共にするとか、さらにはセックスすらも、「親密さ」を深める方法にはならない。
 ただ、二人が見た夢を示唆する、雪景色のなかに二匹の鹿がいる映像は、ただ寒々しいとも言えるし、また寒々しいにもかかわらずそこで鹿が悠々と生きているところに救いがあるともいえるが、映画の終わり方はやや安易である。投げかける問題が多いだけに、この「ハッピーエンド」は残念だった。
ただ、二人が見た夢を示唆する、雪景色のなかに二匹の鹿がいる映像は、ただ寒々しいとも言えるし、また寒々しいにもかかわらずそこで鹿が悠々と生きているところに救いがあるともいえるが、映画の終わり方はやや安易である。投げかける問題が多いだけに、この「ハッピーエンド」は残念だった。
マリアの意識を二重の意味で変えるきっかけになるのは、レンタルショップ店で買ったCDの曲、ローラ・マーリングが歌う
"What He Wrote" 。まあ、彼女は、この曲に飽きたら、またこの映画の始まりのときのような状態にもどってしまうのかもしれないが。
【外国語映画賞】の候補には、あと、『ナチュラルウーマン』、『ラブレス』、『ザ・スクエア 思いやりの聖域』、『The Insult』があり、わたしは、『ナチュラルウーマン』を面白く見たが、映画としては、『心と体と』よりも「古典的」である。
そろそろ、発表までの時間が迫ってきた。書けるのは、あと1回ぐらいか?
(2018/03/03)

いろいろと御託をならべながらノミネート作品を論評したが、今回の候補作のなかで、わたしが、率直に楽しんだのは、エドガー・ライト監督の『ベイビー・ドライバー』だった。候補になる以前から魅惑されていたので、【編集賞】、【録音賞】、【音響編集賞】にトリプルでランクされたのは、喜ばしいことだった。

 が、同時に、それだけかいという気持ちも隠せなかった。だって、主役のアンセル・エルゴートも、強盗団のボス役のケビン・スペイシーもよかったし、脚本(エドガー・ライト)だって、撮影(ビル・ポープ)も、美術(マーカス・ローランド)だって、すごくいいと思ったからである。
が、同時に、それだけかいという気持ちも隠せなかった。だって、主役のアンセル・エルゴートも、強盗団のボス役のケビン・スペイシーもよかったし、脚本(エドガー・ライト)だって、撮影(ビル・ポープ)も、美術(マーカス・ローランド)だって、すごくいいと思ったからである。
 公開時の反響がノミネイションにつながらなかったのには、その間に暴露されたケヴィン・スペイシーのスキャンダルの影響もある。が、それにもかかわらず、サウンド・ミックシングの【録音賞】とサウンド・エディティングの【音響編集賞】にノミネートせざるをえなかったことを見ても、この作品のユニークさがわかろうというもの。
公開時の反響がノミネイションにつながらなかったのには、その間に暴露されたケヴィン・スペイシーのスキャンダルの影響もある。が、それにもかかわらず、サウンド・ミックシングの【録音賞】とサウンド・エディティングの【音響編集賞】にノミネートせざるをえなかったことを見ても、この作品のユニークさがわかろうというもの。
【録音賞】と【音響編集賞】に関しては、他に、『ダンケルク』、『シェイプ・オブ・ウォーター』、『ブレードランナー 2049』、『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』がノミネートされているが、わたしは、断固として『ベビー・ドライバー』に獲ってほしいと思う。
 他の4作品がいかにも腕利きのエンジニアと潤沢な資金を駆使して大「映画工場」で作った作品の様相を呈しているとすれば、『ベビー・ドライバー』は、エドガー・ライトという一人のマニアックな天才が手作りで作ったような個性にあふれている。むろん、一人で作ったわけではないが、そのチームワークのやり方には、古典的な企業と最新のヴェンチャービジネスとの差ぐらいのちがいがある。
他の4作品がいかにも腕利きのエンジニアと潤沢な資金を駆使して大「映画工場」で作った作品の様相を呈しているとすれば、『ベビー・ドライバー』は、エドガー・ライトという一人のマニアックな天才が手作りで作ったような個性にあふれている。むろん、一人で作ったわけではないが、そのチームワークのやり方には、古典的な企業と最新のヴェンチャービジネスとの差ぐらいのちがいがある。
その意味で、この作品は、映画を作りつつある映画のビギナーが見たとき、ひょっとすると自分でも作れるかもしれないという「幻想」と夢をいだかせるようなところがあり、映画の未来を明るくする。スピルバーグにしても、タランティーノにしても、そしてゴダールにしても、みな、そういう「幻想」と夢に後押しされて映画の世界に入ってきたのではなかったか?
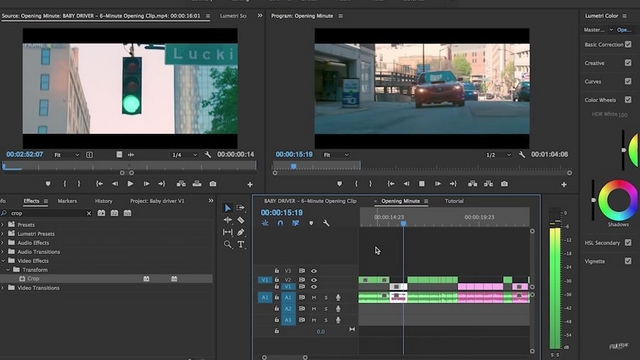 しかし、【編集賞】の場合は、若干事情が異なる。サウンドと映像とを比べた場合、これまでさまざまな技術が投入されたとはいえ、映像がスクリーンに投射されるという点において変わりはなく、そこで出来ることがサウンドより狭い。そのため、『ベビー・ドライバー』のような、編集者の「顔が見える」編集の仕方と、他の4作のような「映画工場」的な編集とのあいだで、評価がわかれてしまうのだ。
しかし、【編集賞】の場合は、若干事情が異なる。サウンドと映像とを比べた場合、これまでさまざまな技術が投入されたとはいえ、映像がスクリーンに投射されるという点において変わりはなく、そこで出来ることがサウンドより狭い。そのため、『ベビー・ドライバー』のような、編集者の「顔が見える」編集の仕方と、他の4作のような「映画工場」的な編集とのあいだで、評価がわかれてしまうのだ。
音楽のリズムとビート、アクショのスピード、会話のピッチが、ありがちなDJ的(といってはDJに失礼だが)な組み合わせではない、有機的なひとつながりの織物になっている映・音像(両者はもはや分離できない)。そこには、既存の音楽・映画作品へのオマージュ・引用・たわむれもある。
スタントやカーのアクションも、ミュージカルに刺激をあたえさえする振付(コレオグラフィー)になっているような新しさ。これは、「アクション・ミュージカル」だという評価もある。ちなみに、カーチェイスのシーンは、CGIではなく、すべて実写だという。
しかし、これらの、わたしには新しいと思われる要素も、「映画=夢工場」の「プロ」たちには、子供だましに見えるかもしれない。すくなくとも、【編集賞】に関しては。このへんで過去を振り切れないことが、映画の将来を暗くする。
すでに、第90回アカデミー賞の儀式の開催まであと12時間しかなくなった。「映画=夢工場」の「成績」が評価される度合いの強い【脚本賞】、【脚色賞】、【撮影賞】、【衣装デザイン賞】等については、素人は論評を遠慮しておく。
授賞式でもし意外なことでも起こったら、また書くかもしれない。久しぶりに映画のことを長めに書き、楽しかった。
(2018/03/04)

 エレクロトニカの鋭角的な音で始まるこの映画で音楽と音の力は大きい。音楽がエモーショナル・ナレーターを演じているとも言える。好き嫌いはあるだろうが、ジョニー・グリーンウッドはいい仕事をした。【作曲賞】の候補になっているが、その資格は十分だ。
エレクロトニカの鋭角的な音で始まるこの映画で音楽と音の力は大きい。音楽がエモーショナル・ナレーターを演じているとも言える。好き嫌いはあるだろうが、ジョニー・グリーンウッドはいい仕事をした。【作曲賞】の候補になっているが、その資格は十分だ。
 ここでテーマ音楽を含めてピアノを弾いているカスリーン・ティンカー(Katherine Tinker) は、ロンドンの若いアーティストで、これがフィーチャー映画では初仕事のようだが、これからどんどん出てくるひとに思える。グリーンウッドの引きで参加したらしい。
ここでテーマ音楽を含めてピアノを弾いているカスリーン・ティンカー(Katherine Tinker) は、ロンドンの若いアーティストで、これがフィーチャー映画では初仕事のようだが、これからどんどん出てくるひとに思える。グリーンウッドの引きで参加したらしい。
 【監督賞】では、わたしは、『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロは非常に有力だと思う。【作品賞】を避けた者は、この作品に【監督賞】をあたえてバランスを取ろうとするパターンが考えられる。
【監督賞】では、わたしは、『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロは非常に有力だと思う。【作品賞】を避けた者は、この作品に【監督賞】をあたえてバランスを取ろうとするパターンが考えられる。 しかし、この作品の基本と情感は、すでに『ヘルボーイ』シリーズにあったと思う。だから、わたしが、この作品よりも、最後に残る『ファントム・スレッド』のポール・トーマス・アンダーソンを選ぶのは、Fox Newsが推す作品には抵抗したいという子供じみた理由だけからではない。彼は、彼のこれまでの作品のなかでも異質なものを取り入れており、「冒険」をしているからである。
しかし、この作品の基本と情感は、すでに『ヘルボーイ』シリーズにあったと思う。だから、わたしが、この作品よりも、最後に残る『ファントム・スレッド』のポール・トーマス・アンダーソンを選ぶのは、Fox Newsが推す作品には抵抗したいという子供じみた理由だけからではない。彼は、彼のこれまでの作品のなかでも異質なものを取り入れており、「冒険」をしているからである。


 その二人が、わずかにコミュニケーションを交わすようになるのは、勤務者の精神衛生担当医(二人の雰囲気とは裏腹にやけに艶めかしい女性)による面接で二人が同じ日に一つながりの夢を見たことがわかったからだった。偶然にすぎないかもしれないし、テレパシーかもしれない。
その二人が、わずかにコミュニケーションを交わすようになるのは、勤務者の精神衛生担当医(二人の雰囲気とは裏腹にやけに艶めかしい女性)による面接で二人が同じ日に一つながりの夢を見たことがわかったからだった。偶然にすぎないかもしれないし、テレパシーかもしれない。 ただ、二人が見た夢を示唆する、雪景色のなかに二匹の鹿がいる映像は、ただ寒々しいとも言えるし、また寒々しいにもかかわらずそこで鹿が悠々と生きているところに救いがあるともいえるが、映画の終わり方はやや安易である。投げかける問題が多いだけに、この「ハッピーエンド」は残念だった。
ただ、二人が見た夢を示唆する、雪景色のなかに二匹の鹿がいる映像は、ただ寒々しいとも言えるし、また寒々しいにもかかわらずそこで鹿が悠々と生きているところに救いがあるともいえるが、映画の終わり方はやや安易である。投げかける問題が多いだけに、この「ハッピーエンド」は残念だった。

 が、同時に、それだけかいという気持ちも隠せなかった。だって、主役のアンセル・エルゴートも、強盗団のボス役のケビン・スペイシーもよかったし、脚本(エドガー・ライト)だって、撮影(ビル・ポープ)も、美術(マーカス・ローランド)だって、すごくいいと思ったからである。
が、同時に、それだけかいという気持ちも隠せなかった。だって、主役のアンセル・エルゴートも、強盗団のボス役のケビン・スペイシーもよかったし、脚本(エドガー・ライト)だって、撮影(ビル・ポープ)も、美術(マーカス・ローランド)だって、すごくいいと思ったからである。 公開時の反響がノミネイションにつながらなかったのには、その間に暴露されたケヴィン・スペイシーのスキャンダルの影響もある。が、それにもかかわらず、サウンド・ミックシングの【録音賞】とサウンド・エディティングの【音響編集賞】にノミネートせざるをえなかったことを見ても、この作品のユニークさがわかろうというもの。
公開時の反響がノミネイションにつながらなかったのには、その間に暴露されたケヴィン・スペイシーのスキャンダルの影響もある。が、それにもかかわらず、サウンド・ミックシングの【録音賞】とサウンド・エディティングの【音響編集賞】にノミネートせざるをえなかったことを見ても、この作品のユニークさがわかろうというもの。 他の4作品がいかにも腕利きのエンジニアと潤沢な資金を駆使して大「映画工場」で作った作品の様相を呈しているとすれば、『ベビー・ドライバー』は、エドガー・ライトという一人のマニアックな天才が手作りで作ったような個性にあふれている。むろん、一人で作ったわけではないが、そのチームワークのやり方には、古典的な企業と最新のヴェンチャービジネスとの差ぐらいのちがいがある。
他の4作品がいかにも腕利きのエンジニアと潤沢な資金を駆使して大「映画工場」で作った作品の様相を呈しているとすれば、『ベビー・ドライバー』は、エドガー・ライトという一人のマニアックな天才が手作りで作ったような個性にあふれている。むろん、一人で作ったわけではないが、そのチームワークのやり方には、古典的な企業と最新のヴェンチャービジネスとの差ぐらいのちがいがある。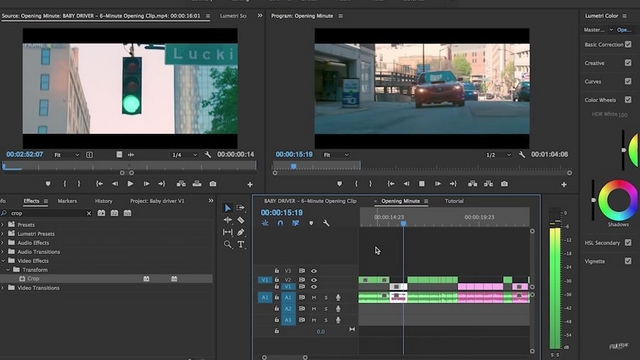 しかし、【編集賞】の場合は、若干事情が異なる。サウンドと映像とを比べた場合、これまでさまざまな技術が投入されたとはいえ、映像がスクリーンに投射されるという点において変わりはなく、そこで出来ることがサウンドより狭い。そのため、『ベビー・ドライバー』のような、編集者の「顔が見える」編集の仕方と、他の4作のような「映画工場」的な編集とのあいだで、評価がわかれてしまうのだ。
しかし、【編集賞】の場合は、若干事情が異なる。サウンドと映像とを比べた場合、これまでさまざまな技術が投入されたとはいえ、映像がスクリーンに投射されるという点において変わりはなく、そこで出来ることがサウンドより狭い。そのため、『ベビー・ドライバー』のような、編集者の「顔が見える」編集の仕方と、他の4作のような「映画工場」的な編集とのあいだで、評価がわかれてしまうのだ。