2015年第87回アカデミー賞の顛末
例年通り、2015年1月25日から2月21日までアカデミー賞の「予測」と称し、候補に挙がった作品のどれがウィナーになるか、なるとすればその条件はなにか、ならないとすれば、その周辺にはどんな問題がからんでいるのかを思いつくままにかきなぐってみた。以下の囲みの記事がそのすべてだが、その「予測」が当たったものもあり、はずれたものもある。昨年よりもはずれたほうが多いかもしれないが、以下の「コメント」を書く刺激を得ることができたことに満足している。
ここでの「予測」よりも実質的な予測は、IMDbのMessage Boardに「実りある選択かあるいは日和見的選択か」("My Viable or Opportunistic Selections from the the Oscar 2015 nominees")というタイトルで一覧を発表してある。こちらの「日和見的」選択のほうは、かなり当たっている。この「日和見的選択」とは、要するに作品そのものの評価とは関係のない業界的な噂をもとに推測した選別である。
詳細英語情報→AWARDS CENTRAL (IMDb)
【受賞作品について】
【落選した問題作】
【受賞作と「予測」の流れ】
●作品賞: バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)
◆ゴールデングローブ賞でもアカデミー賞でも、優先されるのは、凡庸な大衆性である。その大衆性は必ずしも数の大衆性ではなくて、映画コミュニティの意識の高揚の平均値であるが、異様なものや突出しているものはおおむね退けられる。
◆候補に挙がった8作品のうち、『6才のボクが、大人になるまで。』の受賞を予想する者の数が一番多い。賞に意外性を求めなければ、そうなるだろう。『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の実質以上の評価は、映画評論家や映画通を気取るひとたちのスノビッシュな弱みが影響している。『セッション』への評価は、メソードアクティング過剰の演技に映画のリアリティを感じてしまう感覚がまだまだ映画批評の平均値になっていることを物語る。
◆とはいえ、『セッション』は、ネタバレすると、メソードアクティング過剰の演技を相対化していると言えないこともない。鼻につくのは、J・K・シモンズが演じる音楽リーダー、フレッチャーだが、この映画の主題は、〝リーダー面してるけど、テメエなんかいらないよ〟ということだからである。最後まで自分がコントロールしようとするフレッチャーに対して、ドラマーのアンドリュー(マイルズ・テラー)が反抗する。最後にフレチャーは、自分の醜さを自覚するが、にもかかわらず最後は自分がコントロールしているということを誇示しようとする。原題の"Whiplash"は〝ムチ打症〟(ここから転じて、ふだんうちとけた相手が急に白々しかったりすることをも指す)のことで、フレッチャーは、トレイニングには厳しくムチ打つ必要があり、その結果としての〝ムチ打ち症〟として教育の成果があがると信じているらしい。が、そういう教育は古いんだよ。このへんの支配と反抗の闘争劇はなかなか見どころがあるのだが、にもかかわらず、この映画を買えないのは、少なくとも個々のプレイヤーの力がちゃんと評価されるバンドなら、こんなバカな関係は成り立ちえないからである。すべてが映画効果のためのプロットだからである。
◆『グランド・ブダペスト・ホテル』の圧倒的な完成度は高く評価されるべきだが、知的なスタイル性や物語性に富んだ軽快なリズム性よりも、「人生観」だとか「信憑性」や「迫力」を重視する向きは、音楽コーチと生徒との「スリリング」な相反関係や J・K・シモンズの見え透いた「圧倒的な熱演」の『セッション』のほうを支持するだろう。知的なレベルで言えば、『グランド・ブダペスト・ホテル』の躍動する知的快楽よりも、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の思わせぶりな「知的」スノビズムが勝つだろう。つまり、『グランド・ブダペスト・ホテル』がトップに位置するには、二重の壁がたちはだかる。
◆マーチン・ルーサ・キングとはいえ、アフリカンアメリカンの抑圧と解放というテーマは、昨年度で打ち止めではないだろうか? 『セルマ〔仮題〕』の受賞の可能性は薄い。
◆『博士と彼女のセオリー』でエディ・レッドメインは、彼がこういう役を演じたという意味では面白いのだが、ホーキング博士をクソリアリズムで模倣している凡庸さを評価するとしたら、このレベルの作品はいくらでもあるから、作品賞の評価基準を替えなければなるまい。
◆科学的な天才をあつかっている点では似ている部分がある『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』は、アラン・チューリングの顔やものごしをクソリアリズム的に真似たりはしない。チューリングといえば、ナチの暗号を解読した功績以上に、コンピュータの基礎理論を構築した有数の人物の一人として有名だが、この映画は、その間の仕事を、彼が「晩年」同性愛の嫌疑で逮捕(1950年代には同性愛は違法だった)されたとき、警察の取り調べ官に物語るという形式で描かれる。暗号解読の劇的な興奮のプロセスも描かれるが、それが、「異分子」差別への批判的な視点で二重化されている。とはいえ、アカデミー賞の作品賞の候補としては、どうしてもマイナーな位置におしやられそうである。
◆クリント・イースウッドの『アメリカン・スナイパー』は、アメリカの国家的矛盾を鋭く描ききっている。それは、一見、愛国主義者の栄光を讃えているかのように見えるが、911にショックを受け、アメリカ海軍の特殊部隊NavySEALsの狙撃兵を志願したクリス・カイル(ブラッドリー・クーパー)が、イラクで史上例のない成功(狙撃による敵の死者255人中160人の「敵」を一人で殺したといわれる)をおさめる一方、徐々に戦争後遺症にむしばまれていくさまを描いている。狙撃に成功すればするほど、その弾は狙撃する者の心に跳ね返って虚無の穴をうがつのである。ちなみに、映画は、軍人であることをやめたクリス・カイルが遊びに出かけるといった風情のシーンで終わるが、カイル自身は、こののち、射撃場でむかしの仲間に銃殺されてしまう。が、これに続くエンディングで、彼の死を悼む市民の姿を当時の記録映像で流すが、それは、決して、愛国主義者を市民が悼むだけのシーンには見えない。ここにイーストウッドの鋭い、そしてそれを居丈高には示さない批判精神がある。折しも、フランスでも日本でも「イスラム国」問題が緊急の課題になり、テロと戦争の悪循環の先に光明はますます見えなくなっている。敵をピンポイントで殲滅しても、解決にはならない。『アメリカン・スナイパー』のなげかける課題は深く、重い。
◆『アメリカン・スナイパー』と『6才のボクが、大人になるまで。』は、アメリカの現実の陰と陽の部分を表現している。後者の主人公は、一応、タイトル通り、エラー・コルトレーンが演じるメイソンであるが、リチャード・リンクレイターのこれまでの作品との関係をあわせて考えると、メイソンの父親(イーサン・ホーク)が、妻子をもちながら、(むろん離婚や別居の形を取るとしても)いかに「スラッカー」(フリーター以上に働くことそのものを拒否するひとたち)であり続けるかというテーマを追求している。それは、同時に、男が家父長的な男であることをやめることであり、女性が家父長的な男から自律することを意味する。アメリカでは、パパ/ママ/ミーの核家族とセットになった20世紀型の資本主義がほころびを見せ、「21世紀の資本」(トマ・ピケティ)が求められつつあるが、そういうトレンドからすこしずれたアメリカ西南部に舞台を設定しているところも賢明だ。12年間という時間をかけながら、しかも、決してドキュメンタリー映画ではないところも、新鮮さがある。
◆『6才のボクが、大人になるまで。』のなかで、もとはオリヴィア(パトリシア・アークエット)のカレッジの学生の一人だったジム(ブラッド・ホーキンス)――やがて彼女の恋人になる――が夕食に招かれて、イラクに陸軍の州兵として行ったときの話をするシーンで、隣の客が「なぜアメリカはイラクへ行ったの?」と問うと、彼は、「石油(オイル)さ、単純明快だよ」と答える。この映画には、ブッシュ政権やネオコン、その政治と価値観をともにしてきた人間への揶揄や批判が随所にあるが、イラク戦争から10年を経過して、アメリカは、「シェールオイル革命」で、エネルギーをアラブの石油に頼る方向を脱しはじめた。いま、オイルのために中東に戦争をしかける必然性が薄まっている。とはいえ、政治と経済の利権をともにする国々を「支援」するという形での戦争から手を引いたわけではない。つまり、アメリカは、『アメリカン・スナイパー』の諸問題を依然として抱え込んだままなのである。
◆その意味で、作品賞が『6才のボクが、大人になるまで。』か、それとも『アメリカン・スナイパー』かという選択は、いまのアメリカが、その「未来」をオプティミスティックに取るか、それとも悲観的にとるかの尺度でもある。わたしは、そう簡単にアメリカの未来が開かれるとは思えないので、『アメリカン・スナイパー』を取ろうと思う。
(2015/01/25)
●主演男優賞: エディ・レッドメイン [博士と彼女のセオリー]
◆『フォックスキャッチャー』がゴールデングローブの作品賞にノミネートされたときは、ゴールデングローブの枠のなかでは無理としても、アカデミーでノミネートされることが確実になったと思った。だが、そうはならなかったのを知り、今年のアカデミーは去年以上に凡庸な選別なのだなと思った。その意味で、スティーヴ・カレルとマーク・ラファロがゴールデングローブでもここでも候補からはずれていないのは、それだけ彼らの演技が有無を言わせぬものだったからである。とにかく、スティーヴ・カレルの演技は、狂気の新しい演技としても、また、彼自身のキャリアを飛躍させた点でも、最高に評価できるのである。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』におけるベネディクト・カンバーバッチは、ジェンダー的にも、才能的にも、その本来性を活かす場にめぐまれたとは言えない実在の科学者アラン・チューリングの屈折を有機的に演じていた。しかし、これは、決してカンバーバッチの最高の演技ではない。
◆『アメリカン・スナイパー』のブラッドリー・クーパーは、『ハングオーバー』シリーズでも『リミットレス』でも『世界にひとつのプレイブック』でも『アメリカン・ハッスル』でも、自分のいいかげんさに当惑しているようなキャラクターが定番になっていたのを雲散霧消させた。東部から南部の男に、インテリから汗臭いワーキングクラスの男に体型自体が変わってしまったかのようだ。口ごもった口調でニヤニヤ笑う男ではなく、国家を狂信からではなく、ごく自然の意識で信じてしまう男。彼が仕事に忠実になればなるほど、殺す敵の数が増える。国家に忠実な兵士の矛盾。といって、彼が演じるクリス・カイルという男は、『ハート・ロッカー』でジェレミー・レナーが演じたウィリアム・ジェームズが、絵に描いた〝戦争中毒患者〟に見えてしまうほど〝まとも〟なのである。そして、だからこそ、そこに秘められ、徐々に噴き出してくる狂気は恐ろしい。映画は、その爆発は描かない。妻と別れたクリスは、射撃場に遊びに行き、かつての戦友に撃たれて死ぬのだが、出かけるまえ、ふざけながら妻に拳銃を向けるシーンがある。それは、さりげないシーンだが、この男の深い狂気がよくあらわれている。しかし、狂気の表現としては、『フォックスキャッチャー』のスティーヴ・カレルをより高く評価するので、次席に置く。
◆マイケル・キートンの存在を知ったのは、日本企業へに鋭い揶揄を含む『ガン・ホー』(1986)だったが、その後、『ビートルジュース』(1988)を見て、この俳優のエキセントリックな異能の演技に感心した。〝普通〟を演じながら、決して半端ではない感じは、湾岸戦争のテレビ取材をシニカルに描いたテレビ映画の『Live from Baghdad』(2002)によくあらわされていたと思ったが、それを全面展開する機会は、今回の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』までなかったと言ってよい。しかし、気取りの韜晦で煙にまく気配の強い、〝芝居の芝居の芝居〟のようなこの作品でキートンの才能が全面展開されたとは思えない。とはいえ、彼も今年、64歳。功績賞としては資格十分ではある。
◆エディ・レッドメインは、いい筋を持っている。『ザ・デンジャラス・マインド』(Like Minds/2006/Gregory Read)から、『マリリン 7日間の恋』、『レ・ミゼラブル』へと強い印象を残しながら成長してきた。だから、『博士と彼女のセオリー』のようなテレビの再現ドラマ風のソックリさん演技はしてほしくなかった。
(2015/01/26)
●主演女優賞: ジュリアン・ムーア [マップ・トゥ・ザ・スターズ]
◆『サンドラの週末』で、〝ブラック〟な会社の身勝手な論理に追い詰められる底辺の(といって居直ることもできない無力な)女性労働者を演じるマリオン・コティヤールは、これまでに演じた役柄と全く異なる人物になりきっている。といって、そのうまさをこれ見よがしにするのではなく、文字通りこの人物と同じようにつつましく演じているのは、高く評価できる。コティヤールの演技の歴史のなかでも特異な位置を占めるだろう。が、主演女優賞にはマイナーな演技とみなされる。
◆『博士と彼女のセオリー』のフェリシティ・ジョーンズは、けなげではあるが、“自信のないスカーレット・ヨハンソン”のような彼女の演技のどこが傑出しているのかが、わたしにはよくわからない。『ヒステリア』(2011)では、マギー・ギレンホールのまえで全く影が薄かった。が、ニューヨークのアップステイとのファミリーの家にホームステイする学生を演じた『Breathe In』(2013) で見せた、心のなかに他人への距離を潜ませた役柄は悪くなかった。ある意味で、『博士と彼女のセオリー』でジョーンズは、その全力を出す機会にめぐまれたわけだが、『Breathe In』で見せたような心に距離を潜めた役柄のほうが向いているという点で、(トレイラーで見るところでは)最新作の『True Story 』(2015)のほうが『博士と彼女のセオリー』よりももっと彼女に向いた演技を見せているのではないか?
◆『ゴーン・ガール』のロザムンド・パイクの演技はすばらしい。内臓のどこかが悪くて、午後に起きたとき、顔がむくんでいるような女。性交よりもクンニリングスが好きで、図書館のような閉ざされ、奥深い過去につながっている子宮的な空間で淫乱になる女。自分が「悪い女」で、罰してほしいと願っている。自分が構築したロジックのためなら男の首をボックスナイフで掻っ切ることも辞さないし、完璧なまでのたくらみを実行する。が、にもかかわらず、それが、高温多湿なノース・カロライナの町カーセージの、個々人は閉ざされながらも、(あるいはだからこそ)テレビが世間を作っている環境では〝ノーマル〟に見えてしまう。これもある種の〝狂気〟表現だが、『フォックスキャッチャー』のジョン・デュポンや『アメリカン・スナイパー』のクリス・カイルの〝狂気〟よりもある種の普遍性を持っており、主演女優賞にふさわしい。
◆〝主演女優賞〟と訳す/略すアカデミー賞のひとつは、"Best Performance by an Actor in a Leading Role"と記されている。『マップ・トゥ・ザ・スターズ』のジュリアン・ムーアは、たしかに、〝主導的役割〟を演じているが、決して〝主演〟ではない。いかにもハリウッドにいそうな女をその神経症や脆さがむんむんするほどの密度で表現してはいるが、この映画の〝主役〟は、ムーアではなくて、ミア・ワシコウスカであり、顔を出す度合はムーアより少ないが、最後に彼女の怨念を内に秘めた個性が発揮される。わたしは、クローネンバーグが近年〝演劇志向〟に陥っているのをこころよしとしないのだが、この作品をひとつの演劇作品と見たとき、クライマックスでワシコウスカが見せる演技は、その構造に見合っているし、彼女を〝主演女優〟と見なすことに何の不都合もないと思う。しかし、彼女はノミネートされなかった。
◆ジュリアン・ムーアは、『アリスのままで』で、ゴールデングローブの主演女優賞を取った。こちらは文字通りの〝主演〟であり、『マップ・トゥ・ザ・スターズ』とは全く異なるキャラクターを劇的ではなく演じた。それは、ある意味で〝テレビ的〟であったし、だからこそ(認知症というテーマとともに)ゴールデングローブ賞に向いていた。はたして、これにくわえて『マップ・トゥ・ザ・スターズ』の彼女に主演女優賞をあたえる意味があるだろうか? メリル・ストリープとまさるとも劣らないヴァーサタイルの女優であるから、何を演じても、並の演技は軽々と凌駕してしまう。だから、ジュリアン・ムーアを選ぶの不当ではないのだが、それだけ安易だとも言える。もっと新人や受賞歴がすくない俳優に賞をあたえるべきだろう。結論は、彼女が主演女優賞を獲得すれば、アカデミー賞の選考に失望するだけである。
◆『ワイルド〔仮題〕』のリース・ウィザースプーンは、『サンドラの週末』のマリオン・コティヤールのように、〝生地〟をストレートに出そうとする演技を披露する。その意味で、これまでのウィザースプーンとひと味違うことはたしかであるが、彼女でなければ演じられない演技ではない。ウィザースプーンよりも、母親役のローラ・ダーンのほうが演技の質が高い。そもそも、わたしには、実話にもとづくというこの映画に共感できるところが少ないので、批評の資格がない。母の病死や自分の男とのことなど、いろいろあったことで自分を(未経験のまま)厳しい自然環境にさらし、いじめる意味がわからない。いや、それは、一種の〝求道〟なんだろうから、わからないではないが、それをこういう形(平凡な記録的描写と安易なフラッシュバック)で映画にしても、面白くもなんともない。
(2015/01/27)
●助演男優賞: J・K・シモンズ [セッション]
◆『ジャッジ 裁かれる判事』には、ロバート・デュヴァル、ロバート・ダウニー・Jr、ビリー・ボブ・ソーントン、ビンセント・ドノフリオ、ベラ・ファーミガといった錚々たる俳優が登場する。そのなかでロバート・デュヴァルは、ロバート・ダウニー・Jrほかの面々が小粒に見えるほどの傑出した演技を見せる。が、これは、彼の偉大さを意味していると同時に、脚本と演出の貧しさを意味してもいる。結局は、息子(ロバート・ダウニー・Jr)と父(ロバート・デュヴァル)との復縁のドラマであるのに、中途半端な法廷劇を前面に出している。そもそも、ロバート・ダウニー・Jrがトイレでビンセント・ドノフリオに小便をひっかけたり、ダックス・シェパードがゲロを吐くシーンをストレートに映すような演出である。だから、にもかかわらずロバート・デュヴァルがこれだけの演技を見せたという点では、助演男優賞に値するが、積極的に彼を推すわけにはいかないのは、主演女優賞のところでも書いたように、彼が、メリル・ストリープやジュリアン・ムーアと同様に、もう、受賞のレベルを越えているからである。
◆『6才のボクが、大人になるまで。』のイーサン・ホークは、最高の演技をしながら、何も演技をしていないように見えるところが凄い。それは、リチャード・リンクレイターの演出のユニークのおかげである。ホークのこの〝自然〟な演技は、すでに、シナリオに忠実な演技をしながら、あたかもアドリブのように見える、同じ監督の『ビフォア』三部作でもはっきりと出ていた。だから、『6才のボクが、大人になるまで。』の彼の演技は、見事ではあるが、決して特別ではなく、助演男優賞には適さないとわたしは思う。しかし、選びやすさの度合は高いから、受賞の可能性は大である。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の演技に対してエドワート・ノートンに賞をあたえるのは、ノートンに失礼ではないか? これまでの彼の仕事への功労賞(アカデミー賞にはそういう係数はいつもあるが)という意味でなら別だが、彼がこの作品で見せているレベルの演技は、彼のほかの作品で何度も見せている。しかし、彼はいつ見てもいい男だ。ほれぼれする。
◆マーク・ラファロという俳優は、いつも〝運の悪い男〟を演じてきた。『フォックスキャッチャー』でも、チャニング・テイタムが演じるレスラーの善良な兄でありつづけながら、ジョン・デュポン(スティーブ・カレル)に意味なく殺されてしまうという〝運の悪い男〟を演じている。実在の有名レスラーにして名コーチ、デイヴ・シュルツのレスラーとしての体型をチャニング・テイタムにおとらずコンヴィンシングに自分の体に移し替えている(模倣ではない)。そろそろ彼に運をあたえたいものだ。
◆『セッション』のJ・K・シモンズの演技のどこがよいのだろうか? それは、俗受けするメソッド・アクティングの系列に属する凡庸な演技ではないか? もっとも、シモンズのおかげで、彼の生徒役のマイルズ・テラーは、その俳優キャリヤのなかのベストを演じることができたのでもあるから、シモンズは、サポーティング役としては評価されるべきなのかもしれない。が、ベストの助演とは言えない。
(2015/01/28)
●助演女優賞: パトリシア・アークエット[6才のボクが、大人になるまで。]
◆『6才のボクが、大人になるまで。』のパトリシア・アークエットは、この映画が撮影される12年間に、実際に離婚と再婚を複数回経験する。そうした〝実〟人生の変化と脚本上の年令的経過とが、主要な出演者すべてにおいてシームレスに(約14分を1年に振り当てている)連結した形で映像化されているのだが、この独特の演出設定をパトリシア・アークエットが傑出した形で活かしているかどうかはわからない。といよりも、この映画では、たとえばメリル・ストリープやジュリアン・ムーアのようなヴァーサタイルな俳優がその実力を発揮するような形での演技力はそれほど重要ではない。実在する時間に素直に乗れる(ある意味でミュージシャン的な)柔軟さと即興性を、いかにもドキュメンタリーっぽくではなく表現できることが要求される。こういう設定は俳優にとって決してやりやすい条件ではない。とすれば、最初から最後までこの条件を〝自然〟に演じているパトリシア・アークエットは凄いのだと言うべきなのだろう。
◆『きっと、星のせいじゃない。』で不治の病の娘の母親を演じたローラ・ダーンは、『ワイルド〔仮題〕』では、逆に、リース・ウィザースプーンが演じる娘の母親を演じている。年令的にはウィザースプーンより9歳しかちがわないダーンがずっと上の年令をコンヴィンシングに演じている。それは、十分評価できるのだが、ウィザースプーンの熱の入れ方(製作にも加わっている)にもかかららず、この作品が決して上出来とは言えず、ローラ・ダーンの役柄は、終始、回想のなかで登場することもあり、助演という視点では、アッピール度が低いように思う。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』のキーラ・ナイトレイは、なかなかよかった。『危険なメソッド』(2011)のときのような頑張り演技ではなく、もっと肩(と顎)の力を抜いて演技しているので、彼女のよさが出た。『はじまりのうた』(2013)では、まだ顎で頑張る(!)スタイルが残っているので、『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』での彼女の演技は一段向上したと言うことができる。が、助演女優賞には、若干弱いだろう。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の新しさは、フィジカルな意味での〝名優〟を重要ではなくした点にある。ここでは、カメラと音が俳優のフィジカルな演技を凌駕し、彼や彼女をヴァーチャルな地平に追いやる。だから、マイケル・キートンもエドワード・ノートンも エマ・ストーンもナオミ・ワッツも、撮影と音次第でどうにでもなるのであり、とりわけエマ・ストーンが目立つとすれば、それは、カメラと音とメイキャップに負っているといわざるをえない。そういう要素はこの映画にかぎらないとしても、それを意図的に強化しているのがこの映画なのだから、この作品を評価するのならば、俳優はある意味どうでもいいという点を考慮に入れなければならない。が、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』は、この問題を意識しながらも、主題にはしない。いわば、前ヴァ―チャリティ時代のレイモンド・カーヴァー/村上春樹流の〝オシャレな賢さ〟にとどめている。
◆『イントゥ・ザ・ウッズ』は、ブロードウェイ・ミュージカルの映画化だが、舞台の(おちゃらけの多い)〝アナログ志向〟に対して、映画はCGIを駆使して映画ドラマとしてメリハリのあるスタイルになっている。が、それならば、ミュージカルスタイルとはきっぱり縁を切ればよかったのだが、そうしていない分、矛盾が露呈した。候補のメリル・ストリープの場合、その実力は余すところなく発揮され、ダントツのオーラを放っているが、それは映画ドラマの登場人物としてであって、ミュージカルのパフォーマーとしてではない。魔女の演技は見事でも、ミュージカルの歌唱力では見劣りがする。それはいたしかたない。が、この屈折を見落としてはならない。そのため、この作品でのストリープの映画ドラマ的な側面だけを評価して持ち上げるのは、まちがっている。
◆作品のなかで占める演技の比重(つまりは目立ち度)の大きさを重視するならば、メリル・ストリープとパトリシア・アークエットの二人が残るが、アークエットは、フェミニズムや女性の自立といったこの30年間のアメリカの支配的風潮にもかかわらず、家庭という場のなかでは所詮、男は男であるという現実に苦悩する女/主婦を自然体で演じている点で、一般受けがする。全体として、今年の助演女優賞候補は、とびぬけた候補がいないので、こうした一般受けの空気のなかでアークエットがウィナーになる公算が強い。
(2015/01/30)
●監督賞: アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ [バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)]
◆『フォックスキャッチャー』でベネット・ミラーは、スティーブ・カレル、チャニング・テイタム、マーク・ラファロ、バネッサ・レッドグレーブの既存の演技を一変させた。とりわけ、スティーヴ・カレルの場合は、この作品への出演が彼の演技キャリアを決定的に高めたと言える。出演者をここまで変革した点で、ミラーは、5人の監督のなかでとびぬけている。
◆リチャード・リンクレイターは、独自の演出法を全面展開した。自然時間を映画の時間のなかに取り込むこと。俳優の身体時間と演技による仮想時間とのあいだにある独特のリアリティへの注目。サラ・ポーリーの『物語私たち』のような、ドキュメンタリー的な方式へのナルシスティックななれあいではなく、むしろ、厳密な脚本にもとづく演技によって、既存のドキュメンタリーの惰性を異化すること。そうした点では、リンクレイターは、新しい映画表現を提出した。
◆リンクレイターがめざしたのは、「真実」の記録ではない。短いぶつ切れの時間であれ、リアルタイムで流れる時間に観客を居合わせるということを仕掛けたのである。「真実」ということで言えば、たとえば、あるマニアックな観察者によると、オリヴィア(パトリシア・アークエット)と〝ダッド〟(イーサン・ホーク)とのカップルから生まれた娘ということになっているサマンサ(ローレライ・リンクレイター)の目は茶色をしているが、ともに青い目の両親から茶色の目の子供が生まれる確率は非常に低いという。が、映画は、そういう〝奇跡〟が起こったとして見るところから始動する。
◆『グランド・ブダペスト・ホテル』のウェス・アンダーソンに関しては、他所で書いた〝絶賛〟の文章を引用する → これは、現時点でのウェス・アンダーソンの最高傑作である。ここでは、やれステファン・ツヴァイクの『昨日の世界』にインスパイアーされたとか、エルンスト・ルビッチのトーンで撮っているとか、いまはなきハンガリー・オーストリア帝国と古きヨーロッパの香りがただようなどといった、教養主義的な解説がむなしい。そんなものは捨ててまず見るべし。いま、かつてマイナスイメージで見られてきたヒキコモリがあたりまえの時代になりつつある。ティム・バートンには旧ヒキコモリの否定的な雰囲気があるが、アンダーソンの場合、〝閉所恐怖症的〟な意識で狭い空間をどんどん奥に掘り込んで行けばいくほど、ハッピーで躍動的な世界が展開する。が、その〝開放性〟は物語中の物語やフラッシュバックのなかのフラッシュバックといった形で内側に織り込まれている。キャスティングも絶妙だ。ホテルのコンシェルジュ役がレイフ・ファインズとはすぐにはわからないとか、アンダーソン映画ではおなじみのビル・マーレイやエドワード・ノートンはむろんのこと、〝裸〟になるのが好きなハーヴェイ・カイテル、〝凶悪〟がうまいウィレム・デフォー、〝小心者〟に見えやすいマチュー・アマルリック等々、姿をあらわした瞬間、他の出演作を思い出させ、ニンマリさせるサービスもある。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』のモルテン・ティルドゥムの仕事は、スクリーンで見たものでは『ヘッドハンター』(2011)しか知らないが、テレビ的なサスペンス(と映画の場合はちょっぴり血なまぐさいシーンを好む)クライム・ムーヴィー系という印象を持っていた。その人間関係は、〝ゲーム〟的な陰謀と狡知によって組み立てられており、映画はその謎を明かすプロセスになっている。これに対して、『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』では、もっと時代的な係数(同性愛差別、軍事機密など)がからんでくる。とはいえ、それがテレビ的な(どのみち完結した)世界におさまってはいないという点で、ティルドゥムの演出は、奥行を増したと言える。が、アラン・チューリングという実在の人物の心の闇に迫るところまでは行っておらず、物足りなさが残る。
◆アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの作品は、『アレハンドロ・ゴンサレス』(1999)以来すべて見ているが、『アモーレス・ペロス』(1999)から、『21グラム』、『バベル』、『BIUTIFUL ビューティフル』(2010)とくだるにつれて、べとべとした身体性とうさんくさい街の強度が弱まってくる。それが、今回の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』になると、冒頭でマイケル・キートンが麻原彰晃的な〝空中遊泳〟を見せるように、バードマンをはじめとしてその身体は空虚である。空虚という言い方が誤解をまねくとしたら、身体性がゼロ度に設定されていると言おう。とにかく、イニャリトゥの過去の作品とは決定的な転換である。もともと彼は、メキシコの内部と外部とを区別している。また、『11'09''01 セプテンバー11』(2002)のメキシコのセグメントでは、画面(つまり身体性の強度を示す尺度)は、暗転から、わずかに「神の光は我々に道を示すのか、それとも目をくらませるのか」というアラビア文字と英語の文字だけをはさみ、まぶしい白色に昇華する画面だけを見せた。この場合、身体的要素は音と音楽であったが、これは、ある意味で、映画における身体性のヴァーチャル化である。言い換えれば、イニャリトゥは、911のアメリカに身体性の極限地平を見たのであり、彼がアメリカを描くとすれば、メキシコを描いたときの生々しい身体性は退けられるということである。が、こうした身体性の変化は、911からはじまったのではなくて、電子テクノロジーの高度化とともにはじまり、遅くとも1980年代には社会と文化を変え始めていた。911は、むしろ、その帰結の1つにすぎない。そして、このような身体性の変容とヴァ―チャリティの亢進から、スパイク・ジョーンズの『her 世界でひとつの彼女』(2013)のような、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』などよりもはるかにメディア論的にポイントをついた作品が生まれたのだった。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』で不満なのは、登場人物の身体性のレベルでヴァーチャル化を意識しながらも、それを徹底させることができない(イニャリトゥはメキシコを捨てることができない)点である。それを補完するためにここでは、シームレスに動くカメラとたえずなり続ける音の身体性を活用する。それは、それでセンシュアルで、この作品の魅力の1つになっているのだが、とりかかったヴァ―チャリティへの切込みとしては、不徹底と言わざるをえない。〝おいおい俺はそんなことを目指しているんじゃないよ〟とイニャリトゥは言うかもしれないが、ならば、彼は、メキシコの身体と街に執着した作品を作りつづけるべきだ。
◆今回、『フォックスキャッチャー』のベネット・ミラーを評価するのは、彼が一貫してアメリカにおける〝父親の不在〟を追及し、それが、この作品において、アメリカという国家の矛盾(戦争、家庭、結婚、資本の蓄積と継承など)の根源に迫るところまで来たからだ。ミラーの最初期の作品『The Cruise』(1998)は、マンハッタンのダウンタウンを回遊する遊覧バスのガイドにして詩人というか自由人のティモシー・〝スピード〟・レヴィッチ(Timothy 'Speed' Levitch)のノマド的・フラヌール的日常を映す。彼は、ゲイ・アクセントの独特の英語で、自分は五体満足な両親の〝機能不全児〟(dysfunctional child)だと言うが、マンハッタンのカオス的な多様性のなかで幸せそうである。が、面白いのは、彼が、いまは亡きワールド・トレイド・センターの広場に寝そべり、この街に住むことの満足感をあらわしているシーンで、彼を庇護するように見下ろすWTCのふたつのタワーの姿である。つまり、彼は、この街で、生物学的な父と母から(ゲイとして)離脱することによって幸せのなかにいるが、彼は、WTCのシンボリックな〝母〟と〝父〟とに守られていたのである。911がそうしたオイディプス父母の死の日とみなすならば、『The Cruise』は、1970年代から90年代いっぱいまでのマンハッタンでつかのま続いた、父親を持たず、生物学的にも文化的にも父親にはならないことによって自由である〝ゲイ〟的ライフスタイルのひとつの形を表現していた。
◆ベネット・ミラーの映画には、生物学的父親は不在でも(不在なるがゆえに)その存在を補完するヴァーチャルな父親が登場する。『マネーボール』でジョナ・ヒルが演じたデータオタクのピーターにとって、ブラッド・ピットが演じるビリー・ビーンはそうした〝父親〟の機能を果たしていた。『カポーティ』(2005)は、父親から〝離脱〟しているはずのカポーティ(フィリップ・シーモア=ホフマン)が、にもかかわらず、収監され、死刑宣告を受ける男たちにヴァーチャルな〝父性愛〟をいだいてしまう不幸を描いている。それは、ママ・パパ・ミーのオイデプス的ファミリーの象徴的ないしはレジティマシー的存在として機能したワールド・トレード・センターが、2001年9月11日に消滅したあとも、亡霊のようにたちあらわれる〝父親の不在〟の補完現象の矛盾である。ミラーは、この矛盾を、『フォックスキャッチャー』においては、アメリカが振り払うことができない戦争とのしがらみをあらわにさせるところまで行く。アメリカの主要な軍需産業をになってきたデュポン家の嫡子ジョン・デュポン(スティーブ・カレル)は、父親から離脱すればするほど母親(バネッサ・レッドグレーブ)の支配から逃れられない。そして、彼が、強引に子飼いにしたレスラーたちのヴァーチャルな〝父親〟になろうとする願望は、はかなく潰える。これは、単にデュポン家の矛盾ではなく、アメリカそのものの矛盾である。
(2015/02/01)
●脚本賞: バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) [アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、 ニコラス・ヒアコボーネ、アレクサンダー・ディネラリス・Jr.、アルマンド・ボー]
◆日本語で〝脚本賞〟というのは、"Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen"のことである。つまり映画のために書き下ろされたオリジナルのスクリプトである。とすると、『6才のボクが、大人になるまで。』は、脚本という概念を大幅に変えたという意味で優位に立つ。完成した脚本は最終段階でしか存在しない予定表のような脚本。が、短期間に作る映画でも、毎日のように小出しに出てくる脚本もあるから、これが脚本ではないとは言えない。
◆脚本そのものの機能と意味のユニークさを取るのではなく、映画の設計図としての脚本の完成度を問題にするならば、『グランド・ブダペスト・ホテル』と『フォックス・キャッチャー』が『ナイトクローラー〔仮題〕』を凌駕するが、華麗さの点で『グランド・ブダペスト・ホテル』が優位に立つだろう。
◆ゴールデングローブの脚本賞では『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』が受賞したが、どうだろう? この作品は、脚本よりもカメラと音・音楽が優っているのではないか? が、カメラを動かすのは脚本だから、この作品世界の流れるような動きは脚本が設定したものだと言えるのか?
◆台詞の多声性(ポリフォニー)という点では、たしかに『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』は一番ヴァラエティに富んでいるかもしれない。映画のなかで、台詞が多元化するようにつくられている。相手をなじっても、ヒステリーを起こしても、それは二重・三重化されていたりする。が、それは、演技という平面では一重なのだ。つまり脚本としては多彩でブリリアントな記述になっているが、脚本そのものは安定した一重の次元のうえに安らっている。
(2015/02/02)
●脚色賞: イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密 [グラハム・ムーア]
Pynchon
◆脚色賞の候補で一番意見がわかれるのが『インヒアレント・ヴァイス』(Inherent Vice)だろう。トマス・ピンチョンの同名の小説(邦題『LAヴァイス』の〝本格的な最初の映画化〟だという。が、ピンチョンの原作は、〝ハイパーテクススト〟だと思うわたしは、よほど大胆に組み替えないと、原作の映画化にはならないだろうと思っているので、原作の表層を映像とキャラクターによって、そのムードを繊細に選択された音楽によって引き継ごうとしたポール・トーマス・アンダーソンの脚色と演出をあまり高くは評価できない。
◆『インヒアレント・ヴァイス』のなかごろで、ジョシュ・ブローリンが、怒ったような表情で〝チョト、イチロ、モト、パンケーク〟といきなりわけのわからない言葉を発するので、何かと思ったら、それは、原作で〝Chotto, Kenichiro! Dozo, motto panukeiku〟と書かれている個所をほぼ忠実に使ったのであった。原文が片言の日本語なのだが、アンダーソンは、一応原テキストに忠実な姿勢を取っているわけだ。が、これは、逆に言うと、原作を〝ハイパーテクススト〟として組み替えるほどの大胆な脚色はしていないということである。
◆原作には、ニクソンの情報コントロールや、やがて全般化するネットワーク化と情報資本主義化でアメリカ社会が大きく変貌する予感が描かれている。原作は2009年に刊行されたのだから、ピンチョンは、インターネットを十分意識してこの小説を書いたはずであり、実際、インターネットの前身であるARPANETやコンピュータのネットワーク化への言及が少なからずある。
◆ピンチョンの世界からメディア・テクノロジーの問題を無視してしまうと、残るのは、パラノイアである。映画『インヒアレント・ヴァイス』で、フォアキン・フェニックスが演じるドク (Doc) は、終始、陰謀パラノイアに陥っている。彼のパラノイアは、増殖するネットワーク(警察、FBI、CIA、ゴールデン・トライアングルのマフィアコネクション、コンピュータによる情報コネクションなど、すべてが複雑に関係づけられ、全体化しているネットワーク)によって亢進するのだが、映画のやりかただと、それがわからない。これでは、ベニチオ・デル・トロやオーウェン・ウイルソンがフェニックスにひそひそ声で語る思わせぶりなことが操作的な情報ではなくて、身体的な〝事実〟になってしまって、ピンチョンの世界をえらく古めかしいものにしてしまう。
◆トマス・ピンチョンを創造的に理解すると、ドクがいつもマリファナを吸っているのは、いわば、そうしたネットワーク化への予防措置/防御である。が、原作は、そういうことがとりあえず可能だった時代が、60年代後半から1970年までを最後に終わったと考える。映画も、たしかに、その点はおさえており、だから、最後のほうで、ビッグフットが皿のうえに乗ったマリファナの葉っぱを全部口に入れてしまうようにしているのだ。つまりマリファナは終わりというわけだ。しかし、これでは、ピンチョンの原作の広大かつ深遠な含蓄はほとんど表現できない。
◆『アメリカン・スナイパー』は、映画の主人公でもあるクリス・カイルと、スコット・マックユーエン、ジェイムズ・デフィリス (Chris Kyle, Scott McEwen, James Defelice)の共著という形で出た『American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History』(2013) を脚色したものであるが、原作には、映画のような、人を殺すことに対する繊細な迷いや逡巡は希薄である。ありていには、愛国主義者を喜ばせるような武勇伝になっている。だから、映画化に際してジェイソン・ホールが脚色したスクリプトは、原作の奥行をぐんと押し広げることに成功しているのがわかる。
◆『セッション』の監督・脚本のデイミアン・チャゼルは、『グランドピアノ 狙われた黒鍵』(2013) の脚本も書いている。両者に共通するのは、映画世界のゲーム性である。その〝外部〟は、あくまでも映画のなかの出来事を印象づけるためであって、特になくてもよいのである。『セッション』の場合、プロのドラマーをめざすアンドリュー(マイルズ・テラー)がなぜあんなにマゾキスティックなのか、また、フレッチャー(J・K・シモンズ)のあの攻撃性と自信過剰がどこから来るのか、はどうでもよい。むろん、エンターテインメントとしてはよく組み立てられており、内在的に完成されていればよしとする批評基準からすれば、うまく出来ている。しかし、わたしは、映画にはつねに〝外部〟地平への露出の〝破綻〟が必要だと思うので、この作品は取らない。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』と『博士と彼女のセオリー』、とりわけ後者の脚本としての要素からは、既存の感覚や知を揺さぶられ、自分の平衡感覚を疑ったり、既存の思い込みを考え直したりする経験はほとんどえられなかった。
◆『インヒアレント・ヴァイス』のピンチョンへのチャレンジと選曲と音への繊細さは評価できるが、《商業映画であるにもかかわらずそこを逸脱する》機能をポジティヴに発揮している作品を優先したいと思うと、『アメリカン・スナイパー』に落ち着く。
(2015/02/04)
●長編アニメ映画賞: ベイマックス
◆候補に挙がった5作品のうち、『ザ・ボックス・トロールズ〔仮題〕』、『ベイマックス』、『ヒックとドラゴン2』は、いわば〝アメリカン〟なイマ様アニメであり、『ソング・オブ・ザ・シー〔仮題〕』と『かぐや姫の物語』は、古典アニメの素朴さとある種〝エキゾチック〟な雰囲気をただよわせるアニメである。前3者のうち、いちばんゲーム的なサスペンスをねらっているのが『ヒックとドラゴン2』で、これは、第1作の『ヒックとドラゴン』(2010)とくらべると格段にその度合が強く、わたしには、第1作のほうがよかった。が、2011年のアカデミーで候補にはなっても、受賞はできなかった。今回、ゴールデングローブ賞で『ヒックとドラゴン2』が受賞したことを合わせて考えると、アメリカでは、〝1〟よりも〝2〟のようなサスペンス性の度合の強いものが評価されるように思う。だから、また、『ヒックとドラゴン2』がアカデミーでも賞を取ってしまう可能性は高いのである。
◆大人向きのアニメとしては、『ザ・ボックス・トロールズ〔仮題〕』が社会的なアイロニーに富んでいて、奥行がある。マンホールの下の地下に住み、胴体を段ボール箱でおおっているボックストロールたちは、社会のなかで差別され、パブリックな場面から押しのけられている層である。チーズ橋に象徴されるこの町の上層階級は、チーズを愛食する。ここには、乳牛に多分の残酷さを強いるチーズ生産へのヴェジタリアン的批判が込められているような気がする。ただし、この上流階級に対して謀反を起こすスナッチャー(声:ベン・キングスレー)は、最底辺のボックストールの味方ではない。逆に、彼は、ボックストールの殲滅(ホロコースト)を狙っている。このへん、いまの状況との符合がある。スナッチャーを原理主義的な〝テロリスト〟、ボックストールをその〝暴虐〟による難民に置き換えると、このアニメの世界は、いま世界で起こっている事態に符合する。が、このアニメは、この問題に対してラディカルな解決策を提示することはない。上流階級のトップに鎮座するPortley-Rind卿の破格の娘ウィニー(声:エレ・ファニング)が媒介者になり、ボックストールと人間との媒介者であるエッグス(声:アイザック・H・ライト)と助け合って、スナッチャー一味を倒すのだから、いかにも君主制万歳の結末である。
◆『ベイマックス』は、その点、もっと〝平等主義的〟である。冒頭、それぞれのロボットで戦う賭競技のシーンから始まるように、機会均等が許されている。そして、このアニメは、そういう機会均等と平等が侵されことにヒロ(声:ライアン・ポッター)が闘う物語である。実写に近い色気のある映像でロボティクスやAV(拡張現実)の先端的環境を見せかけではなく取り込み、わくわくさせる。そういう鋭利な現実性のなかに、ベイマックスのとろ~んとしたオブジェが加わるくとによって、味わいが深くなった。ヒロが作ったロボットは〝Microbot〟というが、この〝マイクロ〟は、ナノテクノロジーの微小さを意味すると同時に、そのひとつひとつの単位がそれぞれに自律しているというオブジェクト指向的なモジュール性を含意してもいる。実際、〝Microbot〟は、無数に組み合わさることによっていかなる形態のオブジェにもなりえる。したがって、それを旧時代のマシーン・テクノロジーの統合的・中央集権的な方向で用いるのは逆行だが、ヒロの闘いは、テクノロジーのラディカルな側面を逆行させて現状の維持と後退にのみ使おうとする統合権力を倒し、それぞれに自律的な世界を取りもどすことである。
◆『ヒックとドラゴン2』は、2011年の第83回アカデミー賞でノミネートされた『ヒックとドラゴン』(2010)の名前 (How to Train Your Dragon) を引き継いでいるが、両者のあいだには途方もない距離がある。ほとんど別物といってもよい。『ヒックとドラゴン』は、バイキングのボスである好戦的な父親になじめないヒキコモリ系のヒッカップ(ヒック)が人間の敵とされていたドラゴンと仲良くなる話であった。このドラゴン、トゥースレス(トゥース)もまたヒキコモリ系で、ヒキコモリ時代のヒキコモリのコミュニケーションを描いていて、時代的リアリティがあった。一面でヒッカップは、父親の世界に順応し、〝立派〟な兵士に成長するかに見えるが、他面で、彼は、父親のように腕っぷしをふるうのではなく、いわば〝セラピューティック〟(治療的)な方法でドラゴンを調教し、味方につけてしまう術を身に着ける。これは、必ずしも反戦ではなく、武器が腕っぷしではなくて、頭であり、それだけ父親より新しいというだけのことなのだが、そのへんの屈折が面白いのだった。
◆『ヒックとドラゴン2』では、ドラゴンはもはや人間の敵ではなく、人間が自由にあやつって使う乗り物かペットのような存在になっている。ヒカップとガールフレンドのアスティは、自分のドラゴンを乗り回して、カーレースのようなことをやっている。当然、闘うというテーマは『ヒックとドラゴン』よりもはるかに強調されており、"War on Terror"のプロパガンダではないかと思えるほどである。敵は人間(ドラゴ)であり、ドラゴンを魔術的な方法で支配し、世界をわがものにしようとする。ヒカップと父(そして死んだはずの母も)はこの敵と戦うことになる。最初、ヒカップは非暴力による平和が可能だと主張するが、父は受け付けない。〝理由なくひとを殺す奴には道理など通らない〟という彼のせりふは、中東で人質が殺されるときにもよく言われる。
◆しかし、『ヒックとドラゴン2』は、国家が戦争をどうとらえ、ひとびとにどう納得させようとするかを教える。戦争がファミリーを引き裂くのは事実であるが、国家なり権力組織が戦争を遂行するとき、ファミリーの再編という方法を取る。この映画でも、一度離れ離れになった息子と母が再会し、戦いのためにファミリーを再結束しようとする。ファミリーと国家とは別ものであるはずだが、ファミリーが国家のために再結束することによってしかファミリーでありえないといのは不幸である。が、そういうファミリーは、(日本の戦前戦中の家族の型がが戦後崩壊するように)戦争が終われば意味をなさなくなる。アメリカ映画は、そういうファミリーの崩壊をくりかえし描いてきたが、ひとつのパターンは、父の死のあとに息子が結婚して新しいファミリーを作り、ファミリーの型を維持するというものである。おそらく、その新しいファミリーもまた、戦争のためにその成員を失うであろう。ファミリーが継承されるのは、ファミリーのためであって、国家のためではないのだが、うわべは〝お国のために〟ファミリーがあるかのように進んでいく。『ヒックとドラゴン2』が、直接こんなことを考えさせてくれるわけではないが、わたしがそんなことを考えたのだから、同じように考えるひともいるだろう。いずれにしても、アメリカのホームランド・セキュリティには役立つ作品である。
◆『ソング・オブ・ザ・シー〔仮題〕』は、2月7日現在、まだ見ていないが、トレイラーによると、絵柄は前作の『The Secret of Kells』(2009)によく似ている。〝アメリカン〟な3作とは全然違うし、『かぐや姫の物語』よりももっと様式化されている。画面の動きは速く、静的ななかに激しい動きがある。とりわけ、映像に鋭くシンクロした音の入れ方が繊細かつダイナミックで、この点では他の4作品を寄せつけない。もし賞の撰者のなかで〝アメリカン〟なアニメでない方向への関心が高まれば、『ソング・オブ・ザ・シー〔仮題〕』か『かぐや姫の物語』かに絞り込まれるはずだが、様式化の徹底性という点では、『ソング・オブ・ザ・シー〔仮題〕』が勝つだろう。
◆『かぐや姫の物語』は、わたしがジブリアニメを好きでないという点は括弧に入れるとしても、かぐや姫にまつわるおびただしい伝説を折衷主義的にまとめているのがつまらなかった。最終シーンでかぐや姫を迎えにくる使者の長らしき存在が、長谷観音のような風貌の釈迦なのには、唖然とした。この伝説の由来に関しては、東アジア説と国内説とがあり、結論は出ていないから、かぐや姫が宇宙人であってもよいのだが、どうせ迎えにくるのなら、釈迦よりも宇宙人のほうがよかった。また、かぐや姫の物語は、本来、『竹取物語』であり、主人公は、竹取翁である。つまり、この物語でかぐや姫は、竹取翁の願望の対象であって、全体は、竹を取ってつつましい生活をするしかなかった〝翁〟(といっても高齢者とはかぎらない)が、聖なるものにあこがれる〝神婚説話〟の変形であったという解釈もある(伊藤清司『かぐや姫の誕生』、講談社)。ちなみに、〝神婚説話〟は、いまの時代にも生きている。若い女を〝かぐや姫〟とみなし、追いかける老人はいくらでもいる。たいていは、女はそのような老人を振って、若い男のもとに走るのだが、そうはならずに、老人と若い男とのはざまでこの女が、月でも尼寺でも、娑婆を超絶した世界に行ってしまうというような稀なことが起きれば、伝説が始まるのである。日本でなじみの物語を映像化するのなら、もうちょっとひねった想像力がほしかった。
(2015/02/07)
●外国映画賞: イーダ
◆『タンジェリンズ〔仮題〕』は、グルジアの黒海側のエリアのアブハジアでグルジアから独立を求めたアブハジア紛争(1992~93)の出来事を描いている。エストニアから移民してきた主人公イヴォ Ivoは、紛争が勃発しても、家族を故郷に返したのち、近くでオレンジ(原題のTangelinesの意味)を栽培する同郷の友人Margusのために木箱を作っている。ほとんど人の姿を見かけないこの地域にも、ときおり銃を持った兵士が車でやってくる。グルジア内では、ロシア人対チェチェン人との対立があるが、ここでは、チェチェン人は多数派で、移民者を含めたアブハジア人と対立している。ある日、イヴォの家のそばで、両派の銃撃戦が起こり、イヴォとマルガスは一人のチェチェン人と重症の若いコーカサス人を助ける。イヴォの家で療養することになった敵同士の二人の関係は険悪だが、イヴァンは、この家のなかで殺し合いは許さないと二人に言い渡す。つかの間、民族対立をこえた時間が流れるが、それは続かない。村のなかのつつましい生活描写、静けさのなかで突如起こる銃撃戦の鋭い描き方と音採り、決して政治の講釈を披露したりはしないが民族融和の悲しいまでの難しさをつきつけるリアリティ。ダレのない重厚な演技と映像が胸を打つ。
◆『イーダ』については、他所で詳述したので、そのリンクを読んでほしいが、この作品は、ポーランドにおけるユダヤ人問題を歴史的事実を追うだけでなく、映画史的な記憶への鋭い参照を行ないながら、それが新たな美学を構築しているところがすばらしい。アルゼンチンの『ワイルド・テイルズ〔仮題〕』(Relatos salvajes/Wild Tales/2014/Damián Szifrón)とモーリタニアの『ティムブクツ〔仮題〕』(Timbukutu/2014/Abderrahmane Sissako)は、2月8日現在、まだ見ていないのだが、『イーダ』のような作品はそうめったにあらわれないから、これをベストとしたい。
◆『リヴァイアサン〔仮題〕』は、『ヴェラの祈り』(The Banishment/2007)や『エレナの惑い』(Elena/2011)につづくアンドレイ・ズビャギンツェフ監督の新作で、Rotten Tomatoesで99%、iMDbで7.9という高得点を獲っている作品である。フィリップ・グラスの音楽とともに見えるのは、フィンランドに近いロシア領ムルマンスクの内海の波のしぶきと荒寥とした寒村である。次第に明らかになるのは、市長が、警察、裁判所、教会を支配して家父長的な欲望をほしいままにするという一時代まえの社会派の告発映画が取り上げたような世界である。ある意味では、プーチンの支配するロシアの辺境地帯では、いまでもこういう非道な支配者がはびこっているという意味にもとれるが、決してそれだけではない。市長の事務所にはプーチンの肖像がかかっており、冒頭、「現在」という時代設定が示されるから、いまの時代の出来事が描かれていることはたしかだ。むしろ、前近代に舞い戻ったような状況の不可解さこそが、いまのロシアの状況なのだと思う。
◆家を追い出そうとしている市長と闘っているKolya( アメリカ アレクセイ・セレブリャコフ Aleksey Serebryakov)は、延々と判決文を読むだけの裁判(旧ソ連から引き継いだ超官僚的なやり口のシーンがすごい)、市長の恫喝、妻の突然の死と、次第に追い詰められ、みずからもウォトカに溺れていく。抑圧は外からと内から来る。結局は、殺すしかないような悪党の存在が中心にあるのだが、それが、復活した宗教と入れ子構造になってロシア全土をおおっていて、誰も抜け出ることができない――なぜならそのなかの個々人もその入れ子構造に加担しているから――というような状況があるようだ。市長とロシア正教の司祭との関係も、一方が他方を支配するという関係ではない。市長は司祭を立てるが、司祭はその信仰に生きているかのようだ。原題のLeviafanは、旧約聖書・ヨブ記、第41章の海中怪物レヴィアタン(リヴァイアサン)に関係がある。ウォトカに酔ったKolyaに向かって司祭が、その一節を語るシーンがある。《あなたは釣り糸でリヴァイアサンを釣り出すことができるか? 糸でその舌を押さえることができるか?》《地の上にはこれと並ぶものなく、これは恐れのない者に造られた。》《これはすべての高き者をさげすみ、すべての誇り高ぶる者の王である》。つまり、宗教的な祈りは、現状をただ肯定し、恐れおののく弱者だけが耐えなければならないことを無条件に受け入れさせる装置になっているが、それを壊すこともできない。
◆『リヴァイアサン〔仮題〕』の世界は、形なりとも〝民主主義的〟な手続きが尊重される社会から前時代に逆戻りした世界ではなく、むしろ、今後の社会を示唆しているかもしれない。現実を動かすためには戦争しかなく、その戦争はさらなる戦争を生む。しかも、その戦争は内戦からさらに小規模の殺戮行為を生む。これでは、ひとは、自力で戦力を蓄えるしかなくなる。が、自力の〝戦士〟は、大規模な軍の予備軍となる。非戦士は、難民として流浪の民となり、拡散する。戦士しかいない世界とは、この映画の最初と最後に映されるムルマンスクの内海の荒寥とした風景そのものである。
◆とりあえず、わたしは『イーダ』を受賞作に選んだが、以上のように、他の2作品もなかなかパワフルである。
(2015/02/09)
●撮影賞: バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡) [エマニュエル・ルベツキ]
◆撮影に関しては知ったようなことを言いたくない。現場のプロによると、〝映画評論家〟が〝キャメラ〟がどうのこうのと言うときは、ほとんどがデタラメだという。おそらくそうなのだろう。が、このことは、アカデミーの撮影賞は撮影のプロにしか選べないということではない。〝キャメラ〟がどうのこうのと言うことがくだらないのは、それが現場のプロの発言でもそうだからである。それは、映画という表現形態の技術的な要素から来る問題でもある。映画製作には多次元の要素が加わっており、〝キャメラ〟という言い方で含意されている〝製作の特権的な中心〟などに位置することがそもそも不可能な表現形態なのである。カフカ以来(と芸もなく言わせてもらえば)小説で〝作者〟とか〝主人公〟とかいう概念がもはや特権的な位置を占められなくなった以上に、映画においては、もはや〝キャメラ〟などという一点集約的な観念ですべてを語ることはできないのだ。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』は、撮影監督のエマニュエル・ルベツキの存在が過剰なくらい大きな作品であるように見える。彼がいなかったら絶対にこういう作品には仕上がらなかっただろう、と。全体がワン・ロング・テイクのような撮り方になっていることがよく指摘される。しかし、ルベツキ自身は、シングルショットで撮ることを売りにはしない。『トゥモロー・ワールド』(2006)に関して、クライヴ・オーウェン、ジュリアン・ムーアらがキウェテル・イジョフォーの運転で逃げる車のシーンが、ノーカットのワン・ショットで撮られていることに観客が気づいたことにガッカリしたという。彼は、できるだけ自然に撮りたいのであり、トリックがわかる場合は撮り方を変えるのだという。これは、『ゼロ・グラビティ』(2013)に関しても、〝最初の17分間のワン・テイクはすばらしい〟といった賞賛が彼には意味がないことを示唆する。ルベツキによれば、『トゥモロー・ワールド』の車のシーンでも、車をグリーン・スクリーンで囲んで映像を合成したってよかったのだが、そうしないで動く車のワン・テイクで撮ったのは、そのほうが生き生きとした画面になるからだと言う。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の場合も、重要なのは、その撮り方の技術ではなくて、マイケル・キートンが〝游体離脱〟して自分や他者を流動的な距離をおきながら眺めているような映像を生み出した点である。しかし、これは、VRやAR〔拡張現実〕やSR〔代替現実〕のいまの技術の世界では全然めずらしいものではない〔→解説映像参照〕。映画の撮影は、クリストファー・ノーランもアルフォンソ・キュアロンも、このへんの技術を積極的に取り込んでいるのであり、ここでは、〝キャメラ〟がどうのいう撮影論は意味をなさなくなっている。
◆こういう観点に立つと、他の4作品は、非常に〝古典的〟な(つまり〝キャメラ〟が云々の映画評がまだ有効な)撮り方をしているように見える。実際、『アンブロークン〔仮題〕』のロジャー・ディーキンス(1949 ~)、『グランド・ブダペスト・ホテル』のロバート・D・イェーマン(1951~)、『ターナー、光に愛を求めて』のディック・ポープ(1947~)は、みな巨匠であり、すでに多くの〝名作〟を担当してきた撮影監督である。古典的な巨匠らしく、彼らはその〝キャメラ〟の存在を意識させない。『グランド・ブダペスト・ホテル』は、その色彩もスペクタクルな構図もマスターピースの域に達している。『ターナー、光に愛を求めて』は、画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの作品の色調を映像に取り込むチャレンジを試みており、その職人芸には憎いまでである。『アンブロークン〔仮題〕』は、捕虜に屈折した暴力をふるう捕虜収容所の上官を演じるMiyabi(石原貴雅)のパンキーな演技をフォローしつくせていない不満が残る。彼の演技は、暴力とエロティシズムとの境界線を越えるファシズムの美学に迫りそうな名演だが、それを余すところなく表現するにはカメラが(いや〝キャメラが)〟古すぎるかもしれない。)なお、この映画は、日本公開での〝反発〟に過剰な気配りをしているのか、積極的な広報を控えている気配がする。毎度のことながら残念である)。
◆その点で『イーダ』は、これら3作とは異なる撮影監督によって撮られている。若いウカシュ・ジャル(1981~)とベテランのリシャルト・レンチェフスキー(1948~)は、古典的な撮影技法を完璧に意識しながら、それをデジタルで撮り、破綻を見せないという新しい〝手作り〟技法を披露する。これは、なかなかの快挙であり、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の対極に位置する。その点で、両作品は、撮影という概念に関して評者がどういう観点に立つかによって競合せざるをえない。わたしも大いに迷うが、ウカシュ・ジャルの若さとその作品のほれぼれする美しい映像を評価して、『イーダ』を採ろうと思う。『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の撮影技術は、今後もっともっと発展するほずだからでもある。
(2015/02/11)
●編集賞: セッション [トム・クロス]
◆これまで編集賞を受賞した作品で、作品はダメだが編集だけはよいというような作品はあったのだろうか? 通常は、編集がダメで作品はいいということはなく、アカデミー賞でも、作品賞にノミネートされる作品は編集賞とダブることが多い。今年の場合は、候補の5作品がすべて作品賞の候補にもなっている。その点で、作品賞にノミネートされている『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』が編集賞にノミネートされていないのが気になる。一説では、この作品は、"one whole tracking shot"で撮られているので、多くのカットのある作品を好む編集賞の対象にはならず、だからこそ、作品賞に輝く可能性も高いのだという。まるで編集賞の候補にして落ちたら、作品賞をあたえにくいのでわざとはずしたみたいな話である。まあ、そんな経緯で作品賞が『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』に行く可能性もないではない。
◆そういう儀式的な選別が行われるとすれば、『6才のボクが、大人になるまで。』と『アメリカン・スナイパー』も有力候補である。それにともなって、作品賞も、『6才のボクが、大人になるまで。』が取ってゴールデングローブ賞と変わり映えのしない結果になるか、あるいは、『アメリカン・スナイパー』が取って、ちょっと雰囲気を変えるという結果になるかのどちらかであるということになる。もしそうなら、後者のほうが面白い。
◆『6才のボクが、大人になるまで。』のエディターのサンドラ・エイデアー(1952~)は、リチャード・リンクレイターの主要作品、『ビフォア・ミッドナイト』(2013)、『バーニー みんなが愛した殺人者』(2011)、『ビフォア・サンセット』、『恋人までの距離(ディスタンス)』(1995)、『ウェイキング・ライフ』(2001)を編集してきた。リンクレイターの映画の集大成的な要素のある『6才のボクが、大人になるまで。』が編集賞を獲れば、リンクレイターへの彼女の長期の貢献が報いられたことになる。だから、作品賞とは切り離して彼女に賞をあたえるほうがよいだろう。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』のウィリアム・ゴールデンバーグ(1959~)は、『ゼロ・ダーク・サーティ』(2012)、『アルゴ』(2012)、『マイアミ・バイス』(2006)、『コヨーテ・アグリー』(2000)、『カラー・オブ・ハート』(1998)、『シービスケット』(2003)、『インサイダー』(1999)のようないまや名作の部類に入る作品を手掛けてきたベテランだが、『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』でこれらの作品を越えるものを出しているとは思えない。
◆逆に、『グランド・ブダペスト・ホテル』のバーニー・ピリングは、過去の『カルテット!人生のオペラハウス』(2012)、『ワン・デイ 23年のラブストーリー』(2011)、『わたしを離さないで』(2011)、『17歳の肖像』(2009)でいい仕事をしたうえで、今回は過去の仕事をさらに上回る成果を上げたという点で、最も高い評価をあたえるべきだろう。ただし、編集賞の評価基準はそういう見方をしないようだ。
◆過去の作品よりよいという点では、『セッション』のトム・クロスが一番がんばっているかもしれない。クロスが編集した作品は、『チョコレートドーナツ』(Any Day Now/2012/Travis Fine)と『タイムシャッフル』(Time Lapse/2014/Bradley King)しか見ていないが、前者は、ロバート・ダウニー・Jr.とアル・パチーノを掛け合わせてゲイにしたようなアラン・カミングは悪くなかったが、全体にダレた感じがした。後者は、気を持たせるテーマと絵柄であるにもかかわらず、退屈だった。
◆『アメリカン・スナイパー』のジョエル・コックス(1942~)、ゲイリー・D・ローチ(1964~)は、(とりわけコックスは)イーストウッド番とでもいうべきエディターで、功績的には申し分ない。ただし、わたしは、今回、冒頭でクリス・カイル(ブラッドリー・クーパー)が手榴弾を隠し持った女と子供に狙撃のねらいを定め、引き金を引く一歩手前で、カイルの少年時代から軍に志願するまでの経緯をながながと紹介する編集の仕方に、凡庸なものを感じないわけにはいかなかった。気を持たせるにしても、カイルの少年時代から青年期、結婚、過酷な訓練、イラクへの派遣までを時間軸で追う必要はなかったのではないか? もし、これが編集のウィークポイントになるとすれば、作品賞もなしということになり、わたしの希望的予測ははずれてしまうが、『アメリカン・スナイパー』の編集が傑出しているとは思えない。
◆というわけで、苦しいところだが、綜合点的には、『グランド・ブダペスト・ホテル』、ユニークさでは、『6才のボクが、大人になるまで。』を選ぶ。『6才のボクが、大人になるまで。』が他の賞とダブるのバカげたことだと思うが、監督も俳優も並でないことをやったうえに、編集こそが作品の形を決定しているというユニークさを評価して、わたしは、『6才のボクが、大人になるまで。』を勝者にしたいと思う。
(2015/02/13)
●美術賞: グランド・ブダペスト・ホテル [アダム・ストックハウゼン、アンナ・ピノック]
◆美術賞には、プロダクションデザインだけでなく、セットデコレーションも入る。セットデコレイションは、予算がものを言う。推定予算額からすると、米ドルで、『グランド・ブダペスト・ホテル』→3千万、『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』→1千400万、『イントゥ・ザ・ウッズ』→5千万、『ターナー、光に愛を求めて』→1千万に対して、『インターステラー』は、1億6千500万ドルと、桁がちがう。そして、金をかけただけのことは十二分に具体化しており、見事というほかはない。宇宙空間のシーンをちょっと見ただけでも、『ゼロ・グラビティ』などとはレベルがちがうことがわかる。ここまでくると、セットデザインがテクノロジーと科学の新しい実験を包含していると言ってもよい。この映画の製作のプロセスが先端テクノロジーを利用しているだけでなく、逆に先端テクノロジーを産業製品化する際に少なからぬ貢献をするのではないかとすら思える。
◆プロダクションデザインのネイサン・クロウリーとセットデコレイターのゲイリー・フェティスがやりたいことをやりつくしたと思える『インターステラー』と、他の4作品とをくらべるのは無理だろう。そもそも、全5作品をプラネタリウムのような巨大スクリーンで上映してみれば、『インターステラー』の細部の凄さがもっとはっきりするはずだ。逆に、中スクリーンでは美しく見える『ターナー、光に愛を求めて』は無残な映像になるかもしれない。たとえば、冒頭の街路のシーンで、時代設定は19世紀なのに、歩道に20世紀のデザインのマンホールが見えるような状態がはっきりとしてしまうからである。この作品は、比較的小さなスクリーンで見るときに映える作りになっている。ちなみに、プロダクションデザインのスージー・デイヴィーズとセットデコレイションのシャルロット・ワッツは、テレビの仕事を多数こなしてきた。
◆映像のトレンドは、モバイルの浸透とともに次第に小画面志向になっている。批評家も劇場では見ずに、自分のコンピュータ(しかもラップトップの)画面で見て批評する時代である。ちなみに、『Life itself』(2014)で記録されているように、癌にかかっても最期まで批判精神にみちたレヴューを書き続けたロジャー・イーバートは、自宅の液晶画面で試写を見ていた。大画面で見るべき映画は依然としてあるが、それを小画面で見てもすぐれた批評を書くことは不可能ではない。とはいえ、どんなに想像力がゆたかな批評家でも、『インターステラー』を小画面で見たのでは、この映画のポテンシャルを知覚することはできないだろう。
◆選考で〝宇宙嫌い〟が多数を占めるならば、候補にあがっている『グランド・ブダペスト・ホテル』と『イントゥ・ザ・ウッズ』の両方のセットデコレイターがアンナ・ピックであることに注目するだろう。その場合は、『イントゥ・ザ・ウッズ』よりも『グランド・ブダペスト・ホテル』が有利である。
◆『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』のマリア・ジャーコビクとタチアナ・マクドナルドは、トーマス・アルフレッドソンの『裏切りのサーカス』(2011)と『ウディ・アレンの夢と犯罪』(2007)いっしょに担当している。映画らしいセッティングを手堅く、きめ細やかに設定するひとたちのようだが、派手さが目立つ対抗馬に対して、地味すぎるかもしれない。
(2015/02/14)
●衣装デザイン賞: グランド・ブダペスト・ホテル [ミレーナ・カノネロ]
◆たいていの候補者が、アカデミー賞にノミネートされた経験を持つなかで、『グランド・ブダペスト・ホテル』のミレーナ・カノネロ (1946~)はダントツで、アカデミ賞ーだけでも、今回をふくめて6回もノミネートされ、過去には、『マリー・アントワネット』(2006)、『炎のランナー』(1981)、『バリー・リンドン』(1976)でコスチュームデザイン賞を獲っている。なにせこのひと、スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』(1971)でコスチュームデザイナーとしてデビューし、気難しいキューブリックの難物『シャイニング』(1980)もまかされている。コッポラ父の『ゴッドファーザーPARTIII』(1990)を担当したのち、グレン・ゴードン・キャロンの『めぐり逢い』(1994)で主演のウォーレン・ベイティと仕事をした縁で、彼の『ブルワース』に起用された。オリヴィエラの『夜顔』(2006)、ウェス・アンダーソンの『ダージリン急行』(2007)、ポランスキーの『おとなのけんか』(2011)と見てくると、『グランド・ブダペスト・ホテル』のコスチュームデザインはミレーナ・カノネロが適任だという気になる。過去の仕事から吹き上がってくる仕事ぶりを評価したい。
◆『インヒアレント・ヴァイス』のコスチュームデザインを担当したマーク・ブリジズは、すでに『アーティスト』で受賞しているが、60年代後半の西海岸文化を知っている者、さらには、デザインレベルでの何回目かの〝60年代〟リバイバルを好むひとには、ホアキン・フェニックスの服や髪型をはじめとして、何度見ても楽しいらしい。〝らしい〟とわたしが言うのは、60年代を多少知っているわたしには、いくら汚してみても映画のなかの彼らは清潔すぎるように見えるからである。とはいえ、マーク・ブリジズがMarissa G. Mullerのインタビューで話している製作エピソードはなかなか面白かった。とはいえ、彼は、この映画が60年代という時代の終末を描いているということを十分承知しているのだが、それならば、その衣装デザインも服飾的な雰囲気も、もっと〝滅び〟の感覚に満ちていてよかったと思うのだ。
◆『マレフィセント』のアンナ・B・シェパード (1946~) がアカデミー賞と縁がなかったのは、1980年代までポーランドをベースに活躍してきたからだろう。クシシュトフ・ザヌーシとの仕事は数多い。日本で公開されているものでは、『結晶の構造』(Struktura krysztalu /1969)、『コンスタンス』(Constans/1980)と『太陽の年』(Rok spokojnego slonca/1984)の仕事をしている。英語圏で有名になるのは、スピルバーグの『シンドラーのリスト』(1993)からだ。以後、フォルカー・シュレンドルフの『魔王』(1996)、レオン・ポーチ 『クロコダイルの涙』(1998)で実力を見せ、マイケル・マンが『インサイダー』(1999)で起用。これも面白い組み合わせだった。その後、ポーランド出身のポランスキーの『戦場のピアニスト』(2002)に関わるが、これは、シェパードにとってはうれしい仕事だっただろう。本意でない作品もあるが、2010年代になるとコンスタントに注目される作品につきあうようになる。サダム・フセインの息子のダミーの記悲劇『デビルズ・ダブル ある影武者の物語』(2011)は面白かった。ブライアン・パーシバルの『やさしい本泥棒』(2013)は傑作だ。今回の『マレフィセント』は、『イングロリアス・バスターズ』のときのブラッド・ピットとのコネクションからだろうか? いずれにせよ、アンナ・B・シェパードは、ピットとジョリー夫妻に気に入られ『フューリー』(2014)のコスチュームデザインも担当している。こう見てくると、アンナ・B・シェパードの才能は多彩であり、業績的にはミレーナ・カノネロと遜色がない。『マレフィセント』が出来栄えのわりに評価が低いのは、アンジェリーナ・ジョリーへの反感のためか? 男や同性や戦争に対して彼女がどういう考えをもっているかもよくわかる。ただのおとぎ話ではない。が、ヴィジュアルの処理のよさもあるだろうが、登場人物の衣装に違和感がなく、アンジェリーナの羽と衣装が多くを語る。彼女は、2013年にの乳腺切除の手術を受けているが、この映画のなかで、妖精のマレフィセントが羽をもがれるということと、アンジェリーナの実の経験とが演ずる彼女の意識のなかで交じり合うような表情をする瞬間があり、なるほど、この映画は、彼女による彼女のための映画でもあるのだなと思った。
◆『イントゥ・ザ・ウッズ』のコリーン・アトウッド(1948~)は、ここではあまり本領を発揮しているとは思えない。それは、彼女がコスチュームデザインを担当している『ビッグ・アイズ』(2014)が抜群によいと思うからだけではなく、もっといい仕事をたくさん見せているからである。デヴュー初期の1980年代にはマイケル・マンの『刑事グラハム 凍りついた欲望』(1986)やリドリー・スコットの『誰かに見られてる』(1987)に起用されたのち、以後数々の名作を担当し、受賞歴も多い。ジョニ・デップとの関係は深く、ティム・バートンの『シザーハンズ』(1990)以来、ざっと見ても、『エド・ウッド』(1994)、『スリーピー・ホロウ』(1999)、『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』(2007)、『パブリック・エネミーズ』(2009)、『アリス・イン・ワンダーランド』(2010)、『ラム・ダイアリー』(2011)、『ツーリスト』(2011)、そして今回の『イントゥ・ザ・ウッズ』まで続いている。この流れを思い起こしても、『イントゥ・ザ・ウッズ』よりはるかに見栄えのする彼女の仕事が思い浮かぶ。だから、業績と功労賞の係数を抜きにすれば、今回の受賞は無理だろうとわたしは思う。
◆『ターナー、光に愛を求めて』のジャックリーン・デュランがコスチュームデザインを担当した作品には、ほとんど駄作がない。マイク・リーの監督作品が多く、『人生は、時々晴れ』(2002)は、彼女の初期の仕事であり、以後、『ヴェラ・ドレイク』(2004)、『ハッピー・ゴー・ラッキー』(2008)、『家族の庭』(2010)と秀作が続く。限られた監督と俳優との仕事をし、ジョー・ライトとの『プライドと偏見』(2005)、『つぐない』(2007)、『路上のソリスト』(2009)、『アンナ・カレーニナ』(2013)もよい結果を生んだ。リチャード・アイオアディ『嗤う分身』(2013)のコスチュームデザインも面白かったが、ジャックリーン・デュランというデザイナーはあまり浮気が出来ないひとのようだ。だから、『ターナー、光に愛を求めて』は、マイク・リーとの仕事の頂点ともいうべき作品になっていると思う。一貫してよりよい仕事をしてきたという意味で、ジャックリーン・デュランには好感が持てる。が、脂ぎったアカデミー賞の選考では、そういうつつましさは評価されないのだろう。
(2015/02/15)
●メイクアップ&ヘアスタイリング賞: グランド・ブダペスト・ホテル [フランセス・ハノン、マーク・クーリエ]
◆メイクアップも、仕上がった映像だけから判定するのが現場とずれる率が高そうなジャンルである。感覚的な印象からすると、3候補のうち、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のメイキャップは、デジタル処理でやりつくすことが可能な場合にも、メイキャップの手作業的な面をあえて見せつけることによって、トリッキーな裏技をやっている。これは、ピーター・クイル(クリス・プラット)が地球人であり、惑星人とは異なることを強調すると同時に、この映画の出自がマーベルコミックスであることをも暗に示す。ほとんどメイキャップをしていないかに見えるクリス・プラットがいるために、他の、顔色の差異や〝幼稚〟に見える(単色志向の)皮膚や肌の特徴を対置するだけで、不思議な生々しさが生じる。デジタルの〝ウソっぽさ〟を相殺できるのだ。必ずしもメイキャップ・サイドだけの知恵と技術ではないとしても、なかなか賢い。
◆メイキャップが、古典的な意味での化粧と〝らしさ〟の技術だとすれば、『フォックスキャッチャー』のスティーブ・カレル(→ジョン・デュポン)、チャニング・テイタム(→レスラー、マーク・シュルツ)、マーク・ラファロ(→同、デイブ・シュルツ)への変身は見事である。が、メイキャップしましたと自己主張しないのが古典的なメイキャップの技法であるとしても、本作の場合、その〝らしさ〟は多分に3人の俳優の抜群の演技に負っていることも事実である。
◆〝らしさ〟という点では、『グランド・ブダペスト・ホテル』は、出演者の数の多さもさることながら、〝らしさ〟の対象が『フォックスキャッチャー』のような〝実在〟の人物や環境(とはいえ、それらも観客にとっては新聞や本やテレビのマスメディア的記録を通じて刷り込まれたものにすぎないのだが)ではないところが面白い。それは、物語のなかに存在する内在的な要素なので、観客はその〝らしさ〟をそれぞれに味つけできるのである。さらに、ウィレム・デフォーが最たる例だが、それっぽいメイクをほどこしてその俳優にあえてそれっぽい演技をさせるといった技も見られる。それは、エドワード・ノートンにも、マチュー・アマルリックにも、シアーシャ・ローナンにも・・・言える。また、裸になるのが好きなハーベイ・カイテルに入れ墨だらけの裸の演技をさせ、頭も剃らせるというのも、彼の他の作品への記憶を刺激する秀逸なメイキャップである。参照性を埋め込んだメイクアップ&ヘアスタイリング技術になっているわけだ。
◆今年のメイクアップ&ヘアスタイリング賞で変わったのは、これまでは、作品としての評価はB級でもメイキャップやヘアスタイリングがユニークだとノミネートされる余地があったのに対して、今年は、候補の3作とも作品としての評価が高いものばかりだという点である。そのため、メイクアップ&ヘアスタイリングという点にしぼった選別が難しくなった。作品全体の評価がこの賞の評価につながってしまう傾向があり、撰者の好み次第で三者三様の結果になるわけである。わたし自身は、『フォックスキャッチャー』、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』、『グランド・ブダペスト・ホテル』はそれぞれに楽しみ方のちがう映画だと思うので、これ1本というわけにいかず、さらに選別が難しくなる。演技をささえる技術としてメイクアップ&ヘアスタイリングを考えれば、『フォックスキャッチャー』を選ぶ。メイクアップ&ヘアスタイリングが演技と同等に自己表現しているという点でならば、断然、『グランド・ブダペスト・ホテル』だろう。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』もその系列に分類できるが、その多声性(ポリフォニー)の度合では、『グランド・ブダペスト・ホテル』にはおよばない。
(2015/02/16)
●作曲賞: グランド・ブダペスト・ホテル [アレクサンドル・デスプラ]
◆作曲賞は、映像と切り離されて視聴され、評価されるのか、それとも映像といっしょに聴かれて評価されるのかで、大分結果が異なるのではないかと思う。
◆5作品のオリジナル・スコア―のうち、わたしが映像といっしょに聴いて、一番いいと思ったのは、意外にもハンス・ジマーの『インターステラー』だった。意外にもというのは、わたしは、通常、ハンス・ジマーには飽きていたからである。だから、ゴールデン・グローブ賞でヨハン・ヨハンソンの『博士と彼女のセオリー』が受賞したとき、《アレクサンドル・デスプラ(『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』)は本気すぎて、ヨハン・ヨハンソン(『博士と彼女のセオリー』)のミニマルなところがかえって新鮮に聴こえた。ハンス・ジマー(『インターステラー』)がけっこうよくて、困ってしまった。》と書いた。この印象はいまでも変わっていない。
◆YouTubeにサウンドトラックがあるので、個別に聴いてみると、アレクサンドル・デスプラの『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』は、オーケストレイションが歌いすぎるように思う。『グランド・ブダペスト・ホテル』では、多彩な変化を取り込んでいるが、このひとの性格か、本気すぎて、疲れる。ヨハン・ヨハンソンの『博士と彼女のセオリー』は、他にくらべて凡庸、ゲイリー・ヤーションの『ターナー、光に愛を求めて』は描写的すぎるような気がする。
◆異論はあるだろうが、ゴールデングローブ賞にも、BAFTA(『グランド・ブダペスト・ホテル』)にもあえて逆らい、ハンス・ジマーを選ぼうと思う。
(2015/02/17)
●歌曲賞: セルマ〔仮題〕/Glory[コモン、ジョン・レジェンド]
◆コモンとジョン・レジェンドの〝Glory〟(『セルマ〔仮題〕』)以外は、ゴールデングローブ賞とはダブらないのはよかった。違う賞なのにダブるのは、いいものはいいということではなくて、ハリウッドビジネスの事情から来る。ハリウッドではまだ、多品種少量生産の論理は通用しないようだ。ちなにみ、わたしは、ゴールデングローブ賞のコメントでは、《受賞した"Glory" (『セルマ〔仮題〕』)は、一番わかりやすい(ハハハ)。》と書いてしまった。
◆作曲賞のところでも指摘したが、ノミネート作品のソングが、映画から切り離されて売られる場合の評価なのか、それとも映画といっしょに聴かれたときの評価なのかがここでも問題になる。受賞によってソングの売れ行きを伸ばすという意向からは、ゴールデングローブ賞と同様に『セルマ〔仮題〕』の"Glory"が受賞しそうである。
◆歌曲賞で候補になるソングを単独で聴いてみると、映画のなかとのちがいに驚く。『はじまりのうた』でキーラ・ナイトレイがクラブでステージに立たされてしぶしぶ歌いだす"Lost Stars"は、彼女の演技としては悪くないのだが、映画で示される諸事情と切り離すと、他の候補(みな歌のプロだ)のソングほどの力はない。
◆『LEGO(R) ムービー』は、LEGOを使ったユニークなアニメだし、候補に挙がっている"Everthing is Awesome"は映画のなかではさりげなく使われていた。が、これを単独で聴くと(→YouTube)、全然印象がちがう。
◆『ビヨンド・ザ・ライツ』の"Grateful"は、リタ・オラが歌うテーマソングであって、主役のググ・バサ=ローが歌うわけではない。彼女がステージで歌ったあとにかぶさって流れるのである。テーマソングとはそういうものであり、この映画のために書かれたオリジナルであるわけだから、文句はない。しかしです、もし、出演者が歌い、しかもその映画のために歌って、しかも感動的であるとしたら、どちらが〝映画のため〟と言えるだろうか? いちゃもんめいたことを言うのにはわけがある。
 ◆『Glen Cambell: I'll Be Me』のトレイラーを YouTube → 〔1〕 〔2〕 )で見て、他のソングが吹っ飛んでしまったからである。このドキュメンタリーについてのBob Ignizioのレヴュー に詳しいが、これは、グレン・キャンベルが、歌うことでアルツハイマーを〝克服〟するドキュメンタリーなのだ。むろん、アルツハイマーは治らない。少なくともいまのところは。だが、1936年生まれの彼は、歌うというプロセスのなかでは、完全に〝正常〟に、しかも、これまで以上に感動的に歌うのだ。ここには、アルツハイマーとか認知症とかいうものが、病である以前に、実はもうひとつの生き方であることを示唆するものがあると思う。
◆『Glen Cambell: I'll Be Me』のトレイラーを YouTube → 〔1〕 〔2〕 )で見て、他のソングが吹っ飛んでしまったからである。このドキュメンタリーについてのBob Ignizioのレヴュー に詳しいが、これは、グレン・キャンベルが、歌うことでアルツハイマーを〝克服〟するドキュメンタリーなのだ。むろん、アルツハイマーは治らない。少なくともいまのところは。だが、1936年生まれの彼は、歌うというプロセスのなかでは、完全に〝正常〟に、しかも、これまで以上に感動的に歌うのだ。ここには、アルツハイマーとか認知症とかいうものが、病である以前に、実はもうひとつの生き方であることを示唆するものがあると思う。
(2015/02/17)
●録音賞: セッション [クレイグ・マン、ベン・ウィルキンス、トマス・カーリー]/音響編集賞: アメリカン・スナイパー [アラン・ロバー・マーレイ、バブ・アスマン]
◆録音賞(Sound Mixing)と音響編集賞(Sound Editing)では、ノミネート作品の多くがダブっているので、いっしょにとりあげることにする。事実、通常の場合、音のMixingとEditingとを厳密に分けるのは難しい。今回ダブっていないのは、録音賞の『セッション』と音響編集賞の『ホビット 決戦のゆくえ』だけである。
◆たしかに、『セッション』のミクシングはセンスがいい。マイルズ・テラーが廊下をあるいてくると教室から聞こえてくる生演奏の音が単なる直接的な知覚としてだけでなく、彼の心の動きの響きとしても聴こえるような混ぜ方をするときがある。街を歩いていて路上のミュージッシャンのドラムソロがすっと入ってくるシーンも同様である。電話の相手の音の流し方も工夫している。音の微妙さがスリリングな映画だから、音採りが繊細で当然だとしても、このサウンド・ミクシングはすばらしい。
◆『ホビット 決戦のゆくえ』で、イアン・マッケランとマーティン・フリーマンが蜘蛛の糸で覆われるシーンの音はユニークだ。担当のブレント・バージとジェイソン・カノヴァスは、ピーター・ジャクソンとの縁は深く、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の音にもすべてつきあっている。ジェイソン・カノヴァスが、初期に、ウディ・アレンの『トラブルボックス 恋とスパイと大作戦』(Don't Drink the Water/1994)のアシスタント・サウンドエディターをやっているにが気になった。
◆『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』の映像は、シングルテイク風に流れるので、サウンドのエディディングもミクシングも楽ではない。そこでくりかえし聞こえるドラムの音が必要になるのだが、ミクシングとしては、『セッション』よりユニークだとはいえない。たとえば、マイケル・キートンがニューヨークの街でエドワート・ノートンと別れ、エマ・ストーンの店に来て、マリファナのことで言い合いになり、彼女に啖呵を切られて黙ってしまうとき、音楽が入るが、それが、えらく感情の同化を求めるセンチメンタルな(ふつうの)入れ方なのだ。これだと、キートンが演じる表情は〝淋しさ〟というような単純が言語表現で済ませられるようなレベルに堕ちてしまう。この映画のミクシングが冴えているとは思えない理由である。
◆『アメリカン・スナイパー』は、戦車の重厚な音から始まるが、イーストウッドの監督作品だけあって、兵器の音採りはすばらしい。見せ場になるブラッドリー・クーパーの狙撃シーンのミクシングとエディティングは、チョムスキー先生(たぶん、原作で判断し、映画を見ずに批判している →Noam Chomsky's Take on the film American Sniper)に叱られるかもしれないが、惚れ惚れする。これは、映像編集のうまさでもあるが、クーパーが仲間と車で移動中にイラク側の狙撃者に襲われるときの音の処理も見事である。そのとき彼は、故郷にいる妻と電話で話をしている最中であった。車のなかの彼は路上の妻からお腹の子が男であることを知らせられたばかりなのだが、突然始まった戦闘の模様を彼女はモバイルフォンで聴くことになる。この映画では、登場人物の心象風景に観客が同化することを求めるような音処理や音楽の入れ方はしない。即物的なハードボイルドな処理である。これは、この映画が、単純に反戦や愛国をとなえるプロパガンダからはっきりした距離をつくる。
◆しかし、それにもかかわらずわたしが『インターステラー』の音のミクシングとエディティングを他作品より高く評価するのは、映像もそうだが音の帯域が(上映装置次第で)はるかに広い。だから、音の冴えがちがう。また、『アメリカン・スナイパー』にくらべるとひんぱんに入ってくる音楽(ハンス・ジマーもそのことを完璧に理解している)が、決して登場人物の心象風景などに同化することを求めるようなミックスされ方をしていないのもいい。観客自身が考え、それ自身の感覚を感じることを求めているのだが、それは強制されない音。
◆『アンブロークン〔仮題〕』の音採りは見事である。爆撃、波の音、雨、捕虜として閉じ込められた穴で聞こえる外の音・・・非常にリアルである。が、そこにじわーっと入ってくる音楽が安い。完全に登場人物の意識を描写している。
◆もし脳に直接インプットする技術が身近なものになれば、その音源としてのパフォーマンスを十分満たすであろう『インターステラー』のサウンド・デパートメントの偉業に敬意を表する。え?これくらい予算があれば俺でもできるって? 『アメリカン・スナイパー』の推定予算は、5千880万ドルだが、『インターステラー』は、1億6千500万ドル、つまり2.8倍だ。同じ土俵で評価していいものだろうか? 興行収益の評価からすると、『アメリカン・スナイパー』が有利だが、ここでは、未来の映画のために、『インターステラー』を選ぶ。
(2015/02/17)
●視覚効果賞: インターステラー [ポール・フランクリン、アンドリュー・ロックリー、イアン・ハート、スコット・R・フィッシャー]
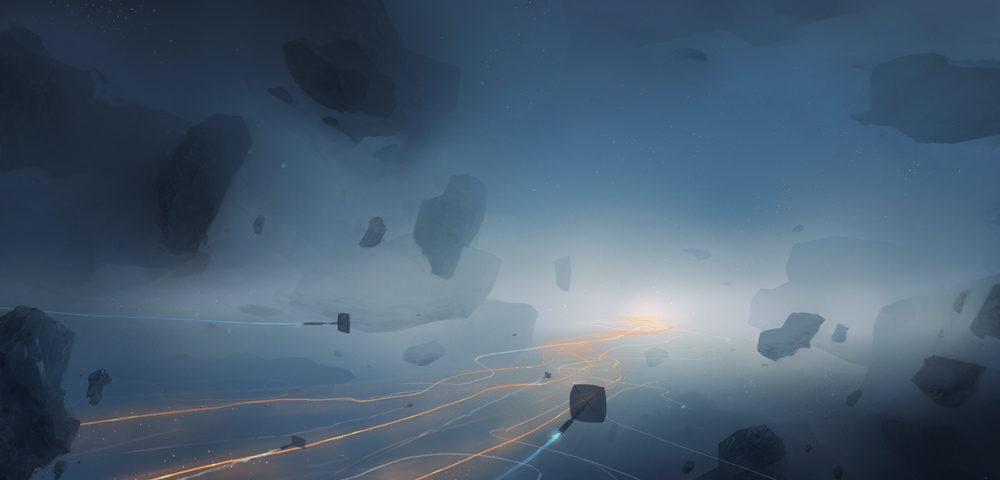 ◆『インターステラー』の映像を思ったら、他の4作品が精彩を失った。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は楽しく仕上がっているが、感覚や映像から触発される新な思考は特にない。『キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー』は、5候補のうち一番激しいアクションの連続だが、これはまさにジェットコースター・ムービーの模範ではあっても、それ以上ではない。『猿の惑星:新世紀(ライジング)』は、モーションキャプチャーを最も数多く使っているとのことだが、ヴィジュアル・エフェクツとしてはどこが凄いのかがわからなかった。『X-MEN:フューチャー&パスト』となると、ヴィジュアルエフェクト的にはレトロの感じすらする。
◆『インターステラー』の映像を思ったら、他の4作品が精彩を失った。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は楽しく仕上がっているが、感覚や映像から触発される新な思考は特にない。『キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー』は、5候補のうち一番激しいアクションの連続だが、これはまさにジェットコースター・ムービーの模範ではあっても、それ以上ではない。『猿の惑星:新世紀(ライジング)』は、モーションキャプチャーを最も数多く使っているとのことだが、ヴィジュアル・エフェクツとしてはどこが凄いのかがわからなかった。『X-MEN:フューチャー&パスト』となると、ヴィジュアルエフェクト的にはレトロの感じすらする。
◆『インターステラー』は、単にブラックホールやワームホールといった概念を問題にしているというような観念的な印象よりも、実際にこの映像に接するとき、時間の謎を考えざるをえないというところを評価したい。ありきたりの時間の観念を打ち壊し、たとえば、われわれは、たえずワームホールのようなものを通過しながら時間を生きているのではないかといった思いに誘われるのである。ヴィジュアルエフェクツのスパーヴァイザーをつとめたポール・J・フランクリンによると、意外にも、95%のスペース・ショットは物理的なミニュチュアを使ったという。むろん、それにデジタル処理をほどこすわけだが、われわれが目にする映像には被写体があったということである。また、スペースクラフト内の俳優たちは、30 x 300 フィートのスクリーンに投射されるプロジェクターの映像に移る外部空間を見ながら演技した。彼や彼女らは、グリーンスクリーンに囲まれて(あとで合成するための)演技をしたのではない。
◆ブラックホールの視覚化、Tesseract(「正八胞体」ないしは「四次元超立方体」と訳される)のなかで、異次元の同時間が流れるシーン、高波が襲ってくる水面のシーン、凍てついた広漠とした原野等々、通常のヴィジュアルエフェクツの成果としても斬新な体験をさせられるが、これらが単なる視覚的なこけおどしではなく、新しい感覚と思念を引き起こすところがすばらしい。
(2015/02/19)
●長編ドキュメンタリー映画賞:シチズンフォー (Citizenfour) [ローラ・ポイトラス、Mathilde Bonnefoy、Dirk Wilutsky]
◆今年の候補には、状況を考えさせるものが多い。評判のいい『シチズンフォー 〔仮題〕』は、アメリカのNSA(国家安全保障局)が一般人を含むアメリカ在住者の電子メール・携帯電話・Google検索・銀行預金などの情報を傍受(通信の途中で盗む)していたことを元CIA分析官のデイヴィッド・スノーデンが暴露したことから発覚した「スノーデンゲイト」のドキュメンタリーだが、スノーデンが実際にNSAのデータベースをハックして、そうした盗聴データが記録されることをカメラのまえで示すシーンがあるにもかかわらず、どこか薄ぺらい。それは、スノーデンにインタヴューして、すぐにCNNにすっぱぬいたジャーナリストGlenn Greenwaldの(本気ではあるが)テレビ屋的一発主義が醸し出す雰囲気のためと、もう一つは、アメリカ合衆国の暗部を暴き出したスノーデンが、モスクワに亡命してしまったことのためかもしれない。モスクワ亡命は、ウィキリークスのジュリアン・アサンジらがアレンジしたといわれるが、なんかこれでは米露両超大国の力学のなかを右往左往しているだけの感じがし、拍子抜けするのである。『ニューヨーク・タイムズ』紙の映画批評家A.・C.・スコットは、外国映画賞にノミネートされている『リヴァイアサン』についての一文のなかで、この映画のなかで描かれているような〝時代遅れ〟なことが起こる一方で、スノーデンの亡命を受け入れるようなところがいまのロシアの興味深いところだと書いていたが、これがまさにプーチンの独裁制ではないかとわたしは思う。
 ◆『Finding Vivian Maier』は、生前は一度も写真家としては認知されたことのないフランス人のヴィヴィアン・マイヤーという女性を発掘する記録である。それは、シカゴの街の歴史の本を執筆していたジョン・マルーフが、たまたま、オークションで彼女の持ち物を手に入れたことから始まる。次第に明らかになるのは、ヴィヴィアン・マイヤーは、25歳でニューヨークに移住し、しばらくバイト仕事をしたのち、1956年にシカゴで修道女という職業のかたわらにシカゴの街をローライフレックスで撮りはじめたが、死の2年前(2007年)にアパートのレントが払えなくなって、持ち物がオークション(というより競売に近い)に出されたのだった。マルーフは、その再発見の過程を自ら撮影し、編集してこの作品を作りあげた。彼女は自分の写真が公開されるのを目にすることはできなかったが、マルーフは、漸次、彼女の3万点におよぶネガフィルムを入手し、写真展も開いていく。そこには、1970年代を中心とするシカゴの都市生活者のつつましい暮らしと孤独がヴィヴィッドに描かれている。老いとその死のなかで廃棄されていく遺品のなかには、このような貴重な記録が数多くあるはずである。ジョン・マルーフのこの〝DIY作品〟は、こうした遺品への再考をうながしもする。彼は、一発当てたのかもしれないが、歴史というものに対する彼の好奇心がなければ、実現しなかったことであり、そうして好奇心の必要を教えもする。
◆『Finding Vivian Maier』は、生前は一度も写真家としては認知されたことのないフランス人のヴィヴィアン・マイヤーという女性を発掘する記録である。それは、シカゴの街の歴史の本を執筆していたジョン・マルーフが、たまたま、オークションで彼女の持ち物を手に入れたことから始まる。次第に明らかになるのは、ヴィヴィアン・マイヤーは、25歳でニューヨークに移住し、しばらくバイト仕事をしたのち、1956年にシカゴで修道女という職業のかたわらにシカゴの街をローライフレックスで撮りはじめたが、死の2年前(2007年)にアパートのレントが払えなくなって、持ち物がオークション(というより競売に近い)に出されたのだった。マルーフは、その再発見の過程を自ら撮影し、編集してこの作品を作りあげた。彼女は自分の写真が公開されるのを目にすることはできなかったが、マルーフは、漸次、彼女の3万点におよぶネガフィルムを入手し、写真展も開いていく。そこには、1970年代を中心とするシカゴの都市生活者のつつましい暮らしと孤独がヴィヴィッドに描かれている。老いとその死のなかで廃棄されていく遺品のなかには、このような貴重な記録が数多くあるはずである。ジョン・マルーフのこの〝DIY作品〟は、こうした遺品への再考をうながしもする。彼は、一発当てたのかもしれないが、歴史というものに対する彼の好奇心がなければ、実現しなかったことであり、そうして好奇心の必要を教えもする。
◆『Last Days in Vietnam』は、ヴェトナム戦争の最末期のサイゴンの状況を当時の記録フィルムと撤退に関わった関係者へのインタヴューから構成している。1968年のテト攻勢以後、勢いを増した北ヴェトナム軍が1975年4月、南ヴェトナムのサイゴンを包囲するにいたり、米軍と南ヴェトナムの市民で米軍と関係のあった者たちがサイゴンを脱出する。パニックに陥った市民が脱出を求めてアメリカ大使館に集まり、壁を越えて館内に入ろうとするが、米国との関係者や米国人の知り合いがいなければ脱出は不可能である現実に直面する姿は痛ましい。映画は、このとき米国が、グラハム・マーティン大使をはじめとして、いかに南ヴェトナム人に対して人道的な態度で臨んだかを描いている。実際、多数の市民をヘリコプターで船に移送し、フィリピンに向けて進みはじめたとき、米軍のヘリコプターに乗った市民たちが追いかけてきて乗船を望むが、甲板に着陸したヘリをそのままにすることが出来ず、市民を降ろしたのち海中に投棄するが、パイロットが海中に落下する等々、米軍の献身的な姿が映されている。ここでは、この脱出作戦に加わったリチャード・アーミテージのようなタカ派で元CIA要員でもあった(そして「知日派」で知られる)人物も、感動的な英雄に見えてくる。だが、これは、ある意味で、敗退する米軍と彼らに協力し、その後米国に亡命した南ヴェトナム人たちの〝絆〟を再確認することによって、アメリカは、過去の(そして今後の)〝植民地主義〟においても、現地人を大切にするということを暗に強調するプロパガンダにも見える。
◆『セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター』(The Salt of the Earth)を通して見ることはできなかったのだが、ブラジルの巨匠写真家セバスチャン・サルガド(1944~)の仕事の足跡を追い、彼の撮影現場にも同行したヴェンダースは、〝サルガドを彼が世界を見るように彼を見ている。彼が写真撮影のために世界を旅したことが、いかなる伝記的な説明が語りうること以上のことを伝えている〟と言う。過去40数年間に世界の諸大陸を踏破し、20世紀の主要な歴史的事件の証人となったセバスチャン・サルガドだが、その経験を総括して、彼は、映画のなかでこう言う――〝われわれは残忍な動物だ。われわれ人間は、ひどい動物である。その歴史は、戦争の歴史である。それは、狂気の物語だ・・・〟(YouTubeのトレイラー)。しかしながら、ヴェンダースを感動させ、この映画を撮る気にさせたサルガドの写真は、原始的な領野、野生の動物や植物、壮大な景色に収斂する人間性――その存在を写真を通じて知覚することによって、他者への通路を発見できる――に満ちてもいるらしい。が、トレイラーやサルガドの言葉を散見したかぎりでは、ちょっと〝偉すぎる〟という気がしてしまった。
 ◆『Virunga』は、コンゴ民主共和国の北東部にあるヴィルンガ国立公園に住む野生のマウンテン・ゴリラを救出するレインジャーたちの活動を映す。『シチズンフォー 〔仮題〕』のメディア批評的な今日性、『Finding Vivian Maier』の推理小説的な快感と若い監督のDIY的しなやかさ、『Last Days in Vietnam』のつかのま起こる感動、などなどで、そのつど最優秀作はこれかと浮気な決断をしてきたわたしだが、『Virunga』を見るにいたって、その文明論的今日性と、依然として過去のものとはならない植民地主義のしたたかさ、そしてそれと闘う人びとが描かれているのを発見して、この作品を選ぶことにした。受賞の基準は作品の映画的な優秀さで決まるとはかぎらないから、多くの人が予想するように、『シチズンフォー 〔仮題〕』あたりに収まるかもしれない。が、『Virunga』は、多くの人がぜひ見るべき作品であるという意味で、特筆したいのである。
◆『Virunga』は、コンゴ民主共和国の北東部にあるヴィルンガ国立公園に住む野生のマウンテン・ゴリラを救出するレインジャーたちの活動を映す。『シチズンフォー 〔仮題〕』のメディア批評的な今日性、『Finding Vivian Maier』の推理小説的な快感と若い監督のDIY的しなやかさ、『Last Days in Vietnam』のつかのま起こる感動、などなどで、そのつど最優秀作はこれかと浮気な決断をしてきたわたしだが、『Virunga』を見るにいたって、その文明論的今日性と、依然として過去のものとはならない植民地主義のしたたかさ、そしてそれと闘う人びとが描かれているのを発見して、この作品を選ぶことにした。受賞の基準は作品の映画的な優秀さで決まるとはかぎらないから、多くの人が予想するように、『シチズンフォー 〔仮題〕』あたりに収まるかもしれない。が、『Virunga』は、多くの人がぜひ見るべき作品であるという意味で、特筆したいのである。
◆アメリカは、中東に石油を求めて侵略をくりかえしてきた。ヴィルンガ国立公園の汚染と動植物の危機の元凶は、ロンドンを拠点とする石油企業SOCO Internationalである。SOCOは、採掘を進めるために、反政府活動を煽った。地主やフィクサーに賄賂をばらまき、M23叛乱を密かにバックアップした。映画に参加してフランスのジャーナリストのメラニー・グービ(Melanie Gouby)が隠しカメラで彼らの話を盗撮した映像と音が収められている。その一人はこともなげに言う――〝ダイヤモンドの糞でもするのでないかぎり、ゴリラなんかどうでもいい〟。他方、父を戦争で失ったレインジャーの一人のコンゴ人は、M23叛乱でヴィルンガの霊長類保護施設が爆撃の危機にさらされたとき、〝ゴリラはわたしの命。だから、もし死ぬのなら、ゴリラのために死ぬ〟と語る。森から保護したゴリラのなかには、親を失ったゴリラの子供がおり、このレインジャーになつき、甘えている。銃声におびえるゴリラたちの姿は、戦火を逃れる難民たちの姿につながる。ちなみに、SOCOの搾取に反対してきたヴィルンガ国立公園のディレクターであるエマニュエル・デ・メロード(Emmanuel de Mérode)は、2014年に何者かに撃たれたが、からくも死を逃れた。その意味でも、この映画は、現在進行形の映画である。詳細は、virungamovie.com にある。
(2015/02/21)
 ◆『Glen Cambell: I'll Be Me』のトレイラーを YouTube → 〔1〕 〔2〕 )で見て、他のソングが吹っ飛んでしまったからである。このドキュメンタリーについてのBob Ignizioのレヴュー に詳しいが、これは、グレン・キャンベルが、歌うことでアルツハイマーを〝克服〟するドキュメンタリーなのだ。むろん、アルツハイマーは治らない。少なくともいまのところは。だが、1936年生まれの彼は、歌うというプロセスのなかでは、完全に〝正常〟に、しかも、これまで以上に感動的に歌うのだ。ここには、アルツハイマーとか認知症とかいうものが、病である以前に、実はもうひとつの生き方であることを示唆するものがあると思う。
◆『Glen Cambell: I'll Be Me』のトレイラーを YouTube → 〔1〕 〔2〕 )で見て、他のソングが吹っ飛んでしまったからである。このドキュメンタリーについてのBob Ignizioのレヴュー に詳しいが、これは、グレン・キャンベルが、歌うことでアルツハイマーを〝克服〟するドキュメンタリーなのだ。むろん、アルツハイマーは治らない。少なくともいまのところは。だが、1936年生まれの彼は、歌うというプロセスのなかでは、完全に〝正常〟に、しかも、これまで以上に感動的に歌うのだ。ここには、アルツハイマーとか認知症とかいうものが、病である以前に、実はもうひとつの生き方であることを示唆するものがあると思う。
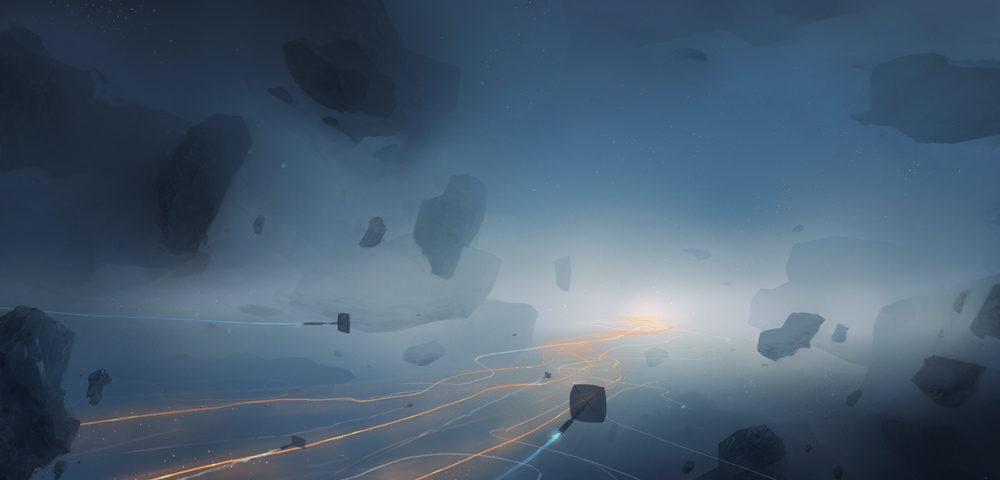 ◆
◆ ◆『
◆『 ◆『
◆『