|
★今月あたりに公開の気になる作品: ★★★★ ザ・マジックアワー ★★★★ ジュノ ★★★★ ぼくの大切なともだち ★★★インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 ★★ 奇跡のシンフォニー ★★ バグズ・ワールド ★★★★ イースタン・プロミス ★★ ●REC レック |
| サヴェジ家〔仮〕 バーナードとドリス〔仮〕 ラースと、その彼女 イントゥ・ザ・ワイルド メイド・イン・ジャマイカ 地球でいちばん幸せな場所 闇の子供たち 落下の王国 庭から上ったロケット雲 ホートン ふしぎな世界のダレダーレ きみの友だち |
2008-06-26_2
●きみの友だち (Kimi no Tomodachi/2008/Hiroki Ryuichi)(廣木隆一)

◆重松清の原作の映画化ということで話題になっていたが、逆にそういうニュースが流れれば流れるほど、身がひけてしまい、とうとう今日は、最後の試写日であった。重松の原作の映画化では、テリー・伊藤が主演している『あおげば尊し』や『疾走』をとりあげたことがあるが、『きみの友だち』でも、学校、家庭、親子、友人関係といったテーマが見える。しかし、今回の重松映画には、基本的なところでなじめないものを感じ、125分をすごすのが辛かった。これは、あくまでもわたしの受容性の問題であって、わたしとは正反対の印象を受けた観客も少なくないと思う。
◆わたしにとって何がダメかというと、一つは、10歳の女性たち(石橋杏奈、北浦愛、吉高由里子)の会話のフィーリングだ。それは、セリフを暗記して棒読みしている稚拙な面が気になるうえに、監督がこの世代の女の子のフィーリング(シャイと距離の文化とが入り混じった独特の――ある意味では白々しい感じ)として認識しているものと、わたしの認識とのちがいから来る。
◆設定されている場所は甲府だが、都市環境とも郊外ともちがうこのような地域に住む子供たちの意識がわたしには、外国以上に遠い存在に感じる。その点でも、わたしには、この映画を論評する資格がない。
◆10歳の恵美(石橋杏奈)と由香(北原愛)が「友だち」になったのは、それぞれが求めあったためではなく、教室で2人がたまたま体が不自由で、縄跳び大会のメンバーをクラスで決めるとき、クラスの子達から「飛べない子はあの二人だけだよね」といったことを言って「いじめ」にも似たやりかたで強制的に「縄持ち」に選ばれてしまったからである。大会まえに練習しておこうと、2人は運動場で縄を回すが、心臓の弱い由香は、うまく回せない。恵美は、それを冷たく批判する。実は、2人のあいだには、不幸な過去がある。恵美が道の向かいにいる由香に話をするために道路を渡ろうとして車にはねられ、松葉杖を捨てられない身になったのだ。それを恵美は、自分の足がこうなったのは「あんたのせいなんだからね」といまでも言っている。由香はそれを自分の罪と思っているようで、雨の日に「家で一番大きな傘」を持って、登校時間に恵美の家に迎えにきたりする。2人のあいだには、「女王」と「従者」的な関係があるが、それをことさらには描かないのはいい。どのみち、女の子同士のあいだにあるそういう意識差は別にめずらしいものではないからだ。このへんまではよくわかる。しかし、結局は若死にしてしまう由香への恵美の思いの屈折をなぜこれだけの時間をかけて描かなければならないのかがわからない。
◆映画は、ある種の時間体験である。その時間に呼応できなければ、どうにもならない。わたしは、それが今回できなかった。
(ショーゲート試写室/ビターズ・エンド)
2008-06-26_1
●ホートン ふしぎな世界のダレダーレ (Horton Hears a Who!/2008/Jimmy Hayward/Steve Martino)(ジミー・ヘイワード/スティーヴ・マーティノ)
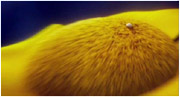
◆植物の葉にたまった雫(しずく)が3つぐらい集まって下に落ちる。その勢いで丸い実が地上にころげ落ち、ヒマワリの花が一面に咲く地帯をころがる。その勢いで、ヒマワリの一本の花のうえに寄生していた本当に小さな「speck」(字幕では「ほこり」となっていたが、この語には「花粉」や「胞子」といった意味もある)が地上に落ち、胞子のように飛び散る。普通こういう「ほこり」には気づかないが、繊細な象のホートンは、それを見て取り、しかもそこから発せられる声や音を聞き取り、そのなかに生き物がいることを直感する。
◆地球や宇宙という「マクロ」な観点からすれば、地球上の生物は「ミクロ」なにすぎない。人は、「マクロ」なものにばかり目が行き、「ミクロ」な世界をないがしろにする。世界の要素はかぎりなくミクロ化しているのに、話題になるのは、「地球」や「宇宙」である。もし、この映画で象のホートンが持ち合わせているような、ミクロな世界への繊細な神経を誰でもが持つならば、われわれの生き方も科学も学問も、根底から変わるだろう。
◆ミクロな世界への接近を許すテクノロジーが進むのと平行するかのように、人文科学でも、1930年代には「ミクロロギー」(ワルター・ベンヤミン)や「神々は細部に宿る」(アヴィ・ワールブルク)といった観念がはやりはじめる。そのころにくらべれば、われわれは、ケータイに代表されるような超小型の機器を持ち、自身の身体や周囲世界に対しても、そのころとはくらべものにならないほど「ミクロ」な世界にかかわっている。しかし、そういう世界は、決して「ミクロ」なものとは認識されていない。単に、かつては「ミクロ」だった世界が「マクロ」なものとして拡大されているにすぎないのだ。「ミクロ」な世界への認識力や神経は、むしろ衰えているかもしれない。「ミクロ」なものを自動的に拡大してくれるテクノロジーに自足して、「ミクロ」な世界を自分で知覚する能力を失っている。
◆「地球」とか「宇宙」とかいう観念がはやる時代は、全体主義の時代である。それは、ナチズムやスターリニズムとともに終わったかのように教科書的歴史は教えるが、実は、いまは、「ミクロ」世界を「マクロ」化して無化してしてしまう超全体主義の時代なのだ。
◆もし、「神々は細部に宿る」といった考え方や、フェリクス・ガタリの「ミクロ・ポリティクス」のような発想が一般化したら、一個の人間のなかに無数の「人間」がいること、両手を広げた態度の「小世界」のなかに「世界政治」があり、「地球」や「国家」などの政治を問題にするよりもよほど手がかかり、またそれだけ手ごたえのある世界であることがわかるだろう。「ミクロ」な世界は、「マクロ」な世界の単なる構成要素ではなくて、まさに人間の脳神経細胞の一つが破壊されると体全体が機能不全に陥るときのように、一にして全なる要素なのである。
◆映画の最後の方で、「Person is person no matter how small」(どんなに小さくても、人は人)という言葉が出てくる。ホートンにはわかった「ダレダーレ」の世界は、ホートン的な繊細さを徹底させるならば、いたるところに存在することがわかるのだろう。この映画は、世界の新しい見方を示唆する。
(フォックス試写室/20世紀フォックス映画)
2008-06-19_2
●庭から上ったロケット雲 (The Astronaut Farmer/2006/Michael Polish)(マイケル・ポーリッシュ)

◆だいぶまえから試写の知らせを受けていたが、「ありえない法外な話」だという批判を読んでいたこともあって、試写を敬遠していた。今日は、最終に近い試写だった。結果は、たしかに「ありえない」話ではあるが、それなりの理由があってそうなっていることを思うと、なかなかいい作品だと思った。要するに、911以後、テロ防止法などの適用によって深まるアメリカの不自由と過剰な管理への批判がこの映画の前提になっている。アメリカにある「DIY」(Do It Yourself)、つまり何でも自分でやってしまうという文化への執着もえがかれる。家庭は、個々人が自由な活動をする際の「拠点」(home)であるという「伝統的」なアメリカ精神への執着もえがかれる。その意味で、ドラマのなかのFBIやNASAの役人たちのように、主人公たちがやることを「おかしい」と思うことは、それだけ、アメリカの民衆的「伝統」が犯されているということなのだ。
◆おそらく、テロ防止法以前のアメリカでは、個人がロケットを作っても犯罪にはならなかっただろう。事実、「実話」にもとづく映画『遠い空の向こうに』に見られるように、目下NASAなどが独占しているようなアメリカのロケット技術は、民間のアマチュア的な実験からはじまったのである。その意味で、911以後のアメリカは、草の根や民間からの大胆な実験精神や努力を吸い上げて世界で最もユニークなものをつくりあげる可能性を閉ざしてしまったのだ。この映画が、いささかコミカルに見えるとしたら、それは、そうしたアメリカの現実を笑殺しようとしているからでもある。
◆アメリカのDIYカルチャーというのは、根強いもので、とりわけ郊外や田舎に住む人たちの家の地下には大工仕事から場合によっては水道・ガス工事まで可能な工具がしっかりと備え付けられている。ガレージも作業場で、ときには車の一台ぐらい組立てられるほどの装置を持っている家もある。だから、ビリー・ブブ・ソートンが演じるチャーリー・ファーマーが、ロケットを自力で組み立てたとしても、あながち「非現実的」とは言えない。
◆この映画でに出てくる家族、妻(ヴァージニア・マドセン)、息子(マックス・シエリオット)、妻の父(ブルース・ダーン)らは、みな(月並みな言い方をすれば)ノーマン・ロックウェルの絵に出てくるような「善人」たちだ。組織や国家が信じられなくなったとき、アメリカでは家庭・家族回帰が起きる。冷戦の50年代に「反共宣伝」で学校からマルクス主義などの教育が姿を消し、若者が反体制的な思想から切り離されたとき、それを維持したのは、30年代に「左翼思想」にそまった彼らの父親や母親たちだった。だから、60年代の「新左翼」(ニューレフト)は、イタリヤ系とユダヤ系が多かったのである。ソートンとマドセンが演じる一家が、エスニシティからして何系なのかはわからないが、別にイタリア系やユダヤ系ではなくても、国家がおかしな方向に進むとき、それをただす軸になるのが家族・家庭だという伝統がアメリカにはある。
◆細かなことを言えば、家を抵当に入れるほどのぎりぎりの予算で作った最初のロケットの打ち上げに失敗したのち、すぐに再度の挑戦を試み、宇宙を遊泳することに成功するが、これは、やや無理な印象をあたえる。2基もロケットを作る予算はなかったはずだからだ。一回で成功するようにした方が説得力が強まっただろう。
(映画美学校第2試写室/デスペラード)
2008-06-19_1
●落下の王国 (The Fall/2006/Tarsem Singh Dhandwar)(ターセム)

◆冒頭からベートーベンの交響曲第7の第2楽章以下が使われる。前作の『ザ・セル』の殺人や陰惨な幼児期の記憶といったどぎつい要素はおさえられているが、イマージネーションの大胆な飛躍は、前作をうわまわる。1915年、ロサンジェルス郊外のノドカな病院に入院しているスタントマンのロイ・ウォーカー(リー・ペイス)と幼い少女、アレクサンドリア(カティンカ・アンタルー)を中心に華麗で想像力豊かな映像が展開する。アンタルーが病院のなかをさまよっているうちにたまたま訪れたベッドの主が、撮影中の怪我で半身不随になっているペイスなのだが、彼が少女に物語る話が即映像として物質化する。やがて、彼の空想と少女のデフォルメや注文や介入とで入れ子状にシームレスな展開をみせるようになる。
◆『ザ・セル』では、VRシステムのような装置を使って他人の脳に感応できる超能力の女性(ジェニファー・ロペス)がおり、たまたま起こった連続殺人事件の犯人(ヴィンセント・ド・フリオ)が逮捕されたとき、その脳に入り込み、秘密を探り出す。明らかになるのは、犯人の幼児期の父親による虐待であり、分裂した人格のなかにわずかに残っている「純真」な少年的要素であった。この作品では、ヴァーチャルな脳の世界でロペスとフリオとが闘い、彼女が彼を剣で刺すと、装置で天井から吊られた彼の生身は死に、ヴァーチャルな世界のなかでのみ「少年」が生き残るという、ヴァーチャルなものと「現実」とのシームレスな関係に関して、なかなか斬新な視点を提出してもいた。このへん、『落下の王国』では、夢の世界(ペイスの抑圧が入り混じった物語とペイスが病院で出会う人物たちの記憶がないまぜになって出来上がった夢と悪夢)と現実(ペイスがスタントで半身不随になっている/アンタルーが父の農園でオレンジを摘んでいて腕を折ったがやがて全快する)の境が比較的はっきりしている。
◆『落下の王国』では『ザ・セル』よりも、「夢/空想」と「現実」の世界がはっきりと分かれていることに関して、前者よりも後者を高く評価する批評がかなりあるが、わたしは、逆に、本作を通じて、ターセムが『ザ・セル』で、あの一見おどろおどろしい雰囲気にもかかわらず、ブレヒト的な「叙事詩」的手法を導入していたことがわかって面白かった。本作のなかで、ペイスがアンタールに「叙事詩」のことを説明するくだりがある。この叙事詩は、ブレヒト的な叙事詩を包含している。空想の世界と病院の現実とのあいだを行き来する切り替えのタイミングは、ブレヒト的な「中断」ととれる。そしてその意味では、『ザ・セル』が「認識論」的なドラマだとすると、本作は、ブレヒト的な「教育劇」だとみなすこともできる。
◆『ザ・セル』の犯人が幼児期に受けた屈折・トラウマの深さに比して、ペイスがスタントマンとして、あるいはそれ以前の生涯で受けた屈折は、さりげなくしか描かれないが、彼が終始自殺を考え、実行を試みようとしていることを思うと、彼とて、「健康」で単純な生活を送っているわけではないことが想像できる。映画製作の現場で顔を会わせているスター女優への想いと、スタントマンとしての低い地位との落差。撮影現場で彼は決してしあわせではない。そのへんの屈折の強度が、彼が少女に物語る物語のネガティヴな強度とシンクロしている。
◆『ザ・セル』では、登場人物たちの階級性は希薄だったが、本作では、階級性の問題が前面に出ている。空想物語のなかでは、ギリシャかどこかの王国で「総督オウディアス」のもとで奴隷として拘束されている5人の男が登場するが、その登場人物は、すべて、ペイスとアンタルーの日常に登場する人たちである。そして、この5人は、現実には(撮影中の爆発で足を失った)俳優仲間(ロビン・スミス)、アンタルーの父親の農園の使用人(ジ-トゥー・ヴァーマ)、同じ使用人(ジュリアン・ブリーチ)、病院職員(レオ・ビル)、病院に氷を運ぶ人(マーカス・ウェズリー)というように、「被支配者階級」の人たちである。
◆さりげない形でではあるが、アンタールに対するペイスの態度にはある種「幼児性愛」的な要素が感じられる。それは、『ザ・セル』でロペスが少年に対していだく「母性愛」的な愛とも異なる愛情を見せたのと対をなす。
(ショウゲート試写室/ムービーアイ・エンタテインメント)
2008-06-18_2
●闇の子供たち (Yami no Kodomotachi/2008/Sakamoto Junji)(阪本順治)

◆タイの病院で、子供の心臓移植に、生きた子供を使い捨てにしている。その生贄を提供する組織を追う新聞記者(江口洋介)、少女が行方不明になった施設の女性所長ナパポーン(プライマー・ラチャタ)、そこへ日本からボランティアに来た日本人・音羽恵子(宮崎あおい)らが、しだいにその「闇」をあばいていく。心臓病の娘のために高額な金を払ってこの闇のサービスを受けに日本から家族でやってくる日本人商社マンを佐藤浩市が臭く演じている。力作ではるが、クライマックスは詰め込みとはしょりすぎ。それ以前のあまりにゆったりしたテンポをもう少し圧縮し、クライマックスをもっとゆったり描いてもよかった。
◆この映画には、貧しい階級の子供を食い物にしている組織への倫理的・政治的批判がある。つまりこの映画は、「社会派」の表情で作られている。阪本順治は、もともと社会意識の強い監督であるが、わたしは、批判とか告発は内に秘め、もっと映画としてのエモーション(emotion=e-motion)やアクション(動き)が躍動する『顔』、『新・仁義なき戦い』『この世の外へ』などの方がよかったと思う。阪本は、『KT』あたりから狭い意味での「政治色」を強め、『亡国のイージス』でそれにはまった感じになった。だから、『魂萌え!』のような「政治性」が全面には出ない作品では、どこか及び腰の感じが抜けなかった。だから、今回は、フルスロットルの展開というわけである。しかし、近年の阪本の「政治」映画を見ていると、映画が現実を「告発」したりできるというような勘違いしているのではないかという思いをぬぐえない。
◆梁石日の原作は彼のそうした志向をさらに強める結果になった。ちなみに、小説と映画とはメディア的機能が異なる。小説は、映画のように黙って椅子に座っているだけでは入ってこない。映画も色々だが、この映画のように、「完成」されたパッケージとして観客のまえに提出される映画(つまりは「商業映画」)は、それがどんなに現実批判や告発の身ぶりを強調しても、所詮はドラマとして面白いかどうかの(要するに)娯楽の域をこえることができない。知っておかなければいけないのは、商業映画が持つ政治性は、その内容にあるのではなく、そのスタイルと娯楽性にあるということだ。だから、この映画のように、タイのどこかで、子供たちが売られ、売春を強制されていたり、臓器移植の単なるパーツにされているということを「知った」江口やラチャタや宮崎らが、「残酷だ」、「ひどい」といった表情をして見せ、それに観客の感情的・観念的な同化を求めるよりも、ずばりその「残酷さ」や「ひどさ」に観客の感覚を直面させ、ショックをあたえる方がより「政治的」なのだ。この映画は、依然として「印象主義」のフィルターで政治を語る。だから、そうした現実と観客とのあいだを媒介する登場人物たちは、やがて欺瞞を露呈せざるをえない。通常、現実を「告発」する人物は、その現実に闘いをいどみ、勝利したり敗北したりする。この映画で新聞記者の江口は、何度か危険な目に遭うが、殺されることはない。だから、そのかわり、自分もその世界の一部である自分を責めることになる。江口の「最期」がそれを象徴している。もし、阪本が、映画の真の政治性で勝負をしようとしたのなら、こういう結末は選ばなかっただろう。
◆この映画は、ここで描かれる世界を批判しているようで、実は、それを肯定するような意識に観客をいざなう。実際、わたしは、この世界を批判する身ぶりをする江口やプライマー・ラチャタや宮崎あおい、らよりも、幼児売春や臓器売買の現場にいつも登場するプラパドン・スワンバーンの演技にしびれた。ありていに言えば、やくざの中堅的人物なのだが、スワンバーンは、必ずしも非情というわけでも、まただからといって温情があるわけでもない機能的人物を見事に演じていた。彼は決してただの「悪党」にとどまらない演技をしているので、彼の演技の側からこの映画を逆照して見ると、江口らが代表する世界は実に子供っぽい世界になってしまう。
(映画美学校第1試写室/ゴー・シネマ)
2008-06-18_1
●地球でいちばん幸せな場所 (Owl and the Sparrow/2007/Stephane Gauger)(ステファン・ゴーガー)

◆思っていることをずばり言わないことは、依然、日本でも有力な文化だが、いまのタテマエは、そういうものを排除する方向で進んでいる。しかし、体に染み付いた基底文化(その語の本来の意味での「サブカルチャー」)のレベルでは決してなくなってはいないから、ちょっとしたきっかけでぽろりとそういう「つつましさ」の文化が姿をあらわす。ベトナムは、戦後、そして90年代の経済成長によって、社会は大きく変わった。が、そこに住む人々のなかには、依然としてある意味「アジア」的なものが残っているらしい。むろん、ベトナムと日本とは大違いである。ベトナムは、フランスによる植民地化の経験もしている。フランス文化の影響もある。
◆3人の人物を並行的に描き、徐々に合流させていく典型的なスタイルだが、いい仕上がりになっている。一人は10歳の娘トゥイ(ファム・ティ・ハン)。ホーチンミン市の郊外の叔父の竹細工工場で働いているトゥイは、両親がいない。叔父が憎いわけでもないが、慣れない作業を誤り、叔父にしかられると、貯金を持って飛び出してしまう。もう一人は、国際線のフライトアテンダントのラン(カット・リー)。レイオーバーで毎回5日をホーチンミン市で過ごす彼女は、妻子のいるパイロットとの逢引をくりかえしているらしいが、むなしさを感じはじめている。もう一人は、動物園で象の飼育係をしているハイ(レー・テー・フー)。彼は、父親の仕事をついで象の飼育係になった。経営難で子象がインドに売られていくのを悲しんでいる。婚約者ともうまくいっていない。
◆ホーチンミン市にやってきたトォイが、街の子(まさに「シティワイズ」)に助けられて花売りのアルバイトの仕事を得る過程がいい。子供たちの自律した世界と連帯。こういう(厳密に言えば)「非合法」の世界が生き生きと存在しているかどうかが、街の活気の源泉だ。
◆ランが泊まるホテルは、国際線のフライトアテンダントが泊まるのだから、一流なのだろうが、随所に見えるある種の「アジア的」な「つつましさ」(といっていいいのか?)が面白い。
◆この映画の登場人物はみな「つましい」が、とりわけハイは「シャイ」なまでにつましい。婚約者に彼氏がいるらしいとわかっても、確認できず、たまたま街で出会ったトゥイから花を買い、届けさせ、物陰から婚約者がどう反応するかを覗き見する。彼には、象との会話がいちばん安らぐらしい。
◆労働や管理やスケジュール的生活に疲れた人間が、そういうものからはずれたところで出会い、連帯する。それは、家族の「愛」とも恋の「愛」とも「友情」とも異なる何かによって結ばれた関係だ。
◆少女役が見事。全員どこかもの悲しい表情を隠している(50年代の日本の映画の登場人物のように)のは、ヴェトナム戦争の依然残る後遺症か?
◆カット・リーがアオザイを着てスクーターを飛ばす姿はカッコよく、またセクシーである。
(シネマート銀座試写室/エスピーオー)
2008-06-16
●メイド・イン・ジャマイカ (Made in Jamaica/2006/Jérôme Laperrousaz)(ジェローム・ラペルサ)

◆ジャマイカの錚々(そうそう)たるレゲエアーティストたちが顔を見せるが、いささかがっかりした。まず、登場人物が多すぎ、その演奏シーンはみな切れ切れだ。せめて、ノイバウテンのアレキサンダー・ハッケがイスタンブールのミュージシャンを訪ねる『クロシッグ・ザ・ブリッジ』のように、ビッグスター1人1曲ぐらいは見せ、聞かせてほしかった。だが、不満はそれだけではない。この映画は、ある種のモラル・キャンペーン映画で、ビッグスターたちは、みんな本音を語っていないのだ。本音をわずかに目撃できるのは、実演のシーンだが、それが短くてすぐに別のシーンに飛ぶので、欲求不満に陥る。
◆ドキュメンタリーといっても、この映画のために演奏をしているのがわかる。映画向きのライブ。最初にちらりとレゲエ・ダンスのダンスたるゆえん(男女が下半身を密着させる「ワイニー」など)を印象付けたのち、ビッグ・スター「ボーグル」が銃殺されたニュースを報じるテレビ映像を見せる。これは、暗黙の「安全弁」で、以後、冒頭に見られたようなレゲエの本領である奔放さはほとんど移されなくなる。大御所が、どこかモラリッシュなことを言うのを聞かされる。わたしが思うに、暴力もセックスもパニックも、みな、本来は、レゲー・カルチャーのなかにあるものであって、レゲエ・ミュージックが殺人や暴力や暴動と結びつくのを抑えること自体がおかしいのではないか?
◆この映画のなかで、暗黙の「検閲」にもかかわらず、その「地」を出してしまうのが、「エレファント・マン」。さすがである。まあ、「バニー・ウェイラー」のような「長老」が何を語っても味があるから、見て損はなかったが、「サードワールド」のスティーヴン・"キャット"・クーア親子が穏やかに団らん的会話をしているなんぞ、ちょっとちがうなという感じ。
◆しかし、とにかく面子(めんつ)がおびただしいから、DVDで持っていると「辞典」的には役にたつかもしれない。
(京橋テアトル試写室/ヘキサゴン・ピクチャーズ)
2008-06-11
●イントゥ・ザ・ワイルド (Into the Wild /2007/Sean Penn)(ショーン・ペン)

◆大学を優秀な成績で卒業した青年がアラスカの原野への放浪の旅に出かけ、そのまま行方不明になり、3年後、原野に放置された廃バスのなかで死体で発見される。のち、ジャーナリストのジョン・クラカウアーがその足跡をたどって書いたノンフィクションはベストセラーになった。その映画化だが、監督のショーン・ペンの関心は、まず、「運の悪い男」にあったような気がする。というのも、この青年クリストファー・マカンドレス(エミール・ハーシュ)は、極寒の地で食べ物に窮し、野草を集めて食料にしているうちに、たまたま毒草を食べてしまい、全身麻痺に陥って死んだのだった。つまり彼は望んだ死ではなかったのだ。ペンが監督した『プレッジ』のアル中男(ジャック・ニコルソン)も『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』のサム(ショーン・ペン)も、みな運の悪い男だった。
◆クリストファー・マカンドレスは、もともと「つつましさ」への願望があった。「つつましさ」を拒否し、浪費と華麗さを価値とするアメリカ文化に対し、彼は抵抗していた。だから、卒業記念に両親から車を買ってやると言われたとき、それをあっさり断る。彼が、2万4千ドルの貯金をこれまたあっさり慈善団体に寄付し、クレジットカードを切り裂き、現金を燃やしたのも、「文明」との決別のためだった。しかし、彼の皮肉は、その「文明」の産物である「野草辞典」を見間違えたことによって、命を落とすところではないか?
◆冒頭に、ジョージ・バイロンの「断片」からの引用がある。「I love not man the less, but Nature more.」は、しばしば「われわれは人を愛する心の薄きにあらず、自然を愛する心の深きなり」と訳される。
There is a pleasure in the pathless woods,◆アメリカ人には、どこか「自然回帰」的な志向がある。クリストファーのアラスカ行きにもそうした流れが入り込んでいただろうが、この自然回帰には、一人になるというローナー志向もある。ヘンリー・デイヴィッド・ソーローの『森の生活』がその典型だ。自然と孤独。が、この孤独は孤立ではない。一人でいることによって、自然と共生し、万人と一体になるというロマン主義的自然主義である。クリストファーは、アラスカの原野でそれを実現したが、その過程で潰えた。これは、ロマン主義的自然主義への皮肉であるはずであり、この映画をそういう観点から見ることもできるが、原作とこの映画を賞賛する人たちは、クリストファーをヒーロー化する。
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more.
◆アラスカへの途中でクリストファーがアルバイトをさせてもらう大麦畑(?)のオーナーがFBIの急襲を受けて捕まるシーンがあるが、逮捕の理由は、たしか、衛星通信の傍受装置を作って持っていたからだったように思えた。
◆クリストファーの旅の途中で、ヒッピーとかヌーディストとかのコミュニティーが映る。クリストファーがしばらく身を寄せるジャン・バレス(キャサリン・キーナー)とレイニ(ブライアン・ダーカー)は、ヒッピー・カップルである。キーネーがいい感じを出している。
◆「親の心子知らず」ということわざがあるが、「子の心親知らず」というのもあるらしい。クリストファーが自然に回帰した背景には、両親の不和、父親の母親への暴力といった子供時代の「トラウマ」があったらしい。わたしなぞ、若いときには、いつも、「子の心親知らず」だと自分の親を呪っていたが、彼らが死に、嫌な記憶が時間のなかで洗い流されていくにつれ、自分が「親の心子知らず」だった部分の多さに気づき、赤面する。「孝行のしたいときに親はなし」というやつだが、つっぱって生きている10代や20代のときには「親の心」なぞ絶対にわからない。いや、わたしは30代、40代でもわからなかった。いまになって、わたしは、ようやく、この映画を主人公クリストファーの観点だけからではなく、その両親の観点から見ることができる。長期にわたって音沙汰がなく、突然その死を知らされる両親に若干の同情を禁じえないのだ。子供のとき、あんたたちがやっていたことが「トラウマ」になったというのは、いま流行りの論法だが、クリストファーの父親は、彼に対して大した虐待をしたわけではないから、親の側からすると、夫婦喧嘩ぐらいやらしてくれよという言い分もなりたつのである。
◆全体として、旅の途中でそれぞれに魅力的な人物と会うところは、「教養小説」(ビルドゥングスロマン)の形をなすが、その経験を活かすことが全くなく、死んでしまうところが、「セラヴィ」とも、残念ともとれる。ショーン・ペンはそんなところに興味を持ったのかも。
◆原作を書いたジョン・クラカウアー(Jon Krakauer)は、「kauer」の「k」と「c」の違いはあるが、あの『カリガリからヒットラー』への著者にしてワルター・ベンヤミンの友、ジークフリート・クラカウエル(Siegfried Kracauer)の親戚かなにかかと、少し知らべてみたが、詳細は不明だった。わたしは、その昔、ニューヨークに亡命して先述の書を書いていた時代のクラカウアーのことが知りたくて、ニューヨーク時代のクラカウアーの親友のポール・オスター・クリステラー(Paul Oster Kristeller, 1905-1999)に会ったことがある。
(ショーゲイト試写室/スタイルジャム)
2008-06-03_2
●バーナードとドリス〔仮〕(Bernard and Doris/2007/Bob Balaban)(ボブ・バラバン)

◆この作品は、実は、5月30日に成田からトロントへ向かう飛行機の上空(アラスカあたりですか?)で見たんですが、帰りにもう一度見直したので、『サヴェジ家』のあとにレイアウトします。
◆律儀だね。ひねったラブストーリーとしてはいい出来だと思うな。『RollingStone』なんかの評価は高かったね。HBOの映画だけど、2007年10月のハンプトンズ・インターナショナル・フィルム・フェスティヴァルで初上映されたあとは、一般劇場では公開されなくて、ケーブルだけで上映されたんだってね。「公式サイト」もないし、いまはDVDで見れるけど、ある種の「検閲」にあったのね。タバコもぷかぷか、ドラッグも酒もとくると、いまのアメリカでは、やばいのかな? 実在のドリス・デューク(1912~1993)のサイドから圧力がかかったのかもしれない。ドリスの遺産は、いろいろな財団に寄付されて、文化的な貢献をしているんでしょう。 ドリスが相当やばい生活をしていたことはよく知られているとしても、いまそれを暴かれるのはまずいのかな?
◆「実話にもとづいている部分もあるし、創作の部分もある」と断っているのに、実在のドリス・デュークとの違いに目くじらたてている評もある。全然映画としては見ていない。どんなに「実話」にもとづく映画でも、映画は映画でしょう。とにかく、もう歳はいってるけど、億万長者のわがままな娘(スーザン・サランドン)とゲイの執事バーナード・ラファティ(レイフ・ファインズ)という組合せもドラマ的に面白いし、アル中という点で接点を持ち、信頼しあうという関係も身につまされましたね。サランドンもファインズも、いつもよりワンランク上の演技になっていたんじゃないか。音楽も、実在のドリスが好きだったペギー・リーのヴォーカルを軸にしたジャズでまとめ、おしゃれに仕上がっています。
◆レイフ・ファインズは、見事な演技をしてるね。ドラッグとアルコールに溺れたことがあるゲイの中年男。執事の部屋をもらって、荷を解くと、壁にエリザベス・テイラーの写真をかける。テイラーって、ゲイに評判がいいんだね。ただ、バーナードは、ゲイでも、むしろトランスセクシャルな方向なのかな? わがままで、執事が持ってきた食べ物がまずいといって即刻くびにしたサランドンのまえに新しい執事としてあらわれたファインズは、どんどん気に入られていく。ファインズが従順に従ったからだけど、ただ従順で気がつくという「従者と主人の物語」のノリじゃないんだな。最初は上下関係だが、だんだんそれが逆転するというパターンもあるが、そうなるわけでもない。相性というか、彼が「美形」だったからかとか、老いさらばえた彼女が最後に命を彼に託すわけだから、ある種の「純愛」だとか、ま、いろいろ想像させてくれる。その一方、彼女の遺言で、膨大な遺産を彼が引き継ぐわけだから、この間の彼の「忍耐」はしたたかな演技だったのではないか・・・といった想像もできる。映画って、そういう観客側での「創造」の余地が大きいものほどレベルが高いと思うんだけど、その点では、いい線いってますよ。
◆サランドンは、職業紹介所の情報かなにかでやってきたファインズの履歴書を最初はろくすっぽ見ないんだけど、そのうち、気をとりなおして読むわけです。そして、彼にドラッグとアルコールの中毒歴があることを知り、むしろ好感を持つわけです。それは、彼女自身がすでに相当なアル中だったからでしょう。中毒者同士の「愛」というと、オーストラリアのジリアン・アームストロングの『オスカルとルシンダ』を思い出します。この映画では、レイフ・ファインズとケイト・ブランシェットがギャンブルにのめり込むわけだけど、ファインズはアングリカンチャーチの牧師なんです。おそらく、ファインズがこの作品に出ていたことと、『バーナードとドリス』のバーナード役に抜擢されたこととは無関係ではないような気がします。
◆監督のボブ・バラバンは、俳優として有名だけど、テレビシリーズでは20本以上の作品を演出しているのね。俳優としての彼は、けっこう見ているなあ。最初は、『真夜中のカーボーイ』でトイレでジョン・ヴォイトと出会って、ブロー・ジョブをやる学生役だったと思う。なれないのに無理して気持ち悪くなる役ね。最近では、『幸せのレセピ』でキャサリン・ゼタ=ジョーンズがかかっているセラピスト役で、彼女の料理の味見役でもある。あの映画ではなんか別格的な存在になっていたけど、監督のスコット・ヒックスが一目置いているんだろうね。『レディ・イン・ザ・ウォーター』のスノビッシュな映画評論家役も記憶に残っている。
◆あと、ドリスの「つばめ」といった感じで、ピアノをばりばり弾く浅黒い若者がいますね。ドリスを慰めたあと、眠り込んだ彼女がふと気づくとベッドのかたわらに彼がいない。メイドの部屋に行ってみると、そいつがメイドとやってる。頭に来た取りすが即刻追い出す。
◆ちょっと気の毒な感じがしたけど、あいつは、れっきとしたジャズのピアニストで、ドラムのエディ・ゴメス、ベースのレジー・ワークマン、セシル・マクビー、トランペットのジミー・オーウェンスなんかとも共演してるんだってね。あのピアノはなかなかよかった。彼のピアノ演奏で、ファインズとサランドンがペギー・リーの曲を歌うシーンは、2人とも下手だったけど、ムードはノッてたね。
(エア・カナダ/トロント→成田機上)
2008-06-03_1
●サヴェジ家〔仮〕(The Savages/2007/Tamara Jenkins)(タマラ・ジェンキンス)

◆今月からすこし気分を変えようというんだけど、これまで飛行機のなかで見た映画を取り上げるようなことはしなかったよね。それと、会話体というやつも。今後は日本未公開のDVDなんかも取り上げるとか?
◆そう、硬いのもナンなので、このあたりで変えてみようかと思う。同じスタイルで10年以上やってきたから。
◆でもさ、むかしあなた書いてなかったっけ? ひと続きの散文体で書いていた奴が対話体の原稿を書き始めると、大体は、手抜きだって。散文体で書く暇がなくて、そうなるんだと。
◆たしかに、活字の場合はそういう面はあるけど、ネットの場合は違うんではないかと思う。かえってダイナミックな感じがしていいのでは。
◆とにかく、やってみなけりゃわからないから、行きますか。タイトルは、「サヴェジ家の人々」といった意味だけど、「savage」には、「残酷な」とか「荒涼とした」といった意味もあるね。話は、父親(フィリップ・ボスコ)を老人ホームにいれっぱなしできた兄妹(フィリップ・シーモア・ホフマンとローラ・リニー)が、父親の認知症がひどくなって身近にいてやらざるをえなくなる。ここまでは日本でもよくあるパターンなんだけど、だんだんわかってくるのは、実は、この父親は二人を幼児虐待していたんだね。ホフマンは、大学でブレヒト演劇を教えているという設定だが、あいかわらず手堅い演技ですな。リニーは、『トゥルーマン・ショー』でニセモノの妻を演じたイメージが残っていて、どっかで「なんちゃって」をするんじゃないかという心もとない感じがするんだが、今回はしっとりとした感じを出しているね。ボスコは、名端役というか、古くからいろいろな作品に顔を出している人だよね。
◆ローラ・リニーは、『ライフ・オブ・デビド・ゲイル』あたりから存在感のある演技をしてる。ただ、どこかに不安や神経症的なものを宿している役がうまい。今回も、そういう感じ。ただ、せっかくボスコを登場させながら、事実上でくの坊的な老人役で、息子や娘との交流が浅いような気がする。それが、認知症だといえばそうなんだが、もうちょっとあってもよかったかなと。そして、割合あっさりと死んでしまうので、じゃあ焦点はどこだったのか、リニーなのかホフマンなのかと分裂した印象を持ってしまう。
◆だから、基本は兄妹愛なのかな。ホフマンが教室で「叙事詩的演劇」(Epic Theater)なんて黒板で書いているシーンがあったけど、何でブレヒトなのかね?妹も劇作家志望で、グッゲンハイムの賞を取ろうとしてる。そのためかどうかわからないが、見るからに凡庸な男(ピーター・フリードマン)――元先生だっか?――と寝てる。半分いやいやみたいに。
◆なんでブレヒトかはわからないが、ホフマンが車のなかでロッテ・レニヤが歌う「ソロモン・ソング」に合わせて歌詞を歌うシーンには、なんかブレヒトへの愛を感じる。この歌は、ブレヒトとクルト・ワイルの作で、『三文オペラ』で使われた。要するに監督がブレヒト好きということじゃない?"
◆しかし、それにしちゃあ登場人物はよく泣くね。特にホフマンが。ブレヒトの「叙事詩的演劇」の理念に反するんじゃない? ハハハ。ブレヒトは、観客に登場人物との「同化」を求めるスタニスラフスキー的演劇に対して「叙事詩的」演劇を対置したわけだけど、ハリウッドは、リー・ストラスバーグがモスクワからスタニスラフスキー・システムを持ってきたのを演技のスタンダードにしたわけね。いまでも彼の「アクターズ・ストゥディオ」はハリウッド俳優の登竜門になっている。タマラ・ジェンキンスは、ニューヨーク大学の大学院で映画を学んだそうだから、「アクターズ・ストゥディオ」とは一線を画しているつもりなんだろうがね。
◆しかし、全体としては、それぞれが悩みや危機をかかえているが、典型的なハリウッド映画のようにめでたしめでたしで解決するんじゃなく、それらと馴れ合っていくというか、そういう現実感は評価できる。兄の方も、ポーランド人の恋人がいて、別れそうになっていたり、それぞれに人生の危機をいだいているところに、父親が施設でおかしくなって、トイレの鏡に自分の糞で字を書いてしまうというさらなる危機にみまわれる。そういう彼が、自分を虐待していた父親のもとにもどって世話をするというのは、相当な決断。妹ともずっと会っていなくて、二人は、父親のところに来たのを彼のためというより、自分らの弱みからだと思っている。親を放置したことへの倫理的な呵責に埋め合わせをつけようとしているだけなんじゃないかと。
◆うん、それはそうなんだが、それだからこそ反ブレヒト的だと思うんだ。モチーフ的には、タマラは、ブレヒト=非エモーショナルという月並みな「ブレヒト」イメージを利用し、ホフマンが幼児期に父親から虐待されたために非エモーショナルになり、ブレヒトを専攻し、恋人に対しても愛情の欠けた対応をするといった、ブレヒトには気の毒な動機がないでもない。それに、ブレヒトだったら、もっと非情な場に観客を引き込んで、観客自身にそういうことを体験させるというスタイルを取ったと思うんだけど、この監督は、そういうことを登場人物自身に言わせたり、その悩みや呵責を感情表現して、観客に「同化」を求めるわけね。そこが問題かな? ただ、アメリカ社会との関係で言えば、この映画は、これまでの自己中心的、競争主義的な社会観、他者観から、もうすこし「わけあう」(シェアー)の意識というか、そういうものを映像化しようとしていることは確かだね。
(エア・カナダ/トロント→成田機上)